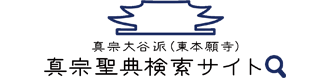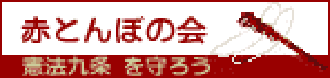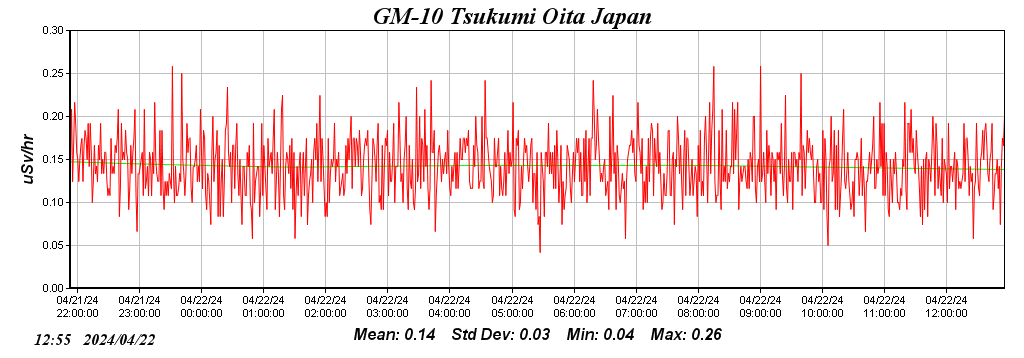『解読浄土論註』現代語訳 下
- utubnen
- 2023年1月25日
『解読浄土論註』の現代語訳解読を見て記載しています。『解読浄土論註』は1975年10月25日大分光西寺での育成員学習会に出席の際求めたものです。
青字は『教行信証』に引文された箇所。あるいはリンク(クリックすると他にジャンプ)箇所
紫字は『解読浄土論註』の細註、『真宗新辞典』
橙字は参考文献
参考資料
『無量寿経優婆提舎願生偈』の書き下しは、東本願寺出版発行の『真宗聖典』によっています。
『往生論註』原文のリンク先は聖教電子化研究会です。
この背景色は『浄土論』の解読です。
この『解読浄土論註』の解読(現代語訳)文で改めたところがあります。
309頁 「舌を抜かれる苦しみ、瘖瘂の苦しみ」の「瘖瘂の苦しみ」を削除。
394頁 「衆生の種類に応じて救済し」の「の種類」を削除。
417頁 「ロバにまたがっていくこともできないような下賎の者」の「ような下賎の」を削除。
目次 『大乗仏典 中国・日本篇 第5巻 曇鸞 浄土論註』参照
一 『浄土論』の組織
三 仏の智慧より生ずる信心(起観生信)
① 五念門の力用
② 五念門の相
1 礼拝門
2 讃嘆門
3 作願門
4 観察門
5 回向門
四 浄土の世界観(観察体相)
① 仏国土の荘厳の成就
1 仏国土の不可思議力
2 仏国土荘厳の十七種を示す
清浄、量、性、形相、種種事、妙色、触、三種(水・地・虚空)、雨、光明、妙声、主、眷属、受用、無諸難、大義門、一切所求満足功徳
3 自利利他の示現
4 真理(第一義諦)を明かす
5 荘厳の総相と別相
氷上燃火の喩
② 仏の荘厳の成就
1 仏荘厳の八種を示す
座、身業、口業、心業、大衆、上首、主、不虚作住持功徳
2 如来の本願力の目覚め
3 如来の自利と利他の成就
③ 菩薩の荘厳の成就
1 菩薩四種の正修行を示す
不動遍至、時遍至、無余供養、遍示三宝功徳
五 願心の荘厳(浄入願心)
1 一法句と三種荘厳
2 一法句とは清浄句なり
3 二種世間清浄
六 方便による衆生救済(善巧摂化)
1 柔軟心のめざめ
2 無上菩提の歩み
九 智慧・慈悲・方便の名とその意味(名義摂対)
1 般若と方便
2 菩提心を障げるもの
3 三種の清浄心
十一 衆生救済の行の成就(利行満足)
1 五種の門と五功徳の相
2 自利の成就と利他の成就
3 阿弥陀如来を増上縁とする
『解読浄土論註』194頁
無量寿経優婆提舎願生偈註 卷下
一 『浄土論』の組織
論じていわく。
これ(よりこの論にのべられるの)は解義の分である。
この分の中の義は十重になっている。
一には 願偈大意
願(生)偈の大意(をあらわす)。
二には 起観生信
(安楽国の)観(察)を起して信(心)を生ずる(についてのべる)。
三には 観行体相
観(察)の行の(三種荘厳の)体相(をあかす)。
四には 浄入願心
(その)浄(土の体相)が、(法蔵菩薩の)願心に入る(ことを説く)。
五には 善巧摂化
(その願心によって、衆生を)善巧に摂め(教)化する(菩薩の回向門を説く)。
六には 離菩提障
(回向門を完成して)菩提の障(害)を離れる(心を説く)。
七には 順菩提門
(それによって)菩提の門に順ずる(心を説く)。
八には 名義摂対
(障害となる心と順ずる心との)名義を摂めて対べる。
九には 願事成就
(それによって)願(生)の事(業)がまったくととのった(ことをあかす)。
十には 利行満足
(以上によって、仏の)自利利他の行がまどかに満たされた(ことをあかす)。
「論」とは、議すことである。つまり、偈の所以を議すのである。「曰」とは詞のことで、以下の諸諸の句を指している。つまり、これらは偈を議し解釈する詞である。だから「論じて曰う」というのである
(さて)願(生)偈の大意は(論につぎのようにいわれている)。
二 「願生偈」の大意(願偈大意)
この願(生)偈はどのような意味を明らかにするか。
彼の安楽国世界を(心に)観じ、阿弥陀如来を見たてまつって、彼の国に生まれたいという願いをしらせあらわすものにほかならない。
『解読浄土論註』200頁
三 仏の智慧より生ずる信心(起観生信)
①五念門の力用
起観生信とは、この分の中がまた二重になっていて、一には五念門の力用を示し、二には五念門の相をあらわすのである。
五念門の力用を示すとは(論につぎのようにいわれている)
どのように(安楽世界を)観じて、どのようにして信心を生ずるのか。
もし善男子・善女人が、五念門を修め、その行ができあがるなら、かならず安楽国土に生れて、彼の阿弥陀仏を見たてまつることができるのである。
② 五念門の相
つぎに五念門の相をあらわすとは(論につぎのようにいわれている)。
どのようなのが五念門か。
一には礼拝門、二には讃嘆門、三には作願門、四には観察門、五には回向門である。
門とは、入りもし出もするという義をいうのである。人が門をたてれば、それによって入るも出るも思いのままにできるように、前の四念は安楽浄土に入る門、後の一念は慈悲(をもって衆生を)教化するために出る門である。
1 礼拝門
どのように礼拝するのか。身の業をもって、阿弥陀如来・応・正遍知を礼拝したてまつるのである。
仏如来がたの徳は無量にある。徳が無量だから、その徳をたたえる号も無量である。もし、それらについてことごとく語ろうとすれば、とても紙や筆にしるせるものではない。だから、いろいろの経典に、十名をあげたり、三号をのせたりしているが、およそこれらは、最も尊い意味を含んだものだけであって、どうして(仏の徳が)それだけでつくされるということがあろうか。ここでいわれている三号は、すなわち如来と応と正遍知とである。
「如来」とは、ものの相その如にさとり、その相の如に説いて、仏たちが安穏の道より来られたように、この阿弥陀仏もまたそのように来られて、ふたたびまよいの生存にもどることはない。だから「如(より)来(る)」というのである。
「応」は応供である。仏は煩悩をことごとくのぞき、あらゆるものに通達した智慧をえて、一切の天地の生きているものの供養を(真実に)受けるに応しい(唯一の)かたである。だから「応」というのである。
「正遍知」とは、あらゆる諸法は(とこしえに)破壊されることがないのが実(相)であって、増えることも減ることもない、と知るのである。どのように破壊されないかといえば、(諸法の実相は)心もおよばず、言葉もたえたところであって、いわば諸法(の実相)は、涅槃の相の不動であるのと少しもかわらないのである。だから「正遍知」というのである。
(論に阿弥陀とあるのは無碍光ということであるが)無碍光という意味は、前の偈のところで解釈したとおりである。
その故は、彼の安楽国に生まれたいとの意をなさんがためである。
どうして、こういわれるかといえば、菩薩の法では、つねに昼三時(晨朝・日中・日没)夜三時(初夜・中夜・後夜)に、十方のすべての仏たちを礼拝するが、これは必ずしも願生せんとの意をなすがためではない。
いまは、つねに願生の意をなすべきであるからこそ、阿弥陀如来(一仏)を礼拝したてまつる、というのである。
善男子・善女人
法を聞いて信受奉行するところの善根をもった在家の男女。『智度論』巻三十五報応品に、「『般若経』で四天王などをいうときは、善天といわないのに、人間をいうときだけなぜ善男子・善女人というのか」と問い、「答えて曰く。諸天は皆、天眼・天耳・他心智有りて、菩薩を供養することを知るが故に、別してその善を説かず。人は肉眼を以て見れば知なし。善者は能く知りて供養す。少なきを以ての故に、別して善者を説く。善者は仏より法を聞き、或は弟子の菩薩より聞き、或は記を受けて当に作仏すべきを聞き、又は仏、其の名を讃嘆したもうを聞くが故に、知りて善を修す」とある。
入出
入は自利、出は利他のこと。往相と還相ではない。
十名
如来・応供・正遍知(等正覚)・明行足・善逝・世間解・無上士調御丈夫・天人師・仏・世尊。『法華経』序品『涅槃経』巻一『大経』巻上等に出る。
如来
tathāgata(tathā 如+āgata 来)。如実に来至せし者、如実より到来せし者。
『解読浄土論註』207頁
2 讃嘆門
どのように讃嘆するのか。口に業をもって讃嘆するのである。
「讃」は、ほめあげる。「嘆」は、うたい、たたえることである。讃嘆は(人間においては)口に、のべねば、あらわされない。だから「口の業」というのである。
彼の如来のみ名を称え、彼の如来の、ひかり明るい智慧の相そのままに、み名の義そのまま、その実の如に、修行して相応しようとおもうからである。
「彼の如来の、み名を称える」とは、無碍光如来のみ名を称えることである。
「彼の如来の、ひかり明るい智慧の相そのままに」。ひかり明るき智慧の相とは、仏のひかりの明るい、かがやきは智慧の相であって、この明るさは、あらゆる世界を照らして、さまたげるものなく、よく生きとし生けるものの無明の(黒)闇を、とりのぞくのである。それは、日や月や珠のひかりが、ただ空穴の中の闇を破るだけのような(小さな)ものではない。
「彼の(如来の)み名の義のまま、実の如に修行して相応しようとおもうからである」とは、彼の無碍光如来の名号は、よく生きとし生けるもののすべての無明をやぶり、よく生きとし生けるもののすべての志願を満足させるのである。
しかし、み名を称え(阿弥陀仏を)おもいつづけても、無明がなおあって、願いが満足しないのはなぜかといえば、それは(如来の)実の如に修行しないのと、み名の義に相応しないということによるのである。
どうして実の如の修行でなく、み名の義に相応しないことになるかといえば、(この無碍光)如来は、実相の身であり、衆生のためにこそ(仏になられたところ)の身である、ということを知らずにいるからである。
また、相応しないことに三種有る。
一には、信ずる心が純朴でなく、信じたり疑ったりするからである。
二には、信ずる心が(専)一でなく、決定する心がないからである。
三には、信ずる心が相続せず、ほかの念がまじるからである。
この三つは、たがいに修行しあって、なりたっている。つまり、信ずる心が純朴でないから決定する心がなく、決定する心がないから念が相続しないのであり、また念が相続しないから決定の信がえられず、決定の信がえられないから心が純朴でないのである。
このようでないことを、「実の如に修行し相応する」というのである。だからこそ、論主はまっさきに「我れ一心に」と宣言されたのである。〔信p.213-214.232〕
私たちには仏陀は、釈尊という固有名詞か、さとりを指す一般名詞としか受けとられませんから、改めて信ずるという行為はできませんし、また、反対に仏を超能力者と考えると、超能力者と考えること自体が信心であって、この信心も特に自覚と関係なく、ただ、効果があるのかないのかの方向にいってしまいます。いずれにしましても、仏と会うという信心はうまれません。
ですから『論註』は「仏を信ずる因縁」があるというのです。仏が信ぜられるには信ぜられる因縁があって、それを曇鸞は「如来は是れ実相身なり、物の為の身なりと」知ることだといいます。
ここでいわれる「為物身」の代表的な仏は釈尊ですが、すでに過去となっている仏です。教理的理解を別にすれば、既に過去である意味で実相身ではありません。既に過去ですので「身」がないからです。
すると釈尊は「実相身・為物身」の条件を欠きます。
では阿弥陀如来はどうであるかといえば、この如来は釈尊の説法においてのみ存在理由が認められるだけで、私たちと接する「身」がかんぜられませんので「為物身」の条件を欠くことになります。
このように見てきますと、曇鸞のいうように「如来は実相身・為物身」とは知り難いのです。曇鸞が如来を二種の身で表現されましたのはやはり、信心の省察によるものでしょう。曇鸞は南無阿弥陀仏の名号にこの二種の身を見られたのでしょう。
つまり、私たちに主格を確立させるはたらきの面からいえば、「為物身」です。だからといって人格的な仏がどこかに存在するのではありませんから、「実相身」です。実相・為物ともに「身」をあらわしますのは、現在性ということと業(はたらき)をあらわすためでしょう。
しかし、このように仏陀が受け入れられるということが私たちには困難なのでしょう。この困難を超えるためには、ひたすら、私たちが求める不退転―自己同一の方向・方法が吟味されていく以外ないでしょう。そしてそれは私たちが既にもっている盲信的なものが吟味されて、正信に趣くことに外ならないでしょう。
だれ一人として、無信のものは存在しません。「わたし」を主格として生きる限り「他者」に「よりかかり、よりたのむ」で生きています。それがただ本人に知られていないだけです。つまり、盲信状態にあることです。それ盲信が破れれば、不信に変わるだけです。無信と不信は違います。
私たちは盲信―不信の間を自己同一を求めて右往左往しているだけなのでしょう。
これは全く自己同一、信心の問題なのです。その意味で、仏を信ずる、という一事をとりあげ、人間の盲信―不信を破って、主格を回復させる正信を獲得せんとしたものこそ『大無量寿経』の正意である、と曇鸞も親鸞も受け取られたようにおもいます。
もちろん、これだけで「信」の問題がつきるわけではありません。「信」を問題とすれば、必ず「教え」につきあたります。また、この「教え」と「信」とによって「機」が決定してきます。この教・信・機こそ、親鸞の人間理解のキーワードと考えられます。『教行信証』の構造を見ればすぐわかることです。
その意味で、「信」を教えと機の関連の中で捉えなおすことがなされなければなりませんが、それは次回に譲ることにします。『浄土論註』講義Ⅰ平野修著
実相 『真宗新辞典』
すべてのもののありのままのすがた。形相を超えた真実のすがた。涅槃の異名。また、弥陀の名号、浄土の荘厳をいう。「諸法実相」〔観経―論註〕。「一切法の不可得なる、是れを仏道と名づく、即ち是れ諸法の実相なり」〔智論―要集〕。「仏地の果徳真如実相第一義空」〔観仏三昧経―安楽―行〕「真実の智慧は実相の智慧なり、実相は無相なるが故に真智無知なり」〔論註―証〕。「如実知とは実相のごとくして知るなり、広の中の二十九句、略の中の一句、実相にあらざることなきなり」〔論註―証〕「無為法身は即ち是れ実相なり、実相は即ち是れ法性なり」〔証〕「如来は常住にして変易あることなければ名づけて実相という」〔涅槃―真〕。「涅槃をば…無為という、…実相という、法身という」〔唯文意〕
実相身 為物身 『真宗新辞典』
真如の理としての仏身である理法身を実相身、物すなわち衆生のためにあらわれた仏身である智法身を為物身という。不如実修行の釈「如来は是れ実相の身なり、是れ物の為の身なりと知らざるなり」〔論註―安楽・信〕。実相身と為物身を法性法身と方便法身に配し、或は方便法身の中の自利と利他、光明と名号にあてる解釈がある〔六要〕。
『解読浄土論註』212頁
問。名は法をしめす指である。たとえば、指で、日をさししめすようなもので、もし仏の名号をとなえて願いが満たされるというのなら、日をさししめす指は闇を破りえるはずである。日をさししめす指が闇を破りえないのなら、仏の名号をとなえることも、またどうして願いを満たすことができようか。
答え。諸法は万差である。一律に(固執)すべきではない。名が法に即している場合もあり、名が法と異なっている場合もある。
名が法に即するとは、仏・菩薩がたの名号・般若波羅蜜及び陀羅尼の文句・まじないのことば、などである。
たとえば、腫をなおすまじないに、「日出東方乍赤乍黄」などという句があるが、たとえ酉亥(午后五時から十一時頃の間)にこのまじないをとなえて、日の出にはあずからなくても、腫は差るのである。また、師に出向いて(敵)陣と対した場合、歯をくいしばってただ一たび、「臨兵闘者皆陣列(在)前行」ととなえるようなもので、この九字をとなえれば、(弓・矢・矛など)五兵にあたることがないのである。『抱朴子』には、これを大切な道といっている。また転筋で苦しんでいるとき、木瓜を火にあぶって痛むところを慰すと、たちまち愈るが、また人あって、ただ木瓜の名を呼ぶだけでも愈ってしまう。これは私の身に(ためして)その効をえたことがある。
このような卑近な事(例)は、世間で(一般に)みな知っていることである。まして不可思議の(尊号の)境界ではなおさらのことである。滅除(という名の)薬を鼓に塗るという喩えも、この一事(例)であるが、この喩えはすでに前にあきらかにしたから、重ねて(ここに)は引かない。
名が法に異なる場合があるとは、指で、日をさししめす場合などの名のことである。
如指指日 指をして日を指ふるが如し。
加点本以外の諸本では日を月に作る。智度論巻九十五「人の指を以て月を指すに、知らざる者は、但だ其の指を観て月を視ざるが如し」とある意
有名即法 有名異法 名の法に即する有り、名の法に異する有り
即は合・不離の意。異は離・分・別の意。
禁呪・音辞
まじないのことば。(呪はのろい、禁は忌みさける、とめる)
日出東方云云
中国に古くから伝わっていた呪文の一種であろう。文そのものに深い意味があるわけではなく、声をあげてとなえるところが禁呪の力用である。(それ故、音辞という)いまは「日出」の二字の意味にかけて、反ってそれ自体に意味があるのでないことを説いている。
臨兵闘者云云
『抱朴子』・内篇第十七に出ることば。原文には「在」の一字はない。筆者しているうちに誤って入ったと考えられる。
五兵
戦闘に用いる五種の兵器。
『解読浄土論註』216頁
3 作願門
どのように作願するのか。心につねに願いをなすよう、一心に専ら(阿弥陀如来を)念じて、ついに必ず安楽国土に往生して、実の如に奢摩他を修行しようとおもうからである。
「奢摩他」を訳して止という。止とは、心を一つ処に止めて、悪をなさないことである。
この訳名は、大よその意味に、たがうことはないけれど、まだその意味は充分でない。なぜかといえば、心を鼻の端に止めるような(観法)をも止と名づけるし、不浄観(法)は貪(欲)を止め、慈悲観(法)は瞋を止め、因縁観(法)は(愚)痴を止めるが、このようなものもまた止と名づける。人が(どこかへ)行こうとして、行かないような場合も、止と名づける。
これで、止という(訳)語は大づかみであって、正確に奢摩他という名を、あらわしたとはいえないことがわかる。たとえば、椿や柘や楡や柳はみな木と名づけるけれども、もし単に「木」といっただけでは、どうしてそれが楡とか柳とかにあてはまろうか。
ここで奢摩他を止というについては、三つの義がある。
一には、一心に専ら阿弥陀仏を念じて、彼の(国)土に生れたいと願えば、この如来の名号及び彼の国土の名号が、よくすべての悪を止めるのである。
二には、彼の安楽(国)土は、三界の道をこえているから、もし人が彼の国に生れれば、自然に身や口や意の悪を止むのである。
三には、阿弥陀如来の正覚の、とこしえに(衆生を)たもたれる力によって、自然に声聞・縁覚(の利己的なさとり)を求める心を止められるのである。
この三種の止は、如来の実の如の功徳より生ずる。
だから「実の如に奢摩他を修行しようとおもうから」といわれるのである。
止心鼻端
五停心観(仏道修行の最初の位において、五種の過失を止めるために修する五種の観法)の一つである数息観のこと。出入の息を利益念持して、数を計え、散乱の心を治する観法。
不浄観
同じく五停心観の一つ。境界の不浄なありさまを観じて、貪欲を止める観法。
慈悲観
同じく五停心観の一つ。一切衆生を観じ慈悲の念を生じ、瞋恚を止める観法。
因縁観
同じく五停心観の一つ。諸法因縁生の理を観じて、愚痴を止める観法。なお以上の四つ(四度門)の他に、第五として界分別観(五蘊・十八界等の道理を観じて、我見を止める観法)又は念仏観(仏を念じて種々の煩悩を止める観法)があるが、いまは「等」の字に摂められている。
『解読浄土論註』220頁
4 観察門
どのように観察するのか。智恵をもって観察するのである。正しい念によって、彼(の国土)を観(察)し、実の如に毘婆舎那を修行しようとおもうからである。
毘婆舎那を訳して「観」という。単にひろく観というのでは、またその意義が充分ではない。
なぜかといえば、(わが)身の無常・苦・空・無我・九想などを観ずるようなものも、みな観と名づけるから、これもまた上(述)の木という名だけでは椿とか柘とかがはっきりしないのと同じである。
(ここで)毘婆舎那を観というにも、また二つの義がある。
一には、此(の穢土)に在りながら、想いをなして彼の(浄土の)三種の荘厳(仏国土・仏・菩薩)の功徳を観ずるなら、この功徳は実の如であるが故に、修行するに、ともなって、その実の如の功徳を得るのである。実の如の功徳は、必ず彼の(浄)土に生れることができるのである。
二には、また彼の浄土に生れることができれば、ただちに阿弥陀仏を見たてまつり、まだ浄心を証っていない(七地已下の)菩薩が、畢竟(八地已上の位たる真如)平等の法身をさとることができ、浄心の(八地の)菩薩と上地(九地・十地)の菩薩とも、同じく畢竟寂滅平等(の涅槃の境地)を得るのである。
だから「実の如に毘婆舎那を修行しようとおもうから」といわれるのである。
彼(の浄土)を観察するについて三種ある。
一には、彼の仏国土の荘厳の功徳を観察する。
二には、阿弥陀仏の荘厳の功徳を観察する。
三には、彼の(国土の)菩薩がたの荘厳の功徳を観察する。
心に、その(三種の荘厳の)事(相)をおもい、うかべることを「観」といい、観ずる心がはっきり明らかになることを「察」という。
九想
身の不浄を観ずるために、人の死骸にあらわれた九つの相を想うこと。
二者亦得生云云 二には亦彼の淨土に生を得れば、即ち阿彌陀佛を見たてまつる。
この一段の文は、浄土論の長行の不虚作住持功徳成就の文(後に掲載)そのままの引用である。論註は、この不虚作住持功徳の成就が、阿弥陀如来の本願力によることを力説されているが、その感銘をもって、いまここに論の文そのままを引用されていると考えなければならないだろう。
未証浄心菩薩
また未得浄心菩薩ともいう。初地以上七地までの菩薩を指す。この位は、すでに不退をえて、衆生教化の仏事をなすことができるが、その心にいまだ微細な煩悩の影が宿っていて、これらの仏事において作心がある故、未証浄心の菩薩という。
平等法身
諸法の不生不滅なる法性平等をさとった身。八地以上の菩薩をさす。
浄心菩薩
第八地の菩薩を指す。
上地菩薩
第九・十地の菩薩を指す。
寂滅平等
平等法身の菩薩の得た境地。寂滅は仏の涅槃の境地。平等は諸法の実相の理。
『解読浄土論註』224頁
5 回向門
どのように回向するのか。すべての苦悩する衆生をみすてず、心につねに(共に安楽国に生れたいとの)願いをなすのである。(自らいただいた実の如の功徳を、生きとし生けるものに)回らし向けることを首として、大悲の心を実現せんがためのゆえである。
回らし向けるには二種の相がある。一には往相、二には還相である。
往相回向とは、己れの功徳を、生きとし生けるものに回らし施し、願いをなして、共に彼の阿弥陀如来の(まします)安楽浄土に往生しようとすることである。
還相回向とは、彼の(国)土に生じおわって、奢摩他(止)・毘婆舎那(観)を得、
(衆生救済の)方便の力が完成して、生死のみ稠林(世界)にかえり入って、生きとし生けるものを教化し、共に仏道に向かわしめることである。
(浄土へ)往くも(穢土へ)還るも、みな衆生(の苦しみ)を抜いて、生死の海を渡らしめんがためである。
この故にこそ、「回らし向けることを首として、大悲の心を完成することを得るがため」といわれているのである。〔信p.233〕〔証p.285〕
『解読浄土論註』229頁
四 浄土の世界観(観行体相)
① 仏国土の荘厳
1 仏国土の不可思議なる力
(五念門第四の観察門)観察体相は、この分の中に二つの体(相)がある。
一には器の体(相)、
二には衆生の体(相)である。
器(を観察する)分の中がまた三重になっている。
一には、国土の体相(をあかし)、
二には、(その国土の荘厳が、如来の)自利利他(の功徳)をしめしあらわす(ことをあかし)、
三には、(その国土の荘厳が)第一義諦(法性)にかなう(ことをあかす)のである。
国土の体相とは(論につぎのようにいわれている)。
どのように彼の仏国土の荘厳の功徳を観察するのか。それは、彼の仏国土の荘厳が、不可思議なる力を完成(持続)しているからであって、(その力は)あたかも彼の摩尼如意宝の性(質)と相似し相対の法のようだからである。
不可思議なる力とは、総じて彼の仏国土の十七種の荘厳の功徳は、思議することができないということである。いろいろな経典には、一致して五種の不可思議があると説かれている。
一には、衆生の多少の不可思議。
二には、業の力の不可思議。
三には、龍(神)(自然現象)の力の不可思議。
四には、禅定の力の不可思議。
五には、仏法の力の不可思議、である。
この論の中(に説くところ)の仏土の不可思議には二種の力がある。
一には業の力、これは法藏菩薩のなみすぐれた善根と、大きな願い(をおこされた永劫の修行)の業力とによって成ったものである。
二には、阿弥陀法王の正覚の(世の汚れを離れておさめられた)善き力にたもたれて、摂められているからである。〔真p.315〕
これらの(願力と仏力の二つの)不可思議については、(以)下の十七種(の仏土の荘厳)にあるとおりであって、一つ一つの相がみな不可思議である。(それは)文に至って説明することにしよう。
『浄土論』に「あたかも彼の摩尼如意宝の性(質)と相似し相対するようである。」というのは、彼の摩尼如意宝の性(質)に借えて、安楽仏土の不可思議なる性を示すのである。
(そのわけは、こうである)仏がたは涅槃に入られるとき、方便の力によって、(仏)身を砕いて舎利となられ、それによって衆生に福をあたえたもうのであるが、(その)衆生の福がつきると、この舎利は変じて摩尼如意宝珠となるのである。この珠は、多くは大海の中に在って、大龍王が首飾りとしている。
もし転輪聖王が世に出られるときは、慈悲の方便によって、よくこの珠を得、
閻浮提(人間世界)に大きな饒益をもたらすのである。もし、衣服や飲食や灯明や(その他)楽しみの道具など、意の欲するところにしたがって、いろいろなものを必要とするときは、(転輪)王は、すぐさま潔斎して、珠を長い竿の頭に置き、願いを発して、こういう。「もし私が実転輪王であるなら、願わくは宝珠よ、これこれのものを雨ふらして、もしくは一理(四方)にあまねく(ふらし)、もしくは十里に、もしくは百里にと、我が心の願いにしたがえ」と。このとき、ただちに虚空よりいろいろなものが雨ふってきて、みな必要に応じて、天下のすべての人の願いを満足するのである。(これは)この宝の性の力によるのである。
彼の安楽仏土もまたこのようである。(それは)安楽の性の力がいろいろ完成しているからである。
「相似し相対する」とは、彼の宝珠の力は、衣食を求めれば、よく衣食などのものを雨ふらして、求める者の意にかなうのであるが、これは求めない(のに雨ふる)のではない。
彼の仏土は、そうではない。性が満足し完成されているから、欠乏したり不足したりすることはないのである。部分的に彼の(摩尼如意宝珠の)性をとって喩えているから「相似し相対する」といわれるのである。
また、彼の宝は、ただ衆生に衣食などの願いを与えることができるだけで、衆生にこのうえない(仏)道を(求め)願う心を与えることはできない。
また、彼の宝は、ただ衆生に(その人)一身(について)の願いを与えうるだけであって、衆生に無量の身(について)の願いを与えることはできない。
このような、かぎりない差別があるから「相似している」といわれるのである。
五不思議
①衆生多少不思議(衆生の数が無限でいつまでもつきない不思議)②業力不思議(業の力によって人間が千差万別の結果を得る不思議)③龍力不思議(龍神が風を呼び雨を降らせる不思議)④禅定力不思議(禅定の力によって神通変化をなす不思議)⑤仏法力不思議(衆生を転迷開悟せしめる不思議)
潔斎
心身を清めてものいみすること。飲食行為を慎み、身体を清めて不浄を避けること。
『解読浄土論註』236頁
2 仏国土荘厳の十七種を示す
彼の仏国土の荘厳の功徳が(仏の願いのごとく)できあがっていることを観察すれば、十七種ある。(この願力成就の次第を)よくよくわきまえておかねばならない。
その十七種とはどのよう(な次第)かといえば、
1 一点のにごりもない清浄さをかざりあげた功徳 (荘厳 清浄 功徳 成就)
2 無限の量をきわまりなくかざりあげた功徳(荘厳 量 功徳 成就)
3 仏の大慈悲の性をかざりあげた功徳(荘厳 性 功徳 成就)
4 形相のうつくしさをかざりあげた功徳(荘厳 形相 功徳 成就)
5 いろいろな事物をさまざまに微妙にかざりあげた功徳(荘厳 種種事 功徳 成就)
6 妙なる色をうつくしくかざりあげた功徳(荘厳 妙色 功徳 成就)
7 触官を柔軟にかざりあげた功徳(荘厳 触 功徳 成就)
8 うつくしく三種にかざりあげられている功徳(荘厳 三種 功徳 成就)
9 華を雨ふらす仏事がかざりあげられている功徳(荘厳 雨 功徳 成就)
10 光明をもってかざりあげられている功徳(荘厳 光明 功徳 成就)
11 妙なる法を説く声をかざりあげた功徳(荘厳 妙声 功徳 成就)
12 主たる力をかざりあげた功徳(荘厳 主 功徳 成就)
13 仏の眷属が仏の功徳をもってかざりあげられている(荘厳 眷属 功徳 成就)
14 受用 ― いのちのかて ― が仏の功徳をもってかざりあげられている(荘厳 受用 功徳 成就)
15 あらゆることにわたっての苦難がないことを仏の功徳をもってかざりあげている(荘厳 無諸難 功徳 成就)
16 大乗の義 ― 第一義諦 ― に通入する大道たることを仏の功徳をもってかざりあげている(荘厳 大義門 功徳 成就)
17 仏たるべきあらゆる願望が満足することが仏の功徳によってかざりあげられている(荘厳 一切所求満足 功徳 成就)である。
先ず章の題を挙げ、つづいてその内容を(以下に)釈する。
荘厳 清浄 功徳 成就
清浄なるを荘厳せる功徳の成就。荘厳は① alaṁkāra 十分につくる、かざる、仏身・仏土・仏具などをかざる、②努力する、③別におく、ととのえる、おきかえる、明示する、軍隊をととのえる、④装飾する、支配する、住する、菩薩が弘誓の鎧をつける(僧那僧涅と音写)など種々の梵名をもつ語。解読では「かざる」と訳し、その意味を充分ならしめるために「美しく」「おごそかに」などの副詞を冠した。功徳成就とは、功徳の力が充分にはたらいていること、功徳がその力を完全無欠にあらわしていること、仏の功徳の永遠不滅性が人間とのかかわりの中で証明されていることなどの意。解読では「かざりあげた(られた)功徳」の「あげた(られた)」の表現に、成就の意を含めて訳した。
十三者云云
曇鸞の解釈によれば、器世間荘厳十七種のうち、第九雨功徳まではいわゆる依報(環境としての安楽国土)に約し、第十光明功徳以下は正報(環境をかたちづくっている主体)を器世間の徳に約して解釈していると考えられる。さらに正報に約する中、第十三の眷属功徳は能住の人(阿弥陀仏)に対して所住の人(阿弥陀仏のもとにある大衆)をあらわし、第十四の受用功徳から第十七の一切求満足功徳までは能住持の相(光明と妙声によって浄土がたもたれている相)に対して所住持の徳のはたらきをあらわしている。つまり、第十三眷属功徳以下は、仏の功徳によっていかされている浄土の大衆及び浄土の徳のはたらきを荘厳している。解読では以上のことを考慮して、第十三眷属功徳以下を訳した。
『解読浄土論註』240頁
1 清浄性をかざる功徳(清浄功徳)
(一点のにごりもない)清浄さをかざりあげた功徳とは、偈に「彼の世界の相を観ずるに、三界の道に勝過せり」といわれているからである。
これはどうして不思議(な功徳)なのであろうか。
凡夫人の、煩悩にみちみちているものでも、彼の浄土に生れることができれば、三界につながれてはなれることができない業のきづなが、あますところなくきれて、(法の徳のゆえに)煩悩を断じないまま、涅槃の分を得るのである。どうして(並々の)思いのはからい及ぶことであろうか。〔証p.281〕〔真p.314〕
2 無量性をかざる功徳(量功徳)
(無限の)量をきわまりなくかざりあげた功徳とは、偈に「究竟して虚空の如く、広大にして辺際なし」といわれているからである。
これはどうして不思議(な功徳)なのであろうか。
彼の安楽国の人天は、もしこころに宮殿・楼閣の広さを、一由旬あるいは百由旬に、あるいは千由旬にしたいとおもい、(またその部屋数を)千間、万間にしたいとおもえば、心のままにそうなり、人それぞれにおもいどおりになるのである。
また、十方世界の衆生が往生を願うに、すでに生じたもの、今、生じるもの、これから生じるものの、一時一日の頃の数をかぞえても、それがどれくらいの数になるか知ることができないほどである。にもかかわらず、彼の世界はつねに虚空のごとくであって、せまっくるしさがまったくないのである。
彼の安楽国の中の衆生は、このような量の中に住んでいて、その志願の広大なことも虚空のようで、まったく限度がないのである。(つまり)彼の国土の量が、衆生の心のはたらきの量になっているのであるから、どうして(われわれが)思いはからうことができるであろうか。
宮殿・楼閣云云
『大経』巻上「宮殿・楼閣、その形色に称う。高下大小なり」とある意。
『解読浄土論註』245頁
3 大慈悲の性をかざる功徳(性功徳)
(仏の大慈悲の)性を(世間を超出した善根で)かざりあげた功徳とは、偈に「正道の大慈悲、出世の善根より生ず」といわれているからである
これはどうして不思議(な功徳)なのであろうか。
たとえば、迦羅求羅という虫は、その形がごく小さいけれども、大風が吹くと身が大山のようになる。風の大小にしたがって、自己の身をつくるのである。安楽国に生れる衆生もこのようであって、彼の正道の世界に生れれば、世を超えた善根をまどかにそなえ、正定のなかまに入るのである。これも風が(虫の)身ではないのに、身となるというようなものである。
どうして(常識でもって)思いはからうことができようか。
4 形相をかざる功徳(形相功徳)
形相すぐれてうつくしくかざりあげられた功徳とは、偈に「浄光明満足せること、鏡と日月輪との如し」といわれているからである。
これはどうして不思議(な功徳)なのであろうか。
そもそも(この世では)、忍辱ぶことによって(身の)端正さをえるのであるが、これは自分の心が(身に)影響を与えるからである。しかし、ひとたび彼の安楽国土に生れることができたなら、瞋とか忍とかの区別なく、人天の色像は平等で、とくにすぐれたものとなるのである。およそこれは、清浄な(国土の)光の力によるのである。彼の安楽国土の光は心のあらわれではないのに、事実心のはたらきをするのである。どうして(常なみの)思いの及びうることであろうか。
5 種々の事物をかざる功徳(種々事功徳)
いろいろの事物をさまざま微妙にかざりあげた功徳とは、偈に「もろもろの珍宝の性を備えて、妙荘厳を具足せり」といわれているからである。
これはどうして不思議(な功徳)なのであろうか。
彼の安楽国のいろいろの事物は、一つの宝でも十の宝でも、百千種類の宝でも、みな心のまま、意どおり充分にそなえることができるのである。(しかも)もしなくならせようとおもえば、たちまち消えてなくなるのである。(このように)心に自在をえることは、神通力の比ではない。どうして(われらの)思い及びうることであろうか。
『解読浄土論註』249頁
6 妙なる色をかざる功徳(妙色功徳)
妙なる色をうつくしくかざりあげている功徳とは、偈に「無垢の光炎熾にして、明浄にして世間を曜かす」といわれているからである。
これはどうして不思議(な功徳)なのであろうか。
その(垢なき)光は、事物をてらせば表裏をつらぬき、心をてらせば無明をことごとく滅するのである。(つまり)光が仏の(教化衆生の)いとなみをするのである。どうして(常の心の)思い及びうることであろうか。
7 柔軟さをかざる功徳(触功徳)
触官を柔軟にかざりあげた功徳とは、偈に「宝性功德の草、柔軟にして左右に旋れり、触るるもの勝楽を生ずること、迦旃隣陀に過たり」といわれているからである。
これはどうして不思議(な功徳)なのであろうか。
およそ宝といわれるたぐいは、堅く頑強なものであるのに、これ(浄土の宝)はやわらかである。(しかもやわらかであれば)触感の快楽に溺れやすいものであるのに、これ(浄土の触感)は仏道(に精進する心)を増させるのである。このことは愛作(菩薩のはなし)と同じである。どうして(常の心の)思い及びうることであろうか。
愛作と字される菩薩があった。すがたかたちが端正であったため、人をすっかり魅了させた。『経』(大宝積経)には、「彼の魅了されたものは、天上界に生れたり、菩提心を発したりする」といわれている。
『解読浄土論註』251頁
8 三種(水・地・虚空)をもってかざる功徳(三種功徳)
うつくしく三種にかざりあげられている功徳というのは、(まず)三種のものがらがあるということを、よく承知すべきである。どのようなのが三種かというと、一に水、二に地、三に虚空である。
この三種を並列していうわけは、同じ類だからである。というのは、(これら三種は)第一に六大 ―― 虚空・識・地・水・火・風 ―― の類であり、第二に(五の)無分別 ―― 地・水・火・風・虚空 ―― の類だからである。
(これらの中で)ただ三種のみをいうのは、識という一大は衆生をかたちづくっている要素であり、火という一大は彼の浄土にはないからである。(また)風は(浄土にも)あるとはいえ、見ることができず、一定の場処をしめるものではないからである。
したがって、六大・五類の中で、有形のものだけをとりあげてうつくしくかざるべく、三種を並べて言うのである。
六大
有情を構成する六種の大なる要素。大とは根本要素、法界に遍満するものの意。このなか、地・水・火・風の四大は物質を造りだす所依となり、これに空大(内外の間隙―空間)を加えて、五大を色法の範疇に摂し、識大は有漏の意識のことで、衆生の生存の所依として心法(精神)の範疇に摂す。従って、世界はこの六大によって構成されていると説くが仏教の通説となっている。
無分別類
論の偈「同地水火風虚空無分別」の文による。偈の下の註解の文にもあるように、これらの五類は色法に属し、本来分別のないものだから、無分別の類という。『解読浄土論註』135頁参照
『解読浄土論註』255頁
① 水をもってかざる功徳(水功徳)
水をうつくしくかざりあげた功徳というのは、偈に「宝華千万種にして、池・流・泉に弥覆せり。微風、華葉を動かすに、交錯して光乱転す。」といわれているからである。
これはどうして不思議(な功徳)なのであろうか。
彼の浄土の人天は、水を飲み穀物をたべるような身ではないのに、どうして水がいるのか。また完全に清浄であって、洗濯する必要はまったくないのにどうして水を用いるのか。また、彼の浄土には四季なく、いつもほどよく、熱いというような煩らわしさもないのに、どうして水を必要とするのか。
必要でないのに、あるというのは、わけがあってのことである。
(即ち)『経』(大経)に(次のように)いわれている。
「彼の浄土の菩薩や声聞たちは、たとえば宝池に入って足まで水にひたそうとおもえば水はすぐさま足をひたし、膝までとおもえば膝まで来、腰までとおもえば腰まで、頸までとおもえば頸まで来、身にそそぎたいとおもえば自然に身にそそぐ。(しかも)もとどおりにしたいとおもえば、水はたちまち、もとにもどる。
冷さ暖かさがほどよく調和し、自然に意のままとなり、神をはればれとさせ身を悦ばせて、心の垢をあらいながすのである。(水は)清らかに澄み、その浄いことはあたかも形がないようである。(水の底の)宝の砂がくっきりとみえ、どんなに深くても、てらしだされないところとてない。小波がゆっくりと流れ、たがいに、うちあい、そそぎあっては安詳に流れさっていく。それは遅くもなく疾くもない。
波があがると、かずしれぬ自然の妙なる声がして、
所応にしたがって(その声を)聞かないものとてない。
あるいは仏の声を聞き、あるいは法の声を聞き、あるいは僧の声を聞く。
また寂静(なる涅槃)の声や、空無我の(理を説く)声や、大慈悲の声や、波羅蜜の(行を説く)声を聞き、
あるいは十力、四無畏、十八不共法(など仏の行い)の声や、いろいろな神通の(もとである)智慧(を説くところ)の声や、なすべき行なく、起すべき善なしという(さとりの境地を説く)声や、(初地の菩薩の)無生法忍(の境地)から、(第十地の)甘露潅頂(の境地)に至るいろいろな妙なる法(を説くところ)の声を聞く。
これらの声はみな、聞こうとする者(の心)にかなって、かぎりない歓喜をあたえるのである。そして(真如法性の)清浄にして欲を離れ、寂滅にして真実なる義にしたがい、三宝の力、無所畏、不共の法にしたがい、神通の智慧をそなえた菩薩と声聞の行ずるところの道にしたがうのである。(そこにはもはや)三塗という苦難の名はなく、ただおのずからなる快楽の音あるのみである。だからその国を名づけて安楽というのである」と。
この(安楽国の)水は、仏の(教化の)いとなみをしているのであるから、どうして(つねなみの)思いの及びうることであろうか。
不共法
詳しくは不共仏法。仏のみにあって他と共通しない徳をいう。これに十八をかぞえるので一般に十八不共法という。
『解読浄土論註』260頁
② 地をもってかざる功徳(地功徳)
大地をうつくしくかざりあげた功徳とは、偈に「宮殿・もろもろの楼閣にして、十方を観ること無碍なり。雑樹に異の光色あり、宝蘭遍く囲繞せり」といわれているからである。
これはどうして不思議(な功徳)なのであろうか。
彼の浄土のいろいろなものは、一つの宝でも、十の宝でも、百の宝でも、数かぎりない宝でも、心におもうまま充分にかざることができる。このかざりは、すみきった鏡のように、十方の国土の浄らかさと穢なさのいろいろな相や、善と悪の業縁など、すべてをありのままにうつしだすのである。彼の国土の人天は、このような事実を見ているから、探湯(悪をやめる)不及(善にはげむ)の情を自然とまっとうするのである。
(このことは)たとえば、もろもろの大菩薩は、法性などを照らす宝をもって冠とし、この宝の冠の中にことごとく諸仏を見、またすべてのものの本性に通達する(といわれている)ようなものでもある。
また、仏が『法華経』を説かれたとき、眉間から光を放って、東方の一万八千の国土を照らしだされると、みな金色の如くかがやき、阿鼻地獄より有頂天に至るまでのあらゆる世界の中で、六道をさまよっている衆生の生死のありさま、また善と悪との業縁と、その結果うける境ぐうのよしわるしが、ことごとくうつしだされた。およそ浄土のかざりはこのようなものである。
かざりにうつった像が仏の(教化の)いとなみをするのである。どうして(われわれの)思いの及びうることであろう。
探湯不及之情
論語・李氏第十六に「孔子曰く、善を見ては及ばざるが如くし、不善を見ては湯を探ぐるが如くす」とあるによる。善を見れば、早く追求せねばおっつかないように熱心に追求し、不善を見れば、熱い湯の中に手をつっこんで、あわてて手を引くときのように、一瞬の猶予もなく遠ざかるという意味
善悪の業縁 『真宗新辞典』より
業の因縁。善悪の行為が苦楽の結果をまねく因縁となること。「善悪の業縁」〔論註〕、「業縁をもってのゆえにしばしば生死を受く」〔涅槃-信〕、「さるべき業縁のもよおせば」〔歎異〕、「過去の業縁のがれがたきによりて」〔口伝〕
『解読浄土論註』264頁
③ 虚空をもってかざる功徳(虚空功徳)
虚空を美しくかざりあげた功徳というのは、偈に「無量の宝交絡して、羅網虚空に遍ぜん。種種の鈴、響を発して、妙法の音を宣べ吐かん」といわれているからである。
これはどうして不思議(な功徳)なのであろうか。
『経』(p.42大経)に次のようにいわれている。
「数しれぬ宝の網が仏の国土をおおいつくし、すべて金の縷や真珠や、くらぶべきものとてない珍らしい百千種のいろいろな宝でかざられ、その四方には、くまなく宝の鈴が垂れている。光がきらきらと、てりはえて、その厳麗さは実に、えもいわれぬものである。
おのずからなる仏の徳をそなえた風が、どこからともなく静かにおこって、そよそよと吹いている。その風はほどよく調和されて、寒くもなく暑くもなく、暖かさと涼しさとが、やわらかくつつまれていて、遅くもなく疾くもなしに吹いている。いろいろの羅網や宝の樹のあいだを吹きぬけると、無量の微妙な法の音がかなでられ、くさぐさのゆかしい徳の香をまきちらす。その法を聞く者は、煩悩の垢習さえ生ぜず、(風が)身に触れれば、みな快楽をうるのである」と。
(仏の徳をそなえた風の)声が仏の、いとなみをするのである。どうして(つねなみの)思いのはからい、およぶことであろうか。
『解読浄土論註』266頁
9 花衣を雨らす仏事をかざる功徳(雨功徳)
(花を)雨をふらすことをかざりあげた功徳とは、偈に「花衣の荘厳を雨り、無量の香普く薫ぜん」といわれているからである。
これはどうして不思議(な功徳)なのであろうか。
『経』(p.42大経)に、つぎのようにいわれている。
「風が吹くと花が散って、仏土全体をおおいつくす。花は色の順にしたがい、ばらばらにならず、やわらかくつややかで、えもいわれぬ香を一面にはなっている。足でそのうえをふむと四寸ばかりくぼみ、足をあげると、もとのとおりになる。花は用がすめば、地がさけてその中に次々と没しさり、きれいさっぱりとなって、あとかたもない。時がくるとまた風が吹き花が散る。このように日に六たびくりかえすのである。
また、さまざまの宝からなる蓮花が世界中に咲きあふれ、それぞれの宝花には百千億の葉があって、その葉からでる光明が、数かぎりない種類の色をなしている。青い色には青い光、白い色には白い光があり、玄・黄・朱・紫の色も同じくそれぞれの光をはなっている。その光のこうこうとして輝くことは、日や月よりも明朗である。一つ一つの花の中から、三十六百千億の光があふれ、一つ一つの光の中から、三十六百千億の仏があらわれている。その仏の身は紫色の色をなし、すがたかたちは世をこえてとおとい。それぞれの仏は、また百千の光明をはなって、普く十方衆生のために微妙なる法を説かれるのである。このようにして仏たちは
各々、数しれぬ衆生を仏の正しい道に安んぜしめられるのである」と。
花が仏の(教化衆生の)いとなみをするのである。どうして(並々の)思いのはからい及ぶことであろうか。
『解読浄土論註』271頁
10 光明をかざる功徳(光明功徳)
光明をもってかざりあげられている功徳とは、偈に「仏恵明浄なること日のごとくにて、世の痴闇冥を除く」といわれているからである。
これはどうして不思議(な功徳)なのであろうか。
彼の浄土の光明は、如来の智慧より、むくいあらわれたものである。だからこれに触れれば、無明の黒闇はことごとく必ず消えるのである。光明は智慧ではないのに、よく智慧のはたらきをするのである。どうして(並々の)思いのはからい及ぶことであろうか。
11 妙なる法を説く声をかざる功徳(妙声功徳)
妙なる声をかざりあげた功徳とは、偈に「梵声の悟深遠にして、微妙なり、十方に聞こゆ」といわれているからである。
これはどうして不思議(な功徳)なのであろうか。
『経』(大経)に、「もし人あって彼の国土の清浄で安楽なことを聞くだけで、よく心にきざみ念じて、彼の国土に生れたいと願うものと、またすでに往生をえたものとは、かならず正定の聚に入ることができる」といわれている。
これは国土の名字が仏の(衆生教化の)いとなみをするということである。どうして(並々の)思いの及びうることであろうか。〔証p.281〕
12 主なる力をかざる功徳(主功徳)
主たる力をかざりあげた功徳とは、偈に「正覚の阿弥陀法王、善く住持したまえり」といわれているからである。
これはどうして不思議(な功徳)なのであろうか。
正覚そのものである阿弥陀仏は不思議であらせられる。彼の安楽浄土は、その正覚たる阿弥陀仏の善根の力によって住持されているのである。どうして(並々の)思いのはからい及ぶことであろうか。
「住」とは異ならず滅しないことをいい、「持」とは分散せず消失しないことをいう。
たとえば、不朽(という名の)薬を種子に塗ると、水にいれても流されず、火に入れても焼けずに、因縁をえて(芽を)出すのである。これは不朽薬の力によるからである。
(これと同じく)もし人が、一たび安楽浄土に生れれば、後になって(再び)三界に生じて衆生を教化しようと願い、浄土の生活を捨ててその願いのとおり(三界に)生じて、三界のいろいろなまよいの生活――煩悩が火のようにもえさかるただ中にもどっても、無上菩提の種子は、けっして朽ちることがないのである。これは、正覚たる阿弥陀仏の善なる住持の力をうけているからである。〔証p.282〕
『解読浄土論註』275頁
13 仏の仲間(眷属)をかざる功徳(眷属功徳)
(仏の)眷属が(仏の)功徳をもってかざりあげられているとは、偈に「如来浄華の衆は、正覚の花より化生す」といわれているからである。
これはどうして不思議(な功徳)なのであろうか。
およそこの雑生の世界には、胎生や卵生や湿生や化生などいろいろな生があって、それぞれ眷属の数もしれず、苦しみや楽しみにも、いろいろな差別がある。これは、いろいろな業をもっているからである。
彼の安楽国土は、阿弥陀如来の開いた正覚の浄花に感化されて生じないものは一人としてない。すべて同じく念仏して、それよりほかの道(より生れるもの)はないからである。〔行p.190〕
(浄土を願生するものは)はるか世界のはてまで、すべてを兄弟とするのである。このように眷属の数ははかりしれないのである。どうして(並々の)思いのはからい及ぶことであろうか。〔証p.282〕
14 法味の受用をかざる功徳(受用功徳)
受用 ― いのちのかて ― が(仏の)功徳をもってかざりあげられているとは、偈に「仏法の味を愛楽し、禅三昧を食とす」といわれているからである。
これはどうして不思議(な功徳)なのであろうか。
(浄土の人々は)物をたべずに命をたもっているが、およそこれにはたもてるわけがあるのである。それは、如来が本願をまどかに成就しておられるということにほかならない。その本願に乗ずることを我が命としているのであ。どうして(並々の)思いの及びうることであろうか。
15 苦難を超える道をかざる功徳(無諸難功徳)
あらゆることにわたっての苦難のないことを(仏の)功徳をもってかざりあげているとは、偈に「永く身心の悩みを離れて、楽を受くること常に間なし」といわれているからである。
これはどうして不思議(な功徳)なのであろうか。
『法句譬喩経』に「身は苦しみの器であり、心は悩みの端である」といわれている。しかし、彼の安楽国では、身も心もありながら、楽しみをうけることばかりがつづくのである。どうして(並々の)思いの及びうることであろうか。
化生
四生の中の化生ではなく、弥陀の浄土に生れること。『大経』に浄土に生れるに胎生と化生とのあることが説かれている。胎生とは、いわゆる自力の往生で、疑惑の心をもって諸々の功徳を修め、罪福を信じ、善本を修習して願生するもの。このものは、仏智を疑惑するが故に、浄土に生れるも宮殿の中で寿五百才をふるまで仏法僧の三宝を見ることができない。化生とは発心して無量寿仏を見、まさに念仏して浄土に生れること。第十八願の往生。
『解読浄土論註』279頁
16 平等の道をかざる功徳(大義門功徳)
大乗の義 ― 第一義諦 ― に通入する大道たることを(仏の)功徳をもってかざりあげているとは、偈に「大乗善根の界、等しくして譏嫌の名なし、女人および根欠、二乗の種、生ぜず」といわれているからである。
(本願に)むくいあらわれた浄土は、二種の譏の過というものを離れている。(このことは)よくわきまえておかねばならない。
(二種とは)一には体(についての譏)、二には名(についての譏)である。
体(についての譏)に三種ある。一つには二乗の人、二つには女人、三つには(眼や耳など)いろいろの根器の欠けた人である。この三種の過がないから、これを〝体についての譏嫌を離れる〟と名づける。
また名(についての譏)にも三種ある。ただ三種の体がないばかりでなく、二乗とか女人とかいろいろな根器が欠けている(人)とかという名前すら耳にすることがないのである。だからこれを〝名についての譏嫌を離れる〟と名づけるのである。
(偈に)「等し」というのは、(浄土の人々はさとりにおいて)平等で同一の相だからである。
これはどうして不思議(な功徳)なのであろうか。
そもそも、(『維摩経』仏国品によれば、)(六欲天など)いろいろな天では、おなじ器で(食事をするが)その飯は(食べる人の)福徳(の程度)にしたがって色がかわる。また(仏が)足の指でおさえ(そこに三千大千世界をあらわされたとき、心の浄いものはその世界を)黄金(と見、心の不浄なものは)瓦礫(と見たので、それによって心)の大切なことを詳らかにされた。
ところが(浄土へ)往生を願うものは、
もとは(上品上生、中品中生など)九つの種に区別されているが、(往生を願う)今は全く差別がない。たとえば淄水と渑水も(海に入れば)一つ味であるようなものである。どうして(つね並の)思いの及びうることであろうか。〔証p.282〕
淄渑一味
淄と渑は斉の国にあった二つの川の名。列子の口義では、易牙という者がこの二つの川の水をそれぞれなめて区別をしたとある。それほどに異なった味をもつ淄水と渑水でも、海に入れば一味となるということ。
『解読浄土論註』282頁
17 願いを満たすことをかざる功徳(一切所求満足功徳)
(仏たるべき)あらゆる願望が満足することを(仏の)功徳によってかざりあげられているとは、偈に「衆生の願楽するところ、一切よく満足す」といわれているからである。
これはどうして不思議(な功徳)なのであろうか。
彼の国の人天は、もし他方の世界の無量なる仏の国に往って、仏と菩薩たちを供養しようと願い、またそのために必要な供養の具を手に入れようと願えば、願いはすべてかなえられる。また彼の浄土の寿命を捨て、余の国におもむき、そこに生きる寿命の長さを自由にしようとおもえば、願いのままにできる。まだ(そのようなことのできる八地已上の菩薩の)自在の位をえていないにもかかわらず、自在の用きと同じになっているのである。どうして(われらの)思いの及ぶことであろうか。
『解読浄土論註』285頁
3 自利利他の示現
(国土の荘厳が如来の)自利利他(の徳)をあらわしているとは、(つぎのようにいわれている)。
(大)略して、彼の阿弥陀仏の国土の、十七種にかざりあげられた功徳を説いて、如来自身の利益である大いなる功徳の力が成就していることと、他の衆生を利益したもう(大)功徳(の力)が成就していることをあらわしているからである、と。
「略して」といわれているのは、彼の浄土の功徳は無量であって、ただ十七種のみにかぎらないということをあきらかにするのである。(その無量の功徳を十七種におさめるのは)須弥山を芥子(の実)の中にとりこんだり、毛ほどの孔に大海をおさめたりするようなものであるが、それは須弥山や大海の神であろうか、または毛孔や芥子の力であろうか。いや、ひとえにそのような不思議をなすひとの不思議な作用なのである。だから、十七種(の功徳)はひとえに他にめぐまれるものであるとはいえ、そこにはもとより自利が満足しているという意義のあることはあきらかである。このことをよく承知すべきである。〔真p.316〕
『解読浄土論註』289頁
4 真理(第一義諦)を明かす
(仏国土十七種の荘厳が)第一義諦(真如)におさまるとは、(つぎのように、いわれているからである)
彼の無量寿仏の国土の荘厳は、第一義諦たる妙なる境界の相(であり、その相をあらわさんがため)十六の句及び一つの句を順次に説きのべるのである。よく(この仏力成就の次第を)了解すべきである、と。
第一義諦とは、仏の(しろしめす)因縁の法である。ここにいう諦とは境界の意味である。だから荘厳(量功徳)などの十六句を称して妙なる境界の相というのである。この義は入法句(を説く)文のところでさらに解釈することにする。
「……及び一つの句を順次に」とは、つまり器(世間の清)浄(功徳)等を観察することであって、総(相たる清浄功徳)と別(相たる十六句)の十七句は観察をなしていく順番である。
どのように順次起ってくるかといえば、
まず建の章で「無碍光如来に帰命して、安楽国に生ぜんと願ず」と言われるのであるが、ここに疑問がおこる。つまり疑っていえば、(そもそも)生ということは、まよいの生ずる本源であり、あらゆるわずらいの根元となるものである。(ところが)その生を棄てて、(また)生を願うというのでは、生はいつまでもはてることがないではないか、と。
このような疑問をとくためにこそ、彼の浄土のかざりあげられた功徳(の相)を観察するのである。(観察すれば)彼の浄土は阿弥陀如来の清浄な本願によるところの無生の生であって、三有虚妄の生のごときではないことが明らかとなる。
なぜかといえば、およそ法性は清浄そのものであって、とこしえに生(滅)なきものである。(したがって)生(を願う)というのは、ひとえに(浄土に)生を得んとする者の情をあらわすものにほかならない。(このように)生がまこと無生である以上、どうして生がつきはてるということがあろうか。
(もし)そのような生を断じつくすならば、上は為すことなくして為す(ところの衆生済度)の身を失い、下は三空(門に沈んで)かえって空にあらずという重病におちいり、(菩提の)根をくさらせ永久に絶やし、はては三千(大千世界)をふるわして泣き叫んでも及ばぬことになる。ここにいたっては、仏法に、たちかえりたちかえり(蘇生して、無上菩提を求めようと)する心がまったくなくなって恥をかくだけである。
そもそも(願生の)体は(法性の)理より生ずるものである、これを浄土というのである。その浄土の宅(をあらわすの)が、いわゆる十七句である。
三空・不空の痼
三空とは解脱に至る行法としての三空門(三解脱門又は三三昧ともいう)即ち①空門(一切諸法の体空なりと知る)②無相門(体が空であるから相も無いと知る)③無願門(無相であるから願うべきものもないと知る)
『解読浄土論註』295頁
5 荘厳の総相と別相
十七の句の中を総と別との二つにわける。
【清浄】 はじめの句は総(ぜんたい)の相をあらわしている。つまり「清浄なる仏土は、三界の道をこえすぐれている」といわれているのがこれである。彼の土が三界をこえすぐれているというには、どのような相があるのか。以下の十六種のかざりあげられた功徳の相がこれである。
【量】 その第一は量である。(浄土は)どこまでも虚空のように広大ではてしがない。(はてしない)量を知ったうえは、この量は何を本としているか(を知らねばならない)。
【性】 だから性を観ずるのである。性とは本という意味である。彼の浄土は正道の大慈悲たる世をこえた善根より生じた。(本が)世をこえた善根であるといわれたうえは、この善根はどのような相を生みだすか(を知らねばならない)。
【形相】 だから次にかざられた形相を観ずるのである。形相を知ったうえは、形相はどのような具体(的な事物)となっているかを知るべきである。
【種種事】 だから次にいろいろな事物を観ずるのである。いろいろな事物を知ったうえは、いろいろな事物の妙なる色を知るべきである。
【妙色】 だから次に妙なる色を観ずるのである。妙なる色を知ったうえは、この色はどのような触感を有するか(を知るべきである。
【触】 だから次に「触れる」ということを観ずるのである。身に触れる(勝楽)を知ったうえは、眼に触れる(もののすがた)を知らねばならない。
【三種(水・地・虚空)】 だから次に水と地と虚空とをかざった三種のものがらを観ずるのである。眼に触れる(すがた)を知ったうえは、鼻(感)にふれるものを知らねばならない。
【雨】 だから次には花衣の香のふくいくとにおっていることを観ずるのである。眼や鼻などにふれることを知ったうえは、それにとらわれることのないことを知る必要がある。
【光明】 だから次に仏の智慧が明らかに照らしていることを観ずるのである。
智慧の光の清浄ならしめる力を知ったうえは、(浄土)声名の遠近を知らねばならない。
【妙声】 だから次に浄らかなる声の遠くまで聞こえることを観ずるのである。声名を知ったうえは、(浄土は)誰によってたもたれているかを知らねばならない。
【主】 だから次に(浄土の)主を観ずるのである。主のましますことを知ったうえは、主の眷属はどのようなひとびとか(を知らねばならない)。
【眷属】 だから次に眷属を観ずるのである。眷属を知ったうえは、この眷属はどのように受用(いのちのかて)をえているかを知らねばならない。
【受用】 だから次に受用(いのちのかてをうるひと)を観ずるのである。受用を知ったうえは、この受用に苦難ありやなしやを知らねばならない。
【無諸難】だから次に苦難のまったくないことを観ずるのである。苦難のないことを知ったうえは、どのような義でいろいろな苦難がないか(を知らねばならない)。
【大義門】 だから次に大乗の義門(大乗の門、すべての人の救われていく道)を観ずるのである。大乗の義門を知ったうえは、大乗の義門において満足するかいなかを知らねばならない。
【一切所求満足】 だから次に求めるものが(すべて)満たされていることを観ずるのである。
『解読浄土論註』299頁
氷上燃火の喩
また次に、この十七句は、ただ疑問をとくだけでなく、この十七種の荘厳がまっとうしていることを観ずるなら、よく真実の浄らかな信(心)を生じて、かならず彼の安楽仏土に生ずることができるのである。
問い。上に(浄土の)生は無生であると知ると言われたが、これは上品の生の者についてであろう。もし下下品の人が、十念することに乗って往生するなら、これは実の生だと固執するのではないか。ただ実の生だと固執するなら、二つの執着に陥るだろう。(すなわち下品の人は)第一には往生することができないのではないかということ、二には(往生したとしても)更に生(死)の惑を生ずるのではないかということである。
答え。たとえば、浄摩尼珠を濁った水にいれると、たちまち水が清らかになるというようなもので、たとえ人ははかりしれぬ生死の罪の濁りのなかにあっても、彼の阿弥陀如来のこのうえもない無生清浄の宝珠たる名号を聞いて、これを濁った心に投ずるなら、一念一念のうちに罪が滅し心が浄くなって、ついには往生することができるのである。
また、浄摩尼珠を玄と黄の弊につつんで水に投げいれると、たちまち水は玄黄色となり、(玄黄と水とが)まったく一色のものになるというようなもので、彼の清浄なる仏土には阿弥陀如来(すなわち)無上の宝珠がましまし、それをかぎなくかざりあげた功徳の帛につつんで、往生する者の心水に投げいれるなら、実の生ありとする執見は、転じて無生の智慧となるのである。
また、氷の上で火を燃すに、火のいきおいがつよければ氷が解け、氷が解ければ火がきえるというようなもので、彼の下品の人は、法性は無生であることを知らずとも、ひとえに仏の名を称える力によって往生の意をなし、彼の浄土に生れたいと願えば、彼の浄土は無生の世界であるがゆえに、実の生ありとする執見の火が自然に消滅するのである。
玄黄
玄は赤味を帯びた黒色。また天の色を玄、地の色を黄として、玄黄で天地の色をあらわす。中国では、この玄色と黄色の糸で織った帛を尊重し、進物などに用いた。
『解読浄土論註』302頁
② 仏荘厳の成就
1 仏荘厳の八種を示す
衆生の体(を観察する)については、この分の中は二重になっている。一には仏を観じ、二には菩薩を観ずるのである。
仏を観ずるとは(つぎのようにいわれている)
どのように仏をかざりあげた功徳を観ずるのか。仏をかざりあげた功徳を観察するに八種をかぞえる。(この次第を)よく知らねばならない。
この(仏を)観(察)するという意味は、すでに前の偈(を解釈したところ)であきらかにした。
八種とはどのよう(な次第)かといえば、
1 りっぱにかざりあげられた仏の座の功徳(荘厳座功徳成就)
2 おごそかにかざりあげられた身の業の功徳(荘厳身業功徳成就)
3 きよらかにかざりあげられた口の業の功徳(荘厳口業功徳成就)
4 あきらかにかざりあげられた心の業の功徳(荘厳心業功徳成就)
5 平等にかざりあげられている仏の大衆の功徳(荘厳衆功徳成就)
6 無上にして等しきものなくかざりあげられている上首としての功徳(荘厳上首功徳成就)
7 だれひとりあおがぬものなくかざりあげられている主たる功徳(荘厳主功徳成就)
8 だれひとり虚しくすぎゆくものがないようにかざりあげられている仏の住持の力の功徳(荘厳不虚作住持功徳成就)である。
『解読浄土論註』307頁
1 仏の座をかざる功徳(座功徳)
りっぱにかざりあげられた仏の座の功徳とはどのようなものか。偈に「無量の大宝王なる微妙の浄花台にいます」といわれているのがこれである。
もし(仏の)座を観察しようとするなら、『観無量寿経』(所説の第七華座観)によるがよかろう。
2 仏の身の業をかざる功徳(身業功徳)
おごそかにかざりあげられた(仏の)身の業の功徳とはどのようなものか。偈に「相好の光一尋なり、色像、群生に超えたまえり」といわれているのがこれである。
もし仏の身を観察しようとするなら、『観無量寿経』(所説の第八像観・第九真身観)によるがよかろう。
3 仏の口の業をかざる功徳(口業功徳)
きよらかにかざりあげられた(仏の)口の業の功徳とはどのようなものか。偈に「如来の微妙の声、梵の響十方に聞こゆ」といわれているのがこれである。
4 仏の心の業をかざる功徳(心業功徳)
あきらかにかざりあげられた(仏の)心の業の功徳とはどのようなものか。偈に「地・水・火・風・虚空に同じて、分別なからん」といわれているのがこれである。分別がないとは、分別する心がないということである。
凡夫たる衆生は、身と口と意との三つの業によって罪を造り、三界をめぐりめぐってはてることがない。だから諸仏・菩薩は身と口と意との三つの業をきよらかにととのえ、それによって衆生の虚誑の三業を治したもうのである。
どのようにして衆生を治したもうかといえば、(衆生は)身についての執見によって、三塗におちる身、卑賎なる身、醜陋身、八難に堕する身、流転きわまりない身をうけるのである。
このような衆生は、阿弥陀如来の相好なるひかりかがやく身を見たてまつれば、上のようないろいろの身業の繋縛からすべてときはなたれ、如来の家に入って、いつまでも平等なる身業を得ることができるのである。
(また)衆生は憍慢によって正法をそしり、賢者・聖者をばとうし、尊い人・年長の人をいやしめるのである。このような人は、舌を抜かれる苦しみ、人に教えても信じられず実行されない苦しみ、名が通らない苦しみをうけるのである。このようないろいろの苦しみをうけた衆生も、阿弥陀如来の至徳の名号たる説法の音声を聞くなら、上のようないろいろの口業の繋縛からすべてときはなたれ、如来の家に入って、いつまでも平等なる口業を得ることができるのである。
(また)衆生はよこしまな見解によって、心に差別のおもいを生じ、有るとか無いとか、ちがうとか正しいとか、好とか醜とか、善いとか悪いとか、彼だとか此だとかというように、いろいろに分別するのである。分別するから、長く三有(の世界)にしずんで、いろいろ分別する苦しみ、取るか捨てるかといった苦しみをうけ、(無明の)大夜にぐっすりと寝こんで、生死を出る期がないのである。このような衆生も、阿弥陀如来の平等なる光照に遇うか、もしくは阿弥陀如来の平等なる意業を聞くかすれば、上のようないろいろの意業の繋縛からすべてときはなたれ、如来の家に入って、いつまでも平等なる意業を得ることができるのである。
如来家
『十住毘婆沙論』巻一に「諸仏の家を名づけて如来の家と為す。今是の菩薩は、如来の道を行ずること相続不断なるが故に、名づけて生如来家と為す」とある。浄土に生れれば諸仏を思いのまま見ることができる故、浄土を諸仏の家といい、また如来の家と名づける。
『解読浄土論註』312頁
問い。心はもともと(ものを)覚知する相である。どうして地や水や火や風と同じように分別することがないということがあろうか。
答え。心は知る相ではあるが、(諸法の)実相に入(ってそのものとな)れば知ったということもないのである。たとえば、蛇の性向は曲がったものであるが、竹の筒に入ればまっすぐとなるというようなものである。また、人の身体に針がささったり蜂がさしたりすれば(痛いという)覚知があるが、石蛭がくらいついたり、鋭い刀できられたりすればまったく覚知がないというようなものである。このように知覚のあるなしは、その対象の条件によるのである。対象の条件によるということであれば、心そのものは知でもなく無知でもないのである。
問い。心が実相(をさとった境地)に入れば無知とならしめられるというなら、すべてにわたって知ろしめす(仏の)智慧はどうして得ることができようか。
答え。凡夫の心は、知るところあればかならず知らないところがある。聖者の心は知ったということがないから知らないということがない。無知であってしかも知であり、知のままが無知なのである。
問い。すでに無知であるが故に知らないところがないと言った。もし知らないところがないのなら、種種の法を知っているのではないか。
種種の法を知っているのであれば、またどうして分別することがないと言うのか。
答え。諸法の種種の相は、すべて幻化のようなものである。しかし、幻化にあらわれた象や馬にも長い頸や鼻や手や足はそれぞれそなわっていないわけではない。だが、知者はこれをみて、実際に象や馬が存在していると分別することはあるはずがないのである。
『解読浄土論註』316頁
5 仏の仲間をかざる功徳(衆功徳)
平等にかざりあげられている(仏の)大衆の功徳とはどのようなものか。偈に「天人不動の衆、清浄の智海より生ず」といわれているのがこれである。
6 仏を上首としてかざる功徳(上首功徳)
ひとしきものなくかざりあげられている上首としての功徳とはどのようなものか。偈に「須弥山王のごとく、勝妙にして過ぎたる者なし」といわれているのがこれである。
7 仏を恭敬することをかざる功徳(主功徳)
だれひとりあおがぬものなくかざりあげられている主たる功徳とはどのようなものか。偈に「天人丈夫の衆、恭敬して繞りて瞻仰したてまつる」といわれているのがこれである。
8 仏の住持の力をかざる功徳(不虚作住持功徳)
だれひとり虚しくすぎゆくものがないようにかざりあげられている(仏の)住持(の力)の功徳とはどのようなものか。偈に「仏の本願力を観ずるに、遇うて空しく過ぐる者なし、能く速やかに功徳の大法界を満足せしむ」といわれているのがこれである。
むなしくすぎゆくもののない住持(の力)が成就しているのは、およそ阿弥陀如来の本願力によるものである。〔真p.316〕
いまはまず、むなしい所作の相をあげて住持することができないことを示し、それによって彼の(浄土の)むなしい所作なき住持の義をあきらかにしよう。〔行p.198〕
人は自分の食をさいて子弟を養うまでにしても、ともすれば舟中で(その子弟に殺されるという)むほんをおこされたり、山のような金が庫いっぱいあっても餓死することを免れえなかったりする。このような眼前の事実はすべてこれ(むなしい所作の住持できない相)である。
(自分に)得たことが(いつまでも)得たことを住持することにならず、(いま)在ることが(いつまでも)在ることを守ることにならないというのは、みな虚妄の業で所作して住持することができないということによるのである。
いまいわれているむなしき所作なき住持(の力)とは、本たる法蔵菩薩の四十八願と今日の阿弥陀如来の自在なる神力とによるものである。
願いが力をつくりあげ、力が願いをまっとうさせるのである。願いは徒然なものではない。力は虚設のものではない。力と願いとが相いかなって、いつまでもくいちがうことがないから「成就している」というのである。〔行p.198-199〕〔真p.316〕
『解読浄土論註』320頁
2 如来の本願力の目覚め
たちどころに彼の(浄土の)仏を見たてまつれば、まだ浄心を証せぬ菩薩も畢竟平等なる法身をうることができ、浄心の菩薩と上地の菩薩とに同じく、畢竟に寂滅平等(の法)を得せしめられるのである。
平等法身とは八地以上の法性(を具現した)生身の菩薩のことである。寂滅平等とはこの法身の菩薩の証した寂滅平等なる法である。
この寂滅平等なる法を得ているから平等法身と名づけるのであり、平等法身の菩薩が得たところのものであるから寂滅平等なる法と名づけるのである。
この菩薩は、報生三昧を得て、この三昧の威大な力によって、よく一処にありながら一念一時のあいだに十方世界に遍じ、すべての諸仏及び諸仏のみもとに海のごとく集まった(菩薩の)大衆をいろいろに供養し、(また)よく無量なる世界の仏法僧の無い処にいたって種種に(三宝を)あらわし、あらゆる衆生を種種に教化し度脱するのである。(しかもこのように)常に仏のいとなみをなしながら、はじめから往ったり来たりするという想い、供養をしようとする想い、度脱しようとする想いがないのである。だからこのような身を平等法身と名づけ、このような法を寂滅平等の法と名づけるのである。
まだ浄心を証せぬ菩薩とは、初地以上七地までの諸の菩薩である。この菩薩もまたよく身をあらわして、あるいは百の、あるいは千の、あるいは万の、あるいは億の、あるいは百千万億の仏ましまさぬ国土にいたって仏のいとなみをなすのであるが、(その場合)かならずそうしようという(分別の)心をおこして三昧に入るのである。つまり、なそうとする(分別の)心をおこさないでもよいのではない。なそうとする(分別の)心をおこすから、いまだ浄心を得ずというのである。
この菩薩は、安楽浄土に生れたいと願えば、たちどころに阿弥陀仏を見たてまつる。(そして)阿弥陀仏を見たてまつる時、上地の菩薩と畢竟に身が等しくなり、(したがって所証の)法も等しくなるのである。龍樹菩薩とかバスバンズ菩薩といった輩が、彼(の浄土)に生れたいと願われたのは、まさしくひとえにこれがためである。〔証p.285-286〕
法性生身
『智度論』巻七十四に「菩薩に二種有り、一には生死肉身、二には法性生身なり。無生忍を得、諸の煩悩を断じ、是の身を捨てて後、法性生身を得」とあり、同巻六十に「般若の正義を説くに二種あり。一には生死肉身の菩薩、二には三界を出でたる不生不死の法性生身の菩薩なり」とある。無生法忍を得た第八地已上の菩薩は、すでに分段生死の身を離れ、法性の理に通達しているが、衆生教化の利他行の実践のために、(変易)生死の身をあえて保つ。故に法性生身という。それ故『智度論』巻二十七には「菩薩は無生法忍を得て、煩悩已に尽くるも、習気を未だ除かざるが故に、習気に因って及び法性生身を受け、能く自在に化生す」とある。
寂滅平等之法
一切諸法の平等無二なる寂滅の相を照らす法性の真理。寂滅はさとりからみられた諸法の相。『智度論』巻七十四には「寂滅とは、増さず、減らず、高からず、下からず、諸の煩悩・戯論を滅し、動せず、壊せず、障碍する所無し。菩薩は般若波羅蜜の方便力を以ての故に、亦た能く布施等をして如寂滅の相ならしむ」とある。
報生三昧
『大品般若経』巻六(智度論巻五十)に、菩薩の第八地について説く中、この第八地の菩薩は五法を具足すとあって、その第三に、この菩薩は如幻三昧に住して「能く一切を成弁し、亦た心相をも生ぜざるなり」と説き、第四に「報生三昧を得」ると説いている。竜樹は『智度論』巻五十において、この如幻三昧と報生三昧とについて、およそ次のように述べている。まず如幻三昧とは、幻人(幻術者)が我身を一定の場所におきながら、世界のあらゆる事象を現前させるというようなもので、この三昧に入る菩薩ぱ「能く十方世界に於いて変化し、其の中に遍満し、先ず布施等を行じて衆生に充満し、次に法を説き教化して三悪道を破壊し、然る後に衆生を三乗に安立し、一切の利益すべき所の事を成就せざる事無し」と釈している。然るに如幻三昧には、いまだ衆生を教化しようという意識、即ち作意分別の心がある。そこで次に菩薩は「常に三昧に入る」即ち「身を転じて報生三昧を得る」のである。ここに於いて菩薩は、はじめて任運無功用に衆生済度の事業をなしうることになる。即ち、人が目で色を見、耳で音を聞くのに何ら心を造作する必要がないように、「是の三昧の中に住すれば、衆生を度すること安穏にして如幻三昧に勝り、自然に事(衆生教化)を成じて役用する所が無」いのである、と釈している。以上の釈よりみれば、幻如三昧より報生三昧への「転身」のかたちが、「生死肉身より法性法身へ」ということであって、報生三昧は法性生身の果報として、生れながらに得られてある任運無功用なる三昧という意味と解ぜられる。曇鸞はこの報生三昧の菩薩の徳を語るに、以下浄土の菩薩の四種の荘厳功徳を以てし、仏の不虚作住持の功徳力を明かす文としている。
作心
前註引用の『智度論』巻五十にある「造作分別心」のこと。如幻三昧を作心有功用の三昧、報生三昧を無作心無功用の三昧という。
未得浄心
未証浄心に同じ。浄心・不浄身が単に浄らかな心・浄らかでない心というような意味にとどまらないことが以上の曇鸞の釈で明らかとなる。浄・不浄は煩悩についていうのであるが、仏教では煩悩が現行(現実にはたらく)しているかいないかで浄・不浄を決するのではなく、いかに煩悩が現行せずとも、菩薩のはたらき自体が有功用、つまり作心をもとにしている場合は不浄即ち未証(得)浄であり、たとえ煩悩の習気があろうとも無功用無作心である場合は浄である。行が煩悩を離れた行か否かは、行ずる心が、作心か無作心かで決定するからである。一般にはその作心と無作心との境界線を第七地と第八地との間に引くことによって菩薩の階位をたてるのであるから、逆にそのような境界線が解消されるような地平が見出されたときは、菩薩の漸次進趣の階位は方便にすぎなくなり「畢竟じて同じく寂滅平等を得る」ことが真実となる。曇鸞はこのことを以下の二番の問答で詳細に明かし、そのことが阿弥陀仏の本願力(不虚作住持力)によってのみ、なりたつことを以下巻末にいたる解釈の核心として顕らかにしていく。
『解読浄土論註』326-329頁
問い。『十地経』をひもといてみるに、菩薩が上へと進んでいく段階は徐徐なるものであって、はかりしれぬ(修行の)功績をつみ、長い長い時間をかけて、その後にようやくその位を得るのである。どうして阿弥陀仏を見たてまつったその時に、畢竟に上地の菩薩たちと身も法も等しくなるというようなことがあろうか。
答え。「畢竟」というのは、ただちに等しいということではない。畢竟じて等しいことが解消されないから「等しい」というにほかならないのである。
問い。もしただちに等しくなるのでないなら、またどうしてまわりくどく(上地の)菩薩(と等しい)という必要があろうか。(つまり)初地に登りさえすれば、だんだんに前進して、(ついには)自然と仏に等しくなるはずである。(とすれば)どうしてかりにも上地の菩薩と等しいなどと言うに及ぼうか。
答え。菩薩は、七地の中において大寂滅(の境地)を得るのであるが、(その時この菩薩は)上に求むべき諸仏を見ず、下にすくうべき衆生を見なくなって、仏への道を捨てて実際(涅槃)に入ろうとする。その時もし十方(世界)の諸仏の威大な力によるはげましが得られなかったら、たちまち滅度してしまって、二乗と何らかわりがなくなってしまうのである。
(しかるに)菩薩がもし安楽国に往生して阿弥陀仏を見たてまつるなら、このような難関は無くなるのである。だから畢竟じて(上地の菩薩と)平等であるという必要があるのである。
さらに次に、『無量寿経』の中の阿弥陀如来の本願(22願)にいわれている。「もし私が仏となるなら、他方の仏土からたくさんの菩薩たちが私の国に生れ来たって、つまるところ必ず(菩薩の究竟位たる)一生補処に至るであろう。ただ、その菩薩の(特別の)本願によって、おもいのまま衆生を教化しようとし、広大な誓願の鎧を身にまとい、善根功徳をつみかさね、すべてのものをすくい、諸仏の国に遊行して菩薩の行を修習して、十方(国土)の諸仏如来を供養し、はかりしれぬ数の衆生を開化して、無上なる正真へいたる道に立たしめようとするものはその願いのままにあらしめよう。(これらの菩薩は)常なみの(菩薩の)倫を超え出て、諸地の修行をことごとく実現し、普賢(菩薩の大悲の行)の功徳を修習するであろう。もしそうでなかったら正覚をとるまい」と。
この『経』(文)をいただいて彼の安楽国の菩薩についておもうに、おそらく一地より一地へと進むのではあるまい。十地の階位というのは、釈迦如来がこの人間世界にしめされた一つの応化の道にほかならないのである。他方の浄土が必ずしもそのとおりである必要はない。(そもそも)五種の不思議の中で(弥陀の本願を説く)仏法は最も不可思議なるものである。もし「菩薩は必ず一地より一地へと進むものであって、それを一気にとびこえるなどという道理はないのだ」と言うなら、それはまだ(仏法の不可思議なることを)くわしく知らないのである。
たとえば好堅という名の樹がある。この樹は地(中)で百歳(の年月を)かけて(枝や葉を)ことごとくつけ、(地上に出るやいなや)一日で高さ百丈に成長する。日日このように成長して百歳になったときの高さを計るなら、どんなにたけの高い松でもおよぶはずはない。松の生長するのをみんば、一日せいぜい一寸たらずである。(そんな常識で)彼の好堅のことを聞けば、たちまち日に百丈のびるなどとは、どうしても疑わずにはおれないであろう。
人あって、釈迦如来が一度聴かすだけで(ある人に)阿羅漢をさとらせ、(また)ごく短い時間にらくらくと無生法忍をえさしめたということを聞いて、これは(凡夫を仏道に)いざなう言であって、真実にかなった説ではないといっている。(このような人は)この浄土論の説事を聞いてもまた信じないであろう。(そもそも)非常の言というものは常人の耳には入らないものであって、この論をまちがっているというのもまた仕方のないことであろう。〔証p.286-287〕
一生補処
菩薩の最高位たる等覚をさす。一生は有的生存の最後の一瞬のこと。この一瞬を過ぎれば仏の位処を補うことができるので補処という。究竟位、一生所繋ともいう。
普賢之徳
諸仏の本源、諸法の体性を普賢といい、また普法を信じ、解し、行じ、証する者を普賢菩薩と名づける。華厳宗では、仏のさとりの世界(性海果分)に対して、そのようなさとりを説きおこした因(縁起因分)を普賢の徳に帰する。
『法華経義疏』(吉蔵549 – 623作)第十二には「普に二義あり。一には法身の普なり、一切処に遍ずるが故に総摂す。三世仏の法身は皆是れ普賢の法身なり。華厳に普賢の身相は猶虚空の如く、如如に依りて仏国に依らずと云うが如きなり。二に応身の普なり、普く十方に応じて一切の方便を作す。故に十方三世仏の応身は皆是れ普賢の応身、皆是れ普賢の応用なり。故に『智度論』に云わく、普賢はその所住の処を説くべからず、若し説かんと欲せば、応に一切世間の中に在りて住すべし、と。即ち其の証なり」とのべられている。また、普賢は常に諸仏を礼敬し、如来を称讃し、仏に転法輪を請い、無始以来の悪業を懺悔して浄戒をたもつ等の十大願を具足し実践するものである。
『解読浄土論註』333頁
3 如来の自利と利他の成就
(大)略して八句を説き、如来の自利と利他との功徳が順次かざりあげられていることをあきらかにした。(この次第を)よく承知すべきである。
これはどのような次第か。前の十七句は国土の功徳をかざりあげたものであった。すでに国土の相を知ったからには、その国土の主について知らねばならない。だから次に仏のかざりあげられた功徳を観ずるのである。
彼の(安楽国にまします)仏はどのようにかざられて、どのような場処に坐っておられるのだろうか。だからまず座を観ずるのである。
座について知ったうえは、この座の主をしらねばならない。だから次に仏の身業についてかざられていることを観ずるのである。
身業を知ったうえは、どのような声名であるかを知らねばならない。だから次に仏の口業についてかざられていることを観ずるのである。
名の(十方に)聞こえることを知ったうえは、その名をえられたわけを知らねばならない。だから次に心業についてかざられていることを観ずるのである。
すでに三つの業がまどかに満足していることを知ったうえは、人天の大師たる仏より教化にあずかるべきものは誰か(を知らねばならない)。だから次に(仏の)大衆の功徳を観ずるのである。
大衆に無量なる功徳のあることを知ったうえは、(大衆の)上首は誰かを知らねばならない。だから次に上首を観ずるのである。上首は仏である。
上首を知ったうえは、それが、年長とか年下とか(という区別)と混同される恐れがあるから、次に主を観ずるのである。
(上首は)主であることを知ったうえは、主はどのような増上(力)を有しておられるか(を知らねばならない)。
だから次にむなしくすぎゆくものなき住持(の力)を観ずるのである。
(以上で)八句の次第をまっとうしおわった。〔証p.287-288〕
『解読浄土論註』337頁
③ 菩薩荘厳の成就
1 菩薩四種の正修行を示す
菩薩を観察するとは(つぎのようにいわれている)。
菩薩をかざりあげた功徳をどのように観察するのか。菩薩をかざりあげた功徳を観察するとは、彼の(浄土の)菩薩には四種の正しい修行の功徳がまどかにそなわっていることを観察するのである。(この四種の功徳の次第を)よく承知すべきである。
真如はあらゆる法の正しき本体である。その本体のままに修行するから、それは(何かを)修行するのではない。修行せずして(つねに)修行していることを如実なる修行という。(このように修行の)体はひとえに一如であるが、その意義を分ければ四(種)の行は正しく一つに統一されるのである。〔証p.288〕
『解読浄土論註』340頁
1 不動にして応化する功徳(不動応化功徳)
(菩薩の)四(種)とはどのようなものであるか。
まず第一には、(浄土の菩薩は)仏の国土にあって身をまったく動かさず、しかもあまねく十方(の世界)に至って、いろいろに応化し、真実のままに修行して、つねに仏のいとなみをなすのである。偈に「安楽国は清浄にして、常に無垢の輪を転ず、化仏菩薩の日、須弥の住持するが如し」と言うのがそれである。(これは)あらゆる衆生の淤泥華を開かんがためである。
八地已上の菩薩は、つねに三昧にあって、その三昧の力によって、身を本の場処からまったく動かさず、しかもあまねく十方(の世界)に至って、諸仏を供養し衆生を教化するのである。
「垢なき(法)輪」とは、仏地の功徳である。仏地の功徳は煩悩のなごりの垢さえとどめない。仏はあらゆる菩薩のために、いつもこのような法輪を転じ、種々の大菩薩もまたよくこの法輪をもってすべて(の衆生)を開導して、かたときも休むことがない。だから「つねに転ず」と言うのである。
法身は日(太陽)のように(不動であり)、しかも応化身の光はあまねく世界にふりそそぐのである。日(太陽)というだけではその不動なることを明らかにするにはまだ足らないので、かさねて「須弥山がとわにそびえて不動なようである」と言うのである。
淤泥華とは、『経』(維摩経)に「高原のような陸地では蓮花は生じない、じめじめした淤泥にこそ蓮花は生じる」といわれている(あの蓮花のことである)。これは凡夫が煩悩の泥の中にありながら、菩薩によって開導されて、よく仏の正覚の花をさかせることに喩えたのである。まことこのように、(浄土の菩薩は)三宝をさかえさせて、いつまでも絶やすことがないのである。〔証p.288〕
『解読浄土論註』344頁
2 同時に十方に至る功徳(一念遍示功徳)
二には、彼の(浄土の菩薩の)応化身は、あらゆる時間に前後の区別なく、一心一念のうちに大いなる光明を放ち、ことごとく十方の世界に至って衆生を教化し、いろいろ方便をつくして修行するのである。その修行するところは、生きとし生けるものの苦しみをとりのぞかんがためである。偈に「無垢荘厳の光、一念および一時に、普く諸仏の会を照らし、もろもろの群生を利益するゆえに」と言うのがそれである。
まえに「動かずして至る」と言われているが、あるいはその至りかたに(時間の)前後があるかもしれない。だからかさねて「一念一時で前後なし」というのである。
3 諸仏を供養する功徳(無余供養功徳)
三には、彼(の応化身)は、あらゆる世界に至るにあますところもなく、諸仏の会座に集まった大衆を照らすにあますものもなく、広大無量に諸仏如来の功徳を供養し、恭敬し、讃嘆するのである。偈に「天の楽と花と衣と、妙香等を雨りて供養し、諸仏の功徳を讃えるに、分別の心あることなきがゆえに」と言うのがそれである。
「あますところなく」とは、すべての世界の、すべての諸仏の(説法の)大会にあまねく至って、一世界、一仏会にも至らぬこととてないということを明かすのである。
僧肇師のことば(『注維摩経』)に、「法身は像なく、しかも形をあらわしてあらゆる衆生(の求め)に応じ、このうえない説法の音声は言をこえ、しかも深遠な経典がひろくゆきわたり、はかりしれぬ権は(衆生を救おうなどという)はからいをまじえることなく、しかもあらゆる動きをあらわして(衆生救済の)事をする」とある。およそこれが(浄土の菩薩の徳をあらわす)意味である。
4 「三宝なき世界」へはたらく功徳(遍至三宝功徳)
四には、彼(の応化身)は、十方のあらゆる世界のうちで、三宝のないところにおいて仏法僧の三宝の大会のごとき功徳をとわにたもちかざりあげて、あまねく(世界に)示現して、真実のままなる修行を(衆生に)解らしめるのである。偈に「何等の世界にか、仏法功徳の宝ましまさぬ。我願わくはみな往生して、仏法を示すこと仏のごとくせんと」と言うのがそれである。
さきの三句は「遍ねく至る」とは言うものの、すべて仏のまします国土についてである。もしこの句がなかったら、法身というも場所によって法でないことがあり、このうえない善というも場所によっては善でないことがあることになるのである。
(以上で)観行の体相を明らかにしおわった。〔証p.288-289〕
『解読浄土論註』349頁
五 願心の荘厳(浄入願心)
已下は、偈の意味を解釈する中の第四段目であって、浄入願心と名づける。清浄(なる三種の荘厳)が(法蔵菩薩の)願心におさまるとは、(つぎのようにいわれているからである)
また、さきに仏土の功徳がりっぱにかざりあげられているすがた、仏がりっぱにかざりあげられているすがた、菩薩がりっぱにかざりあげられているすがたを観察することを説いてきたが、この三種がみごとに完成しているのは、(法蔵菩薩の)願心によってかざりあげられたものだからである。このことをよく承知すべきである。
「承知すべきである」とは、この三種のかざりが完成しているのは、もともと四十八願(を発したところ)の清浄なる願心によってかざられているからで、因(たる願心)が清浄であるから果(としての三種)が清浄なのであって、因がない(のに果が清浄だ)とか、他の因(によって清浄なる三種のかざりが)あるとかということではない、ということをよく承知すべきだというのである。〔信p.233-234〕
1 一法句と三種荘厳
(大)略していえば、(三種のかざりは)一法句におさまる。
さきにのべた国土のかざりたる十七句と、如来のかざりたる八句と、菩薩のかざりたる四句とを広とし、一法句におさまることを略とする。
(そして)なぜ広と略とが相入することを(論が)ときあらわすかといえば、諸仏菩薩には二種の法身がそなわっている。一には法性法身、二には方便法身である(法性法身は略の一法句であり、方便法身は広の二十九種荘厳である)。法性法身によって方便法身が生じ、方便法身によって法性法身があらわれる。この二法身は異っていてしかも分けることはできず、(といって)一であってしかも同じだとするわけにはゆかない。
だから広(二十九種荘厳)と略(入一発句)とは相入し、統て法と名づけられるのである。菩薩は、もしこの広略相入することを知らなければ、けっして自利利他することはできないのである。〔証p.289-290〕
一法句
一法句は一如・真如の意。一は無二平等、法はダルマ。句はその真如が衆生を救済するはたらきとして世間的に顕現する態をあらわす。その場合の句は梵語(処・依処・依事)に相当し、無相なる真如が、有相としての句に顕現する、つまり、無の有としての浄土の荘厳をあらわすものと考えられる。従って一法句を先には第一義諦とあらわし、この下の論註では法性法身とあらわす意味が首肯できる。(詳しくは山口益著『世親の浄土論』152頁以下参照)
『解読浄土論註』353頁
2 一法句とは清浄句なり
一法句とは清浄句である。清浄句とは真実の智慧たる無為法身をいう。
この(「一法句」「清浄句」「真実の智慧・無為法身」)三句はまわりまわってたがいにおさまりあうのである。(つまり)どのようなわけで浄土のかざりを(一)法(句)と名づけるかといえば、清浄(句)だからであり、どうして清浄と名づけるかといえば、真実の智慧たる無為法身であるからである。
真実の智慧とは(諸法の)実の相にめざめた智慧のことである。実の相は無相であるから、真実の智慧は(何かを)知るということの無いものである。(また)無為法身とは法性身のことである。法性は(あらゆる相をはなれた)寂滅なるものであるから、法身は無相である。無相だからあらゆる相をとることができるのである。だから(仏の)相好のかたどりがそのまま法身なのである。(また真実の智慧は)何かを知るということのないものであるから知らないというところもさらにない。だから一切を知る智慧がそのまま真実の智慧である。
真実ということばで智慧をあらわすのは、智慧は(何かを知ろうと)作意するのでなく、(さらに)作意するのでないということもないものであることを明らかにするのである。無為ということばで法身をあらわすのは、法身は色でなく、(さらに)色でないということもないものであることを明らかにするのである。
(ところで)何々でないということもないと(否定をかさねること)は、何々である(と肯定する)ことになろうか(なりはしない)。およそ肯定というのは否定がまったくないことである。(しかし、かといって)何々であると自分勝手にきめこんで、逆の立場に相対しないのも、ほんとうにそれをみとめたことにはならない。(法身は)何々であるということもなく、何々でないということもないのであって、百ぺん否定をかさねたところでたとえきることはできないのである。
このようなわけで清浄句というのである。つまり清浄句とは、真実の智慧たる無為法身をいうのである。〔証p.290〕
『解読浄土論註』357頁
3 二種世間清浄
この清浄に二種類ある。よく承知すべきである。
さきには、たがいにおさまりあう(三つの)句について、一法(句)が清浄(句)におさまり、清浄(句)が法身におさまるとのべられた。いまは、その清浄を二種にわけてあきらかにしようとするのである。だから「よく承知すべきだ」というのである。
二種とはどのようなものか。一には器世間の清浄、二には衆生世間の清浄である。
器世間の清浄とは、さきに説かれた十七種の仏土をかざりあげた功徳のことである。これを器世間の清浄と名づける。
衆生世間の清浄とは、さきに説かれた八種の仏をかざりあげた功徳と四種の菩薩をかざりあげた功徳のことである。これを衆生世間の清浄と名づける。
このように一法句のなかに二種の清浄がふくまれている。よく承知すべきである。
聖全Ⅰp338 往生論註
そもそも衆生とはみな別々のむくいをうける本体であり、国土とはすべてに共通してむくわれるはたらきである。本体とはたらきとは同じでない。このわけをよく承知すべきだといわれるのである。
しかしあらゆる存在は心によって生じるので、そうでない何かほかの境界があるのではない。したがって衆生も器(国土)も異なったものではありえない。(かといって)同じでもありえない。同じでないのは意味をわけるからであり、異なっていないのはともに清浄だからである。
器とは用ということである。つまり彼の浄土は彼の清浄な衆生が受け用いるところだから器というのである。たとえば、浄らかな食物をきたない器にもれば、器がきたないから食物もきたなくなる。きたない食物を浄らかな器にもれば、食物がきたないから器もきたなくなる。かならず両方ともに潔らかであってはじめて「浄」ということができる。だから清浄という一つの名には必ず二種(の意味)がこめられているのである。
問い。(浄土の)衆生が清浄というのは、仏と菩薩とであって、彼の(浄土の)人天はこの清浄のなかまに入ることができるのかどうか。
答え。清浄ということはできるが、真実の清浄ではない。たとえば出家の聖人はすでに煩悩の賊を殺してしまっているから比丘とよぶ(のが当然だ)が、まだ凡夫のままでいる出家者で持戒や破戒のものもすべて比丘とよぶ、というようなものである。また、灌頂王子がはじめて世に生れたとき、三十二相を具し、七宝(の徳)を所有する身であったので、まだ転輪王としての事業をなすことはできないが転輪王とよんだ、というようなものである。彼は必ず転輪王となるべき人だったからである。彼の人天もこれと同じで、みな大乗の正定をえたひとびとのなかまに入り、ついには清浄な法身を得るのである。かならずそうなるときまっているから清浄と名づけることができるのである。〔証p.291-292〕
『解読浄土論註』363頁
六 方便による衆生救済(善巧摂化)
1 柔軟心のめざめ
善巧に(衆生を)摂め教化するとは、(つぎのようにいわれている)
このように菩薩は、奢摩他と毘婆舎那とを広・略に修行して、柔軟な心を完成させるのである、と。
柔軟な心とは、広・略の止と観とをたがいに調和させて修行して、(止と観とがばらばらでない)不二の心を完成させることである。たとえば、水にものの影をうつす場合、清く静かという二つの条件がたがいにたすけあってはじめて完全にうつるというようなものである。
実のままに広(たる二十九種のかざり)と略(たる一法句)との諸法を知るのである。
「実のままに知る」とは、実の相のとおりに知ることである。広の中の二十九の句も、略の中の一句も、実の相でないものはない。
このように(菩薩は)巧みな方便である回向(の門)を成就するのである。
「このように」とは前後にのべられた広と略とがすべて実の相のとおりであることをいう。実の相を知ることによって、三界の衆生が虚妄の相でいることを知るのである。そして衆生が虚妄であることを知れば、おのずから真実の慈悲が生じる。また真実の法身を知れば、おのずから真実の帰依(の心)がおこる。この慈悲と帰依とによる方便については以下にのべられている。〔証p.292〕
『解読浄土論註』367頁
2 無上菩提の歩み
菩薩の巧みな方便である回向とはどのようなものか。菩薩の巧みな方便である回向とは、前に説いてきた礼拝などの五種の修行の功徳をすべて集めた善根によって、自分が法に安住する楽を求めずに、あらゆる衆生のくるしみをとりのぞこうとすることをいう。つまりすべての衆生をすくいとって、ともに同じく彼の安楽仏国に生れたいと願う、これを菩薩の巧みな方便である回向の完成と名づけるのである。
王舎城で説かれた『無量寿経』をひもとくに、三輩の往生には、行について優劣があるけれども、どれ一つとして無上なる菩提の心を発さないものはない。この無上なる菩提の心は、そのまま仏になろうと願う心であり、仏になろうと願う心はとりもなおさず衆生を救済しようとする心である。この衆生を救済しようとする心が、衆生をすくいとって仏まします国土に生れさせんとする心である。だから、彼の安楽浄土に生れたいと願う者は、かならず無上なる菩提の心を発すのである。〔信p.242〕
もし人が無上なる菩提の心を発さずに、彼の国土は楽しいことばかりつづいているとだけ聞いて、その楽のために生れたいと願うのであれば、それも往生することはできないであろう。だから「自分が法に安住する楽を求めず、すべての衆生のくるしみをとりのぞこうとおもう」と言われるのである。
「安住する楽」とは、彼の安楽浄土は阿弥陀如来の本願の力によって安らかにたもたれていて、楽をうけることかぎりがないことをいうのである。
回向という名の意味をひろく解釈すれば、自分が集めたすべての功徳を生きとし生けるものにほどこして、ともに仏の道に向かわしめるということである。〔信p.237〕
「巧みな方便」とは、菩薩がみずからの智慧の火で、生きとし生けるものの煩悩の草木を焼きはらおうとするに、もしひとりでも仏にならなかったら、自分は仏とならないと願うことである。
ところで、それらの衆生がまだすべて仏にならないうちに、菩薩が自分だけ仏になるのは、たとえば木製の火ばしで草木をつまんで、すべてを焼きつくそうとするに、草木がまだ焼きつくされないうちに火ばしのほうが燃えつきてしまうというようなものである。このように菩薩は、自分の身をあとまわしにしながら、(結果としては)人より先んずることになる。だから巧みな方便というのである。
この論に「方便」といわれているのは、生きとし生けるものをすくいとって、共に同じく彼の安楽仏国に生れたいと願うことをいうのである.彼の仏の国は、このうえなき成仏の道路であり、無上なる方便である。〔証292-293〕
ここで「回向」ということばの意味を解釈すると、仏がご自身で集められた功徳のすべてを衆生に施して、共に仏道に向かわせることをいうのである。
また「巧みな方便」とは、菩薩がみずからのめざめた智慧の火で、あらゆる衆生の煩悩の草木を焼きつくそうと願い、もし衆生の一人でも仏になれないものがいるならば、みがすらは仏にならないと誓うのである。
ところが、まだこの世の衆生がみな成仏しないうちに、菩薩が先に成仏されたということは、たとえていうと、木の箸で一切の草木を積みとって焼く場合に、まだ草木すべてを焼きつくさないうちに、火のつけ木のほうが燃え尽きてしまうようなものである。そのような菩薩は自分の身を後にしながら、すべての衆生の救いを誓い、先に成仏していることになる。だから、「巧みな方便」と名づけるのである。
ここに方便というのは、「あらゆ衆生を救いとって、共に同じく阿弥陀仏の安楽国に生れたいと願う」ことである。彼の安楽浄土は、とりもなおさず衆生が仏になる道路であり、無上なる方便であるからである。神戸和麿訳
『解読浄土論註』371頁
七 菩提の障りを離れる門(障菩提門)
菩提にいたる門を障げる(心を離れる)とは、(つぎのようにいわれている)
菩薩はこのようにして善く回向が成就されたことを知って、ただちに菩提の門に相違する三種の法を離れるのである。
三種とはどのようなものか。
一には、「智慧の門」によって、自己の楽を求めず、我の心によって自己自身に貪着することを離れるのである。
前進することを知って退却することをふせぐことを「智」といい、(あらゆる存在は)空であり無我であると知るのを「慧」という。智によるから自己の楽を求めず、慧によるから我の心によって自己自身に貪着することをまったく離れるのである。
二には、「慈悲の門」によって、生きとし生ける者のくるしみをのぞき、衆生を安らかにすることのできない心を離れるのである。
くるしみをとりのぞくことを「慈」といい、楽を与えることを「悲」という。慈によるから生きとし生ける者のくるしみをとりのぞき、悲によるから衆生を安らかにすることのできない心を離れるのである。
三には、「方便の門」によって、生きとし生けるものをいつくしみ、自己自身が供養され、うやまわれたいという心をまったく離れるのである。
正直なことを「方」といい、自己を外にすることを「便」という。正直によるからあらゆる衆生をいつくしむ心を生じ、自己を外にするから、自己自身が供養され、うやまわれたいという心を離れるのである。
これを菩提の門に相違する三種の法を離れるというのである。〔証p.293-294〕
『解読浄土論註』376頁
八 菩提に順う門(順菩提門)
菩提の門に順ずるとは、(つぎのようにいわれている)
菩薩はこのような菩提の門に相違する三種の法をはなれて、菩提の門に随順する三種の法に満足をうるのである。
三種とはどのようなものか。
一には染れのない清浄な心、この心は自分のためにいろいろな楽を求めることがないのである。
菩提は染れのない清浄の場処である。もし自身のために楽を求めるならば、菩提にそむくことになる。だから染れのない清浄な心は菩提に順がう門である。
二には衆生を安らかにする清浄な心、この心はあらゆる衆生のくるしみをとりのぞくのである。
菩提はすべての衆生を安穏にする清浄の場所である。もしわざとあらゆる衆生をほったらかしにして生死の苦しみを離れさせないなら、菩提にそむくことになる。だからすべての衆生の苦しみをとりのぞくことは、菩提に順がう門である。
三には衆生に楽をあたえる清浄な心、この心はすべての衆生に大菩提を得させ、衆生をすくいとって、彼の安楽国土に生れさせるのである。
菩提はこのうえない常楽の場処である。もしすべての衆生に、このうえない常楽をあたえないなら、菩提にたがうことになる。この無上なる常楽は何によって得ることができるかといえば、大乗門によってである。大乗門とは、彼の安楽仏国のことをいう。だからまた「衆生をすくいとって、彼の安楽国土に生れさせる」と言われるのである。
これを菩提の門に随順する三種の法が満足したという。よく承知すべきである。〔証p.294〕
『解読浄土論註』380頁
九 智慧・慈悲・方便の名とその意味(名義摂対)
1 般若と方便
名の義を摂め対べるとは(つぎのようにいわれている)
さき(障菩提門)に説いた智慧と慈悲と方便との三種の門は、般若をおさめており、般若は方便をおさめている。このことをよく承知すべきである。
「般若」とは真如に到達した智慧に名づけ、「方便」とは権に通ずる智慧をいう。真如に到達すれば心の(分別の)はたらきはことごとく滅するが、権に通ずればことこまかに衆生の根機をかえりみるのである。根機をかえりみる智慧は、衆生のねがいに一つ一つ応るものでありながら、しかも何かを知るということのないものである。心のはたらきの滅した智慧も、何かを知るということのないものでありながら、しかもことこまかに衆生のことを思っている。だからこそ、智慧(般若)と方便とはたがいに縁となって(衆生救済の)動きをあらわし、またたがいに縁となって(涅槃の)静なることをあらわすのである。(衆生救済の)動きが静なることを失わないのは智慧(般若)のおかげであり、その静が動をさまたげないのは方便の力である。だから、智慧と慈悲と方便とは般若をおさめており、般若は方便をおさめているのである。
「よく承知すべきである」というのは、智慧と方便とは菩薩の父と母とであって、智慧と方便とによらなければ菩薩の法は成就することがない、ということをよく承知すべきだというのである。なぜかといえば、もし智慧をもたずに(教化を)する時は、よこしまな道におちいるし、もし方便なくして法性を観ずる時は、二乗のさとりを証することになる。だから「よく承知すべきだ」というのである。〔証p.294-295〕
『解読浄土論註』384頁
2 菩提心を障げるもの
さき(障菩提門)に、我の心をはなれ自身に貪着しないこと、衆生を安らかにすることのできない心をはなれること、自己自身が供養され、うやまわれたいとおもう心をはなれる(法)について説いたが、この三種の法によって菩提をさまたげる心をはなれるのである。このことをよく承知すべきである。
いろいろの存在には、それぞれ障害となる相がある。たとえば風は静寂をさまたげ、土は水をさまたげ、湿気は火をさまたげるというようなものである。また、五悪・十悪は人天(に生れること)をさまたげ、四顛倒は声聞のさとりをさまたげる。この論にとく三種の心は菩提をさまたげる心をはなれないのである。
「承知すべきだ」とは、もし、さまたげのないことを得ようとおもうなら、この三種の障害(となる心)をはなれるべきだというのである。
3 三種の清浄心
さき(順菩提門)に、染のない清浄な心、衆生を安らかにする清浄な心、衆生に楽をあたえる清浄な心について説いたが、この三種の心は大略すれば同一場処のものであって、妙楽にして勝れた真心を完成させるのである。
このことをよく承知すべきである。
楽に三種ある。一には外楽、これは五識によって生ずる楽である。二には内楽、これは初禅・二禅・三禅(の世界)の意識によって生ずる楽である。三には法楽の楽、いわゆる智慧によって生ずる楽である。この智慧によって生ずる楽は、仏の功徳を愛しむことから起るのであって、これは我の心をはなれ、衆生を安らかにすることのできない心をはなれ、自分が供養されたいとおもう心をはなれるところの智慧である。そしてこの三種の心がだんだん清浄さを増していくと、大略して妙楽にして勝れた真心となるのである。
「妙」とは好(すぐれた)ということである。それはこの楽が仏をよすがとして生ずるからである。「勝」とはまよいの世界にある楽をこえているということである。「真」とは虚偽でなく、顛倒でないということである。〔証p.295-296〕
『解読浄土論註』388頁
十 菩薩の清浄心と五念門の行(願事成就)
(浄土に生れたいという)願いの事業が成就するとは(つぎのようにいわれている)
このように菩薩は、智慧の心と方便の心と菩提を障げることのない心と勝れた真の心とによって、清浄なる仏の国土に生れることができるのである。このことをよく承知すべきである。
「承知すべきだ」とは、この四種の清浄なる功徳によって、かの清浄なる仏の国土に生れることができるのであって、その他の縁によって生れるのではない、ということをよく承知すべきだというのである。
これを、大菩薩は五種の法門にしたがって、行おうとすることすべてがおもいのまま自由自在に成しとげられる、と名づける。さきに説かれたように、身の業、口の業、意の業、智慧の業、方便智の業は、(浄土に生れることに)随順する法門であるからである。
「おもいのまま自由自在」とは、この五種の功徳の力によってよく清浄なる仏国に生れ、出るも没するも自由自在であるということである。「身の業」とは礼拝すること、「口の業」とは讃嘆すること、「意の業」とは作願すること、「智慧の業」とは観察すること、「方便智の業」とは回向することである。この五種の業が和合すれば、浄土へ往生する法門に随順し、自在なる業が成就する、というのである。〔証p.296〕
『解読浄土論註』390頁
十一 衆生救済の行の成就(利行満足)
1 五種の門と五功徳の相
自利利他の行がまどかに満たされるとは、(つぎのようにいわれている)
さらに五種の門があって、順次に五種の功徳を成就せしめるのである。よく承知すべきである。
五種の門とはどのようなものかといえば、一には近門、二には大会衆門、三には宅門、四には屋門、五には園林遊戯地門である。
この五種は、(浄土に)入り(教化に)出る相を順番にあらわしている。
入る相の中で、まずはじめは浄土へ至る(相をあらわす)、これが近相である。つまり、大乗の正定をえたひとびとのなかまに入って、阿耨多羅三藐三菩提に近づくのである。
(つぎに)浄土に入ってしまえば、如来の説法の大会に集う衆の数に入ることになる。
衆の数に入れば、心おきなく修行し、心を安んずることのできる宅にたどりつくのである。
宅に入れば、修行ひとすじに居住する屋に入るのである。
そして、修行がまったくできあがれば、(衆生を)教化する場処へとでかけるのである。その教化の場処は、菩薩が自らすすんで楽しむ場処であるから、(教化に)出る門のことを園林遊戯地門というのである。〔証p.296〕
『解読浄土論註』394頁
この五種の門のうち、はじめの四種の門は(浄土に)入るについての功徳を成就し、第五の門は(教化に)出るについての功徳を成就している。
この入と出との功徳とはどのようなものかといえば、つぎのようにときあかされている。
入の第一門とは、阿弥陀仏を礼拝し、彼の国に生れんとすることによって、安楽世界に生れることができることをいう。これを入の第一門と名づける。
仏を礼拝してかの国に生まれんと願うというのが、最初の功徳のすがたである。
入の第二門とは、阿弥陀仏を讃えまつり、名の義にこころからしたがって如来の名を称し、如来の光り明らかな智慧の相に依って修行して、その徳をもって仏の説法の大会にあつまる衆のなかまに入ることができることをいう。これを入の第二門と名づける。
如来の名の義のままに讃えまつるというのが、第二の功徳のすがたである。
入の第三門とは、一心にひたすら願いをなしてかの国に生れ、奢摩他・寂静三昧の行を修することによって、(清浄な)蓮華蔵世界に入ることができることをいう。
これを入の第三門と名づける。
(一法句に入るところの)寂静止を修行せんがために、一心にかの国に生れんと願うのが、第三の功徳の相である。
入の第四門とは、ひたすらにかの浄土の妙なるかざりを観察し、毘婆舎那を修行することによって、かの(阿弥陀仏の)処に到ることができ、仏法についてのいろいろな楽しみを味わうということである。これを入の第四門と名づける。
「いろいろな仏法の味楽」とは、(浄土のかざりを観察する)毘婆舎那には、仏の国土を観てその清浄さにふれる味楽、一切の衆生を大乗に入れてひとすじに生かしめる味楽、衆生にいつまでも功徳をたもたせ(仏道から退転するような)虚しい行為をさせぬ味楽、衆生に応じて救済し、仏を供養し、自ら願ってあらゆる世界を仏の国土とする味楽などがある。このようにかぞえきれないかざりによる仏道の味わいがあるから、「いろいろな」というのである。これが第四門の功徳のすがたである。〔証p.296-297〕
『解読浄土論註』399頁
(教化に)出る第五の門とは、大いなる慈悲をもって苦悩するすべての衆生のすがたを観察し、それらの衆生に応じて身を変じて、生死の園である煩悩しげき世界に入り、神通をあらわして遊戯し、衆生教化をまっとうするということである。それはもともと衆生を救済しようとする本願の力が回向されているからである。これを出の第五門と名づける。〔信p.234〕〔証p.284〕
「衆生に応じて身を変じてあらわれる」とは、『法華経』の普門品に(観世音菩薩の)変化身について説かれているような類の意味である。
遊戯というには二つの意味がある。
一つには自在という意味である。つまり、菩薩が衆生を救済するのは、たとえば獅子が鹿を手どりにして、どうしようが、こうしようが思いのまま、まったく遊びたわむれているのににているということである。
二には救済しても救済されたものは無いという意味である。つまり菩薩が衆生を観るのは、もともと衆生という実体があるのではないということを観るのだから、かぎりない衆生を救済しても、真実にはひとりとして滅度をえた衆生が別にあるわけではない。このように、菩薩が衆生を救済するのは、あたかも遊びたわむれているようなものなのである。
「本願の力」というのは、大菩薩は法身のうちでつねに三昧にあって、さまざまの身、さまざまな神通、さまざまな説法をあらわすが、これはすべて本願の力によって起すのだということである。たとえば阿修羅の琴は弾く者がなくても、自然と音楽が奏でられるというようなものである。
これを、「教化ということがかなえられる第五の功徳のすがた」と名づけるのである。〔行p.193〕〔証p.297-298〕
『解読浄土論註』402頁
2 自利の成就と利他の成就
菩薩は(浄土に)入る四種の門によって自利の修行を成就する。このことをよく承知すべきである。
「成就する」とは、菩薩自身のための行が完全になしとげられたことをいう。
「よく承知すべきだ」とは、自利することがあるからよく利他することができるのであって、自利することができなくて利他することができるということはありえない、ということをよく承知すべきだというのである。
菩薩は(教化に)出る第五の門によって、(自分の功徳を)回向して衆生を利益する行を成就するのである。よく承知すべきである。
「成就する」とは、(功徳を他に)回向する因の修行によって、あまねく衆生を教化することができる果が実現されたことをいう。このように因であっても果であっても、何一つとして衆生を利益するためでないものはない。
「よく承知すべきだ」とは、利他することがあるから自利することができるのであって、利他することができなくて自利することができるのではない、ということをよく承知すべきだというのである。〔行p.193〕
『解読浄土論註』405頁
3 阿弥陀如来を増上縁とする
菩薩は、このようにして五念門の行をおさめ、自利利他して、すみやかに阿耨多羅三藐三菩提を成就されるのである。
仏の獲得された法を阿耨多羅三藐三菩提という。この菩提を獲得することによって仏と名づけるのである。いま「すみやかに阿耨多羅三藐三菩提を得る」といわれるのは、早く仏となることができるということである。
「阿」とは無ということ、「耨多羅」とは上ということ、「三藐」とは正ということ、「三」とは遍ということ、「菩提」とは道ということである。だからこれをすべてまとめて「無上正遍道」と訳する。
「無上」というのは、この(仏の)道は、道理をきわめ本性をつくして、これ以上にでた者はないということである。なぜこう言えるかといえば、正ということによるからである。
「正」とは(仏の)聖智をいう。(聖智は)法相のままに知ることであるから、正智と称するのである。法性は無相であるから、聖智は無知である。
「遍」というには二種の意味がある。一には(仏の)聖なる心があまねく一切の法を知るということ、二には法身があまねく法界に満ちているということである。心であれ身であれ、ゆきわたらないものはないのである。
「道」とは無碍の道のことである。『経』(華厳経)に「十方世界の無碍の人(すなわち諸仏)は、ただ一つの道によって生死を出られる」と言われている。「一つの道」とは唯一なる無碍の道である。
「無碍」とは生死はそのまま涅槃であると知ることをいう。このような不二の法門に入るということは、無碍の相をあらわすものである。〔行p.194〕
『解読浄土論註』408頁
問い。どのようなわけで「すみやかに阿耨多羅三藐三菩提を成就する」と言われるのか。
答え。『論』には「五門の行をおさめ、自利利他が成就することによるから」といわれている。
しかし、その根本をあきらかにするなら、阿弥陀如来が大きく強い縁となっておられるのである。
他利ということと、利他ということとは、正確にいえば左と右ぐらいの差がある。(すなわち)もし仏のほうから言うなら利他と言うべきであり、衆生のほうから言うなら他利と言うべきである。いまはまさに仏力をあらわさんとしている。だから利他という語によるのである。(自利利他することによって、すみやかに菩提をうるとは)このような意味であることを、いまこそはっきりと知るべきである。〔行p.194〕
『解読浄土論註』412頁
およそ、かの浄土に生れる(往相回向)こと、及び、かの浄土の菩薩・人天がなす(還相回向)(衆生救済のための)いろいろな行は、すべて阿弥陀如来の本願の力による。
なぜこう言うかといえば、もし仏の力でなかったら、(衆生の救済を誓われた)四十八願は、すべていたずらに設けられたものにすぎなくなるからである。
(よって)今、はっきりと三つの願を取りあげて、仏の力であるわけをあきらかにしよう。
(第18願、念仏往生の)願に言われている。「もし私が仏となるなら、あらゆる世界の衆生が、心から信じ楽って、私の国に生れたいとおもい、せめて十たびでも念仏し、もしそれで生れることができなかったら、私は正覚をとるまい。ただ、五逆の罪を犯すものと、正法をそしる者とはこのかぎりではない」と。
仏の願力によるから、わずか十たびの念仏でも、念仏すればたちまち往生することができるのである。往生できれば三界にあってまよいをくりかえすことをまぬがれる。まよいをくりかえすことがないから、すみやかに菩提を得ることができるのである。これが(仏の力によることの)第一の証拠である。
(第11願、必死滅度の)願に言われている。「もし私が仏となるなら、私の国の人天は、正定をえた人々のなかまに入って、かならず滅度に達するというのでなければ、私は正覚をとるまい」と。
仏の願力によるから、正定をえた人々のなかまに入るのである。正定をえた人々のなかまに入るから、かならず滅度に到達して、まよいくるしみにただよい流されるという心配がなくなるのである。だからすみやかに菩提を得ることができるのである。これが第二の証拠である。
(第22願、還相回向の)願に言われている。「もし私が仏となるなら、他方の仏土からたくさんの菩薩が私の国に生れ来たって、かならず(菩薩の最高位たる)一生補処に到達するように。ただ、その菩薩の本願によって、おもいのまま衆生を教化しようとし、大いなる誓願の鎧を身にまとい、徳を積みかさね、生きとし生けるものをすくい、諸仏の国に遊行して菩薩の行を修め、十方国土の諸仏如来を供養し、はかりしれぬ数の衆生をみちびいて無上なる正真にいたる道へ立たしめようとするものは、その願いのままにあらしめよう。(これらの菩薩は)常なみの菩薩の道を超え出て、諸地の修行をことごとく実現し、普賢(菩薩の大悲の行)の徳を身につけるであろう。もしそうでなかったら、私は正覚をとるまい」と。
仏の願力によるから、常なみの菩薩の道を超え出て、諸地の行をことごとく実現して、普賢菩薩の徳を身につけるのである。常なみの道である諸地の行を超え出るから、すみやかに菩提を得ることができるのである。これが第三の証拠である。
以上のことより他力ということを推察するに、すべてこれ(阿弥陀如来を)大きく強い縁とするのであって、
そうでないことは決してありえないのである。〔行p.194-195〕
的
宗祖加点本には「ヒトシク」との左訓があるが、一般には、明らかに、はっきりと、まさに、まことに、確かになどの意。
三願
順に第十八・第十一・第二十二の三願。第十八願は衆生往生のための行(五念門行―念仏)が仏願力によること、第十一願は正定聚の位に住し、滅度の果をうること(五功徳門中の前四門)が仏願力によること、第二十二願は還相回向としての普賢行(園林遊戯地門)が本願力によることの証しとして的取され、この三願によって衆生往生の因果がすべて本願力によることを明らかにし、もって他力を顕揚するのが、三願を的取する理由である。宗祖がこの第十八願よりさらに第十七願を開いて、四願によって二回向四法を建立された地盤はここにある。
『解読浄土論註』417頁
さらに一つの例をあげて、自力と他力のすがたをあらわそう。
たとえば人あって、三塗のくるしみをおそれるために、いろいろな禁戒をまもろうとし、禁戒をまもることによって禅定を修し、禅定によって神通力を身につけ、神通力によってありとあらゆる世界に遊行することができるようになる、というようなのを自力と名づけるのである。
又、たとえばロバにまたがっていくこともできない者が、転輪王の行列にしたがっていきさえすれば、たちまち虚空にかけのぼり、あらゆる世界におもいのままに遊行して少しも障害となるところがない、というようなものを他力と名づけるのである。
愚かではあるが、浄土の法を学ばんと後につづく者たちよ、他力に身をまかせるべきむねをよく聞いて、信心をおこすべきである。けっして自分だけの小さなおもいにひっこんでひとりよがりしないように。〔行p196〕
結章 仏教に相応して
無量寿修多羅の優婆提舎なる願偈について、大略してその意義を解くことは以上でおわった。
経のはじめには「如是」とある。これは信ずるということによってはじめて教えに入ることができることをあきらかにしている〔信p.232〕。そして一ばんおわりに「奉行」とあるのは、その数えをしっかり身につけおわったことをあらわしている。いまこの論では、はじめに帰命礼拝するとある。これは自らが(しっかり身につけ)宗旨としているものに、はっきりとした由のあることをあきらかにしている。そしておわりにあたって、いま「意義を解きおわった」とあるのは、自らにそなわったものの理をあきらかにしたということである。(経と論と)述作の人はちがっていても、(このように首尾一貫していることは)この論においてより例がしめされたのである。
無量寿経優婆提舎願生偈註 巻下(おわり)
禅定
真理に達した力によって得る不可思議・無碍自在な用き。ここでは戒・定・慧の慧にあたる。
奉行
『維摩詰所説経』の最後に「皆大歓喜信受奉行」とある語による。他の主な経典には「奉行」の言はないが、「信受」「受持」又は「聞仏所説」などとあって、いずれも「奉行」と同意である。