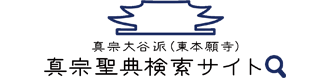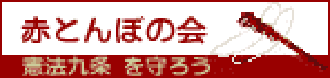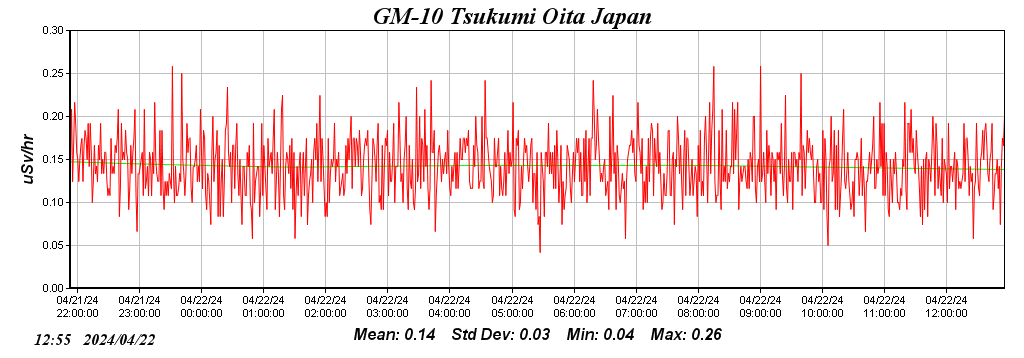『解読浄土論註』現代語訳 上
- utubnen
- 2023年1月17日
『解読浄土論註』の現代語訳解読を見て記載しています。『解読浄土論註』は1975年10月25日大分光西寺での育成員学習会に出席の際求めたものです。
青字は『教行信証』に引文された箇所
紫字は『解読浄土論註』の細註。『真宗新辞典』
偈の書き下しは、東本願寺出版発行の『真宗聖典』によっています。
『往生論註』原文のリンク先は聖教電子化研究会です。
この『解読浄土論註』の解読(現代語訳)文で改めたところがあります。
25頁「めくら」→「盲者(無明存在)」
109頁「譏嫌の名」の名前の箇所を省いています。
152頁「一人の目闇の比丘の」→「一人の失明の比丘の」
152頁、172頁、181頁、185頁「おまえ」→「あなた」
| 序章 本願の歴史 | 八 仏道の歴史への応答 |
| 一 『浄土論』の題名 | 九 観察門 |
| 二 『浄土論』の組織 | ①仏国土の荘厳 |
| 三 「願生偈」と五念門 | ②仏の荘厳 |
| 四 天親の一心帰命の信 | ③菩薩の荘厳 |
| 五 礼拝門 | 十 回向門 |
| 六 讃嘆門 | 十一 八番問答 |
| 七 作願門 |
『解読浄土論註』2頁
無量寿経優婆提舎願生偈註 巻上
世親菩薩(400頃~480頃)造る 曇鸞法師(476〜542)註解す
序章 本願の歴史
謹んで龍樹菩薩(150~250頃)の造られた『十住毘婆沙論』をひもといてみるに、次のようにいわれている。菩薩が不退転を求めるに、二種の道がある。一には難行道、ニには易行道である。
難行道とは、濁乱の世、仏ましまさぬ時に不退転を求めることが難しいことをいう。この難について、その相はいろいろあるが、今はその要点の若干をかかげて、難といわれるわけを説明することにする。
一には、外道のみせかけの善行は、菩薩の法を乱す。
二には、自分だけさとって、それで足れりと執することが、大慈悲を障げる。
三には、(内観のない)自らの悪を反省しない人は、他の人の勝れた徳をも破壊する。
四には、目前の利益にまどわされて、まじめに努力してきた効果を失ってしまう。
五には、道を求めてもただ自力ばかりをたのんで、他力にたもたれることがない。
このようなことなど、目に見えるものすべて難というべきことばかりである。ここに、不退転を求めることの難しさは、たとえば陸路を歩行すれば苦しいようなものである。
易行道は仏を信ずることのみをよすがとして浄土に生じたいと願えば、仏の願力に乗じて、やがてかの清浄の土に往生することができ、仏の本願の力に支えられて、大乗の正定をえた人々の仲間に入ることができるのである。この正定とは即ち不退転のことである。これをたとえれば、水路を船に乗って行けば楽しいようなものである。
この『無量寿経優婆提舎』は、およそ大乗の極致であり、順風を帆にうけて航海する大船にもたとえられるべきである。
正定聚
正性定聚・必定聚・直見際ともいう。三聚の一つで、正定聚は、かならず証果を得ると定まったもの。これに対して決して証果を得られぬものを邪定聚、縁あれば証果を得、縁なければ得られぬものを不定聚という。聚は仲間とか、集団のこと。
一 『浄土論』の題号
『解読浄土論註』9頁
「無量寿」はというのは、安楽浄土にまします如来にかぎっての名である。釈迦牟尼仏は王舎城及び舎衞国にましまして、大衆の中でこの無量寿仏の荘厳の功徳をお説きになられたので、無量寿仏の御名をそのままこの経の体とされたのである。
後の聖者バスバンズ(天親(旧訳)世親(新訳))菩薩は、如来の大悲の教えを身にいただいて、
無量寿経にもとづいて願生の偈をつくり、さらに長行を造って重ねて尊いみことばを解釈されたのである。
「優婆提舎」というのは、中国では訳語として的確なものがない。もし一面の意味をとれば、論とよぶことができる。訳語として的確なことばがないわけは、中国にはもともと仏がましまさなかったからである。たとえば中国の書だと、孔子に関するものは経といい、その他の人の製作したものはみな子(孟子・荘子・荀子などの書)と名づけ、国史や国記のたぐいでも、それぞれに体裁がちがっているようなものである。
ところで、仏の説かれた十二部経(経典を十二種に分類したもの)の中に、論議経というのがあって、これは優婆提舎と名づけられる。さらに仏の弟子たちが、仏の説かれた経の教えを解釈して、それが仏の教えの意味にかなっていれば、仏はそれを優婆提舎と名づけることを許された。それらが、仏法の相を得ているからである。ところが、中国語で論といえば、単に論議ということでしかない。どうして的確にそのことばを訳することができようか。また女性を子どもに対しては母といい、兄に対しては妹というようなものであって、こういったことは、みなそれぞれの意味によって、名前がちがってくるのである。ただ女という名前だけで、母や妹をひっくるめてしまえば、女という本質にかわりはないが、尊いとか卑しいとかという意味が含まれないことになるではないか。ここに論というのもまた同様である。だからそのままサンスクリットの発音を残して、ウパデーシャというのである。
二 『浄土論』の組織
この論の全体はおよそ二重になっている。一つは総説の部分、二つは解釈の部分である。総説の部分というのは、前の五言句の偈が全部それであり、解釈の部分というのは「論に曰く」以下の長行が全部である。
二重にしたわけは二つのたてまえがあるからである。つまり、偈は経を読誦することによって、総まとめにしたものだからであり、論は偈を説明することによって、内容を解釈したものだからである。
『解読浄土論註』13頁
さて、題号の「無量寿」とは、つまり無量寿如来は寿命が永遠であって、はかりしられないという意味である。「経」とは常という意味である。いうこころは、安楽国にまします仏及び菩薩の清浄な荘厳の功徳と、その国土そのものの清浄な荘厳の功徳とが、衆生に対して大きく豊かな利益をもたらし、いつの世にも、はたらきをもちうるから、経と名づけるのである。
「優婆提舎」とは、仏の説かれた論議経の名である。
「願」とはこい楽うという意味である。「生」とは、天親菩薩が彼の安楽浄土に生まれたいと願い、
如来の清らかな蓮華の中に生まれることである。だから「願生」というのである。「偈」とは句の字数という意味である。五言の句で経典の内容を要約してうたうから偈というのである。
「婆藪」を天と訳し、「槃頭」を親と訳する。この人を天親と字する。この人のことは『付法蔵経』に出ている。
「菩薩」とは、サンスクリットの発音を全部あげると菩提薩埵というべきである。菩提とは仏の道をあらわすことばである。「薩埵」とは、あるいは衆生を意味し、あるいは勇健を意味する。仏道を求める衆生は勇猛で強健な志をもつから、菩提薩埵と名づけるのである。いまただ菩薩といわれているのは、翻訳者が省略したからにすぎない。
「造」も作るという意味である。人をとおして法を尊重しようとねがうところから、誰々が造ったといっている。
だから「無量寿経・優婆提舎・願生偈・婆藪槃頭菩薩造」と言うのである。
以上でこの論の題目の解説をおわる。
「婆藪槃頭菩薩論曰」というは、婆藪槃頭は天竺のことばなり。震旦には天親菩薩ともうす。またいまはいわく、世親菩薩ともうす。旧訳には天親、新訳には世親菩薩ともうす。論曰は、世親菩薩、弥陀の本願を釈しあらわしたまえる御ことを、論というなり。曰は、こころをあらわすことばなり。この論をば『浄土論』という。また『往生論』というなり。p.517 尊号真像銘文
三 「願生偈」と五念門
『解読浄土論註』15頁
(願生)偈の中を五念門に区分する。あとの長行に説明してある通りである。
まず第一行の四句には三念門が含まれている。上の三句は礼拝門と讃嘆門であり、下の一句は作願門である。
第二行は論主自ら、私は仏の経に依って論を造り、仏の教えといささかの相違もない、仏の教えのままを身にいただくところ、ただ如来大悲の御旨に基づくのであると述べられるのである。
なぜこう言われたかと言えば、「優婆提舎」という題目を充分なものにするためである。それと同事に、上の三門を全うし、下の二門を提起しようとしている。だから第一行に次いで説かれるのである。
第三行より廿一行をかぞえるまでは観察門である。
最後の一行は回向門である。
以上で偈の章の部門わけをおわる。
(国土1清浄) 観彼世界相 勝過三界道
(国土2量) 究竟如虚空 広大無辺際
(国土3性) 正道大慈悲 出世善根生
(国土4形相) 浄光明満足 如鏡日月輪
(国土5種々事) 備諸珍宝性 具足妙荘厳
(国土6妙色) 無垢光炎熾 明浄曜世間
(国土7触) 宝性功徳草 柔軟左右旋 触者生勝楽 過迦旃隣陀
(国土8-1水) 宝華千万種 弥覆池流泉 微風動華葉 交錯光乱転
(国土8-2地) 宮殿諸楼閣 観十方無碍 雑樹異光色 宝蘭遍囲繞
(国土8-3虚空) 無量宝交絡 羅網遍虚空 種種鈴発響 宣吐妙法音
(国土9雨) 雨花衣荘厳 無量香普薰
(国土10光明) 仏恵明浄日 除世痴闇冥
(国土11妙声) 梵声悟深遠 微妙聞十方
(国土12主) 正覚阿弥陀 法王善住持
(国土13眷属) 如来浄華衆 正覚花化生
(国土14受用) 愛楽仏法味 禅三昧為食
(国土15無諸難) 永離身心悩 受楽常無間
(国土16大義門) 大乗善根界 等無譏嫌名 女人及根欠 二乗種不生
(国土17一切所求満足) 衆生所願楽 一切能満足
故我願生彼 阿弥陀仏国
(仏1座) 無量大宝王 微妙浄花台
(仏2身業) 相好光一尋 色像超群生
(仏3口業) 如来微妙声 梵響聞十方
(仏4心業) 同地水火風 虚空無分別
(仏5衆) 天人不動衆 清浄智海生
(仏6上首) 如須弥山王 勝妙無過者
(仏7主) 天人丈夫衆、恭敬繞瞻仰
(仏8不虚作住持) 観仏本願力 遇無空過者 能令速満足 功徳大宝海
(菩薩1) 安楽国清浄 常転無垢輪 化仏菩薩日 如須弥住持
(菩薩2) 無垢荘厳光 一念及一時 普照諸仏会 利益諸群生
(菩薩3) 雨天楽花衣 妙香等供養 讃諸仏功徳 無有分別心
(菩薩4) 何等世界無 仏法功徳宝 我願皆往生 示仏法如仏
四 天親の一心帰命の信
『解読浄土論註』18頁
世尊、我れ一心に、尽十方
無碍光如来に帰命して、安楽国に生ぜんと願ず。
「世尊」とは諸仏に共通するよび名である。その智慧についていえば、あらゆる道理に通達し、迷いを断つという点では、煩悩の余習さえとどめていない。このように智と断とが完全にそなわって、世の衆生を利益することができ、世の中から尊ばれる。だから世尊というのである。ここで世尊といわれるのは釈迦如来に帰依する意味である。
どうしてそうわかるかというと、下の句に「我れ修多羅に依る」と言われているからである。天親菩薩は釈迦如来の像法の世にあって、釈迦如来の経の教えにしたがえばこそ、往生を願われた。その往生の願いにはもとづくところがあるのである。
だから世尊ということばは、釈迦如来に帰依する意味だとわかるのである。
ところで、この世尊ということばの意味は、ひろく諸仏に告げたと解してもさしつかえない。だいたい菩薩が仏に帰依するのは、あたかも孝子が父母に帰服し、忠臣が主君に帰服するようなものである。たちいふるまいには私がなく、生も死もともにかならずしたがって、恩をわきまえ、徳に報いるのである。だからまず最初に申し上げなければならないのである。〔行p.203〕
また天親菩薩の願われるところは重大である。もし如来が不可思議な威力をお加えにならなかったら、どうしてその願いを達成することができようか。だから今、如来の不可思議の力を加えられんことを願って、世尊と呼びかけたてまつったのである。
「我一心」とは、天親菩薩が自らをはげまされたことばである。これは、無碍光如来を念じて、安楽浄土に生まれたいと願われ、心にたえまなく念じて、雑念が少しもまざらないことをいう。
問う、仏法の中には我はない。ここではどうして我というのか。
答う、我ということばには三つのもとづくものがある。一つには邪見にもとづくことば、二つには自分を誇張することば、三つには普通一般に行われることば、である。今ここで我れといわれたのは、天親菩薩が自分を指していわれたことばであって、普通一般のことばを用いられたのであり、邪見にもとづくことば、自分を誇張することばではない。
像法
正像末の三時の一。像とは映像の意で、釈迦牟尼仏の正法が映像されている時代ということで像法時という。正法時には釈迦の教法とそれを修行する道、及びそれの完成(証果)がともに存するが、像法時には、教行はあるとはいえ、もはやそれを如実に証りうる者がいない。曇鸞は『大集月蔵経』等によって、正法五百年、像法一千年と考え、天親菩薩を像法時の人としたと思われる。
五 礼拝門
『解読浄土論註』23頁
「帰命尽十方無碍光如来」というのは、「帰命」は即ち礼拝門、「尽十方無碍光如来」は即ち讃嘆門である。
なぜ帰命が礼拝であると知れるかといえば、龍樹菩薩が阿弥陀如来を讃嘆する文をお造りになった中で、或いは「稽首礼」といい、或いは「我帰命」といい、或いは「帰命礼」といわれている。この論の長行の中にもまた五念門を修すといわれているが、五念門の中で礼拝が一ばんにある。天親菩薩はすでに往生を願われている。どうして礼拝せずにいられようか。だから帰命は即ち礼拝であると知れるのである。しかし礼拝はただ、うやうやしく拝したてまつることであって、かならずしも帰命ではないが、帰命はかならず礼拝である。もしこれによって帰命をおもえば、礼拝より意味は重い。帰は自らの心を表白するのだからよろしく帰命というべきである。論は偈の意味を解釈するのだから、ひろく礼拝について語っている。偈と論とが互いに呼応して、意義をいよいよ顕わしているのである。
六 讃嘆門
なぜ「尽十方無碍光如来が讃嘆門である」と知れるかといえば、あとの長行にいわれている。「どのようにするのが讃嘆門か、それは彼の阿弥陀如来の名をとなえ、その名が彼の如来の光明のはたらきたる智慧の相であるとうけとり、如来の名の意義のままに、真実にしたがって道をおさめ、如来の心にかないたいと思わしめられるからである。」と。
釈尊が舎衞国でお説きになられた『無量寿経』(阿弥陀経p.128)によれば、
仏自ら阿弥陀如来の名号をお解きになられている。即ち、「どうして阿弥陀と名づけたてまつるのか、それは彼の仏の光明が無量であって、十方の国々を照らすに少しのさわりもない。だから阿弥陀となづけたてまつるのである。」また「彼の仏をはじめ、そのみもとにある人々の寿命は無量であり、永遠である。だから阿弥陀と名づけたてまつるのである。」と。
問う、もし無碍光如来の光明が無量であって、十方の国土を照らしたもうに少しもさわりがないというのなら、この国の衆生はどうしてその光をこうむらないのか。光が照らさないところがあるのなら、どうしてさまたげないといえようか。
答う、さまたげは衆生の側のことである。光にさまたげがあるのではない。譬えば太陽の光は四天下にあまねくふりそそぐが、盲者(無明存在)には見えないようなものである。これは太陽の光がゆきわたらないのではない。またふかくたれこめた雲が大雨をふらせても、かたい石にはしみこまないようなものである。これは雨がうるおさないのではない。
もし一仏が三千大千世界をすべてつつんでいるというならば、これは声聞が論ずる中の説である。もし諸仏があまねく十方無量のほとりなき世界をつつんでいるというなら、これは大乗の論の中の説である。
天親菩薩がいま「尽十方無碍光如来」と言われるのは、とりもなおさず彼の如来の名によって、彼の如来の光明のはたらきたる智慧の相のままに讃嘆するのである。
だから、この句は讃嘆門であると知れるのである。
声聞
仏の教えを聞いて進むものという意味で、仏弟子をあらわすことば。仏の教法、四諦の理を観じて、みずから阿羅漢となることを理想とする仏道修行者をいう。大乗では、縁覚とあわせて二乗という。
七 作願門
『解読浄土論註』28頁
「願生安楽国」とは、この一句は作願門である。天親菩薩の帰命の意である。
安楽の意味はあとの観察門の中にくわしくのべられている。
問う、大乗の経論の中には、処々に衆生はつづまるところ無生(空)であって、虚空のようなものだと説いている。どうして天親菩薩は「願生」といわれるのか。
答う、衆生が無生であって虚空のようだと説くには、二種ある。
一には、凡夫がいわゆる衆生という場合であって、凡夫が実体的にみている生死というようなもの、その見られているものは、つづまるところあることのないもので、ちょうど亀の甲に毛があるとみるようなもので虚空のようだというのである。
二には、諸々の存在は因縁の生であるから、とりもなおさず不生である。それであることがないのは虚空のようだというのである。
天親菩薩が願われる生は、因縁の意味である。因縁の意味だから、仮に生と名づけるのである。凡夫が実際に衆生があり、実際に生死があるというようなものとはちがうのである。
問う、どのような意味で(因縁生の)往生と説くのか。
答う、この国の人々の中にあって、五念門を修するという場合、
前念は後念に対して因となる。この娑婆世界の人間(因)と浄土の人間(果)とは全く同一ではない。しかし全く異なるものでもない。後念門を修する場合の前心と後心もまたこのようである。
どうしてかといえば、もし同一であれば、因果がないことになるし、さればとて異なるなら娑婆の人間と浄土の人間とは相続していないことになるからである。この意味は(『中論』の)一異を観ずる論の中にくわしくのべてある。
第一行の三念門の解釈をおわる。
「世尊我一心」というは、世尊は釈迦如来なり。我ともうすは、世親菩薩のわがみとのたまえるなり。一心というは、教主世尊の御ことのりをふたごころなくうたがいなしとなり。すなわちこれまことの信心なり。
「帰命尽十方無碍光如来」ともうすは、帰命は南無なり。また帰命ともうすは、如来の勅命にしたがうこころなり。尽十方無碍光如来ともうすは、すなわち阿弥陀如来なり。この如来は光明なり。尽十方というは、尽はつくすという、ことごとくという。十方世界をつくして、ことごとくみちたまえるなり。無碍というは、さわることなしとなり。さわることなしともうすは、衆生の煩悩悪業にさえられざるなり。光如来ともうすは、阿弥陀仏なり。この如来はすなわち不可思議光仏ともうす。この如来は智慧のかたちなり。十方微塵刹土にみちたまえるなりとしるべしとなり。
「願生安楽国」というは、世親菩薩かの無碍光仏を称念し、信じて安楽国にうまれんとねがいたまえるなり。
「我依修多羅 真実功徳相」というは、我は天親論主のわれとなのりたまえる御ことばなり。依はよるという、修多羅によるとなり。修多羅は天竺のことば、仏の経典をもうすなり。仏教に大乗あり、また小乗あり。みな修多羅ともうす。いま修多羅ともうすは大乗なり。小乗にはあらず。いまの三部の経典は大乗修多羅なり。この三部大乗によるとなり。真実功徳相というは、真実功徳は誓願の尊号なり。相はかたちということばなり。
「説願偈総持」というは、本願のこころをあらわすことばを偈というなり。総持というは智慧なり。無碍光の智慧を総持ともうすなり。
「与仏教相応」というは、この『浄土論』のこころは、釈尊の教勅、弥陀の誓願にあいかなえりとなり。
「観彼世界相 勝過三界道」というは、かの安楽世界をみそなわすにほとりきわなきこと虚空のごとし。ひろくおおきなること虚空のごとしとたとえたるなり。p.518 尊号真像銘文
八 仏道の歴史への応答
『解読浄土論註』33頁
次に優婆提舎という名を充分なものにし、また上の三門(礼拝門・讃嘆門・作願門)を全うして下(観察門・回向門)の偈を起す。
我修多羅、真実功徳の相に依って
願偈を説いて総持して、仏教と相応す〔行p.167〕。
この一行はどのようにして優婆提舎という名を充分なものにし、どのようにして上の三門を全とうして下の二門を起すのであろうか。
偈に「我修多羅、真実功徳の相に依って」と言われている。
修多羅とは仏の経をよぶことばである。我れは仏の説かれたこの経のいわれを論述して、経といささかの相違もなく、まったく仏法のまことの相と一致しえたから、この論偈を優婆提舎と名づくことができるのである。というのである。これで名を成立させおわった。
どのようにして「上の三門を全とうして、下の二門を起すか」(成上起下)というに、「依る」ということには、
①「何に依るか」、②「なぜ依るか」、③「どのように依るか」、ということがある。
①「何に依るか」といえば、修多羅(『無量寿経』)に依る。
②「なぜ依るか」といえば、如来はとりもなおさず真実功徳の相であるから。
③「どのように依るか」といえば、五念門を修することによって、如来の真実功徳の相に相応することができるからである。
これで上を全とうして下を起すことをおわった。
「修多羅」とは、十二部経の中で仏が直接説かれたものを「修多羅」という。つまり四阿含の三蔵などがこれである。三蔵以外の大乗の諸経もまた「修多羅」と名づける。この偈の中で「修多羅に依る」というのは、三蔵以外の大乗の修多羅であって阿含などの経ではない。
「真実功徳相」とは、功徳に二種ある。
一には煩悩にとらわれた心より生じ、存在の道理にしたがわないもの。
いわゆる凡夫の世界の諸々の善根、それによっておこる結果は、因であれ果であれ、みな本末を顛倒し、みな虚偽である。だからこれを真実でない功徳というのである。〔化本p.338〕
二には、菩薩の智慧による清浄の業にもとづいて、仏の衆生教化の事業を立派に行われた功徳である。これは存在の道理にしたがい、清浄の相にかなっている。この法は顛倒せず、虚偽がない。これを真実の功徳というのである。
どのように顛倒しないかといえば、存在の道理にしたがい、二諦に順じているからである。どうして虚偽がないかといえば、衆生をつつみとって、かならず仏道のきわまりである浄土に入らしめるからである。
「願偈を説いて総持して、仏教と相応す」とは、「持」は散ぜず、失わないことをいう。「総」は少によって多をつつみとることをいう。
「偈」とは五言の句をいくつかつらねた韻文である。
「願」とは往生をこい楽うことをいう。
「説」とは諸々の偈と論とを説くことをいう。
まとめてこれをいえば、往生を願う偈を説くことによって、
仏の経をまとめて身につけ、「仏の教えと相応する」のである。「相応」とは、たとえば函と蓋とがぴったりあうようなものである。〔行p.170〕
九 観察門
①仏国土の荘厳
『解読浄土論註』40頁
1 清浄性(清浄功徳)
彼の世界の相を観ずるに、三界の道に勝過せり。
これより已下は第四の観察門である。この門の中を分けて二つに区別する。
一には、器世間の荘厳の成就を観察する。
二には、衆生世間の荘厳の成就を観察する。
この句より已下「願わくは、かの阿弥陀仏国に生まれん」というまでは、器世間の荘厳の成就を観察するところである。中をまた分けて十七に区別する。その名目は一一の文に至ってつけることにする。
この二句は即ち第一の事がらであって、観察荘厳清浄功徳成就と名づける。この清浄功徳は十七を総じての相である。
仏がもと、この荘厳清浄功徳を起された所以は、三界を見られるに、虚偽にみち、流転し、輪廻は窮ることがない。その相はあたかも、尺とりむしがめぐり歩くようであり、また、かいこがまゆをつくって自らを縛っているようである。ああ何と哀れなことであろうか、衆生はこの三界の顛倒の不浄に束縛されている。その相を見られ、衆生を虚偽なく、流転せず、無窮でない処に安住させ、絶対安楽の大清浄の処を得させようとねがわれたのである。だからこの清浄荘厳功徳を起されたのである。
「成就」とは、(如来の清浄の徳が衆生の場所にはたらくことをいう)この清浄は破壊できず、けがれに染めることができない、三界のようにけがれに染まり、破壊されている相とは全くちがう、ということである。
「観」とは(仏智で)観察(すること)である。
「彼」とは彼の安楽国である。
「世界相」とは彼の安楽世界の清浄の相である。その相については別に下にのべられている。
「勝過三界道」の「道」とは通である。これこれの原因によってこれこれの結果を得、これこれの結果によってこれこれの原因に酬いるというように、原因を通して結果に至り、結果を通して原因に酬いるから「道」と名づけるのである。
「三界」とは、
一には欲界、いわゆる六欲天・四天下の人・畜生・餓鬼・地獄などがこれである。
二には色界、いわゆる初禅・二禅・三禅・四禅の天などがこれである。
三には無色界、いわゆる空処・識所・無所有所・非想非非想処の天などがこれである。
この「三界」は、およそ生死の凡夫の流転きわまりない闇の宅であって、苦楽に多い少ない、寿命に長い短いの差がわずかばかりあるとはいえ、すべてこれを観るに、煩悩のけがれのないものはない。禍いと福とはあい倚りよられ、互いに重なり、いつはてるともなくめぐり、雑然たる生を触受て、四顛倒に長く拘束されている。因も果も虚偽のすがたをくりかえしているのである。
安楽浄土は、菩薩の慈悲の正観より生じ、如来の不思議な力と本願によって建てられたのである。胎生・卵生・湿生などは、これによってはるかに去り、業の繋縛の長い綱はこれによって永久に断たれるのである。衆生を救おうとする続括の方便は、諸仏の勧めをまたずに発され、労を自分の功積にせず、善く人に譲ることは、普賢菩薩とならんでその徳を同じくするのである。
「三界に勝過」してとは、そもそも、われわれの手近かにいわれたことばである。
器世間・衆生世間
器は衆生に受用せられるものの意。故に器世間とは山河・大地・草木など衆生に受用せられる世界。対して衆生世間とは、有情を構成している心身の世界。
二十九種荘厳『真宗新辞典』より
世親の浄土論に説く浄土のうるわしい相。国土・仏・菩薩の三種荘厳に大別され、三厳二十九種ともいう。国土の荘厳に、清浄、量、性、形相、種種事、妙色、触、三種(水・地・虚空)、雨、光明、妙声、主、眷属、受用、無諸難、大義門、一切所求満足功徳の17種、仏の荘厳に、座、身業、口業、心業、大衆、上首、主、不虚作住持功徳の8種、菩薩の荘厳に不動遍至、時遍至、無余供養、遍示三宝功徳の4種がある。
依報の国土荘厳を器世間清浄、正報の仏・菩薩荘厳を衆生世間清浄といい、二種清浄という。
浄土三部経に根拠を求め、摂大乗論釈により種別したといわれる。
曇鸞の論註には、二十九種荘厳の意義について、大悲の願心から起こり、仏威神力の現れとして、観察門の意味を願力仏力の観知信知に求めている。
依報(正報)『真宗新辞典』より
まさしく過去の業のむくいとして得た身を正報、その身が依りどころとする環境を依報といい、合わせて依正二報と称する。報とは自らの業が招いたむくい(果報)。
①器世間と衆生世間。「衆生の依報の処なり、また衆生の所依処と名く」〔序義〕。「此の生死三界等の自他の依正二報」〔散義〕「依正二報滅亡し」〔末讃〕の左訓「ひとのいのちももてるものも」。
②浄土の依正二報。阿弥陀仏とその浄土の荘厳功徳について、依報に17種の国土荘厳功徳、正法に8種の仏荘厳功徳と4種の菩薩荘厳功徳があるとし、これらは、因にかえしていえば弥陀の因位たる法蔵菩薩の願心におさまり、三厳二十九種の広は真如法性たる一法句の略と広略相入すると説く〔論〕。善導は、依報に地下・地上・虚空の三荘厳、正報に主・聖衆の二荘厳を分け、依正それぞれに通別、真仮を分け〔玄義〕、依正二厳ともいう〔定義、散義〕、依報を依果ともいい、「無漏の依果」〔讃偈-浄讃〕の左訓「えほうのくわほう」。「安楽仏土の依正」〔浄讃〕の左訓「えほうは よろづのほうじゅ ほうち よろづのかざりなり、すべてのかざりのななり、しゃうほうは われらがごくらくにまいりなば じんづじざいになるをいうなり」。
荘厳 『真宗新辞典』より
身や国土をおごそかにかざること、身口意の三業をととのえて清浄にすること。阿弥陀仏の浄土は法蔵菩薩の四十八願等の清浄願心により荘厳されたもので、その功徳成就について依報である器世間に17種の国土荘厳。正報である衆生世間に8種の仏荘厳(主荘厳)と4種の菩薩荘厳(伴荘厳)を数える。
功徳 『真宗新辞典』より
修行の功により積まれた徳。世間・出世間。大・小。有漏・無漏。有相・無相。不実・真実などの別がある。
往生の業について、念仏と諸行の功徳の別(大経)、九品の差異(観経)、多善根と少善根の別(小経)をあげる。
弥陀の名号について、「真実功徳ともうすは、名号なり」(p.543 一念多念文意)「広く功徳の宝を施せん」(p.025大経ーp.157行)「阿弥陀仏の不可思議の功徳を讃歎するがごとく」(p.130小経)「真実功徳相というは、真実功徳は誓願の尊号なり」(p.51銘文)「一切の功徳にすぐれたる南無阿弥陀仏をとなうれば」(p.487浄讃)「功徳の宝海みちみちて」(p.490高讃)など、という。
四顛倒
常・楽・我・浄の四顛倒。これに有為の四顛倒と無為の四顛倒とがあるが、いまは有為の四顛倒のこと。無常の世界を常住と思い、苦の世界を楽と執し、無我の法を我と考え、不浄の世界を清浄とみていること。
胎卵湿生
胎生・卵生・湿生のこと。これに化生をくわえて四生という。四生とは、衆生のあり方を生れる状態によって四つに分類したもので、これによって衆生の輪廻転生を説く。胎生とは人や牛馬の如く、母胎内で身体の各部を備えて生れてくるもの。卵生とは鳥類の如く、卵で生れてのち孵化するもの。湿生とはアメーバーの如く、湿気によって(細胞分裂)生れてくるもの。化生とは天上界のごとく、父母の因縁によらず忽然と生れるもの。今、化生をいわないのは、和讃に「正覚の華より化生して」とある如く、化生には真実報土に往生する正覚の化生があるので、それとの混乱をさけるため略したものとも考えられるが、胎卵湿生とあるなかには、忽然と生ずる化生も含まれている。
『解読浄土論註』46頁
2 無量性(量功徳)
究竟して虚空のごとく、広大にして辺際なし。
この二句は荘厳量功徳成就と名づける。
仏がもと、この荘厳量功徳を起された所以は、三界を見られるに、狭く小さく、土地のくぼんだところや裂けたようなところがあるかと思えば、少しばかり盛り上がったところやふくれたようなところがある。或いは宮殿の髙どのは迫くきゅうくつであり、土地田畠はせまってせまくるしい。また、どこかへ行こうとしても路はせまく、或いは山や河が行く手をはばみさえぎり、或いは国境にへだてられて行くことができない。このように、さまざまのせわしく急なことがある。
だから菩薩はこの荘厳量功徳の願いを興され、我が国土は虚空の如く広大で辺際がないようにと願われたのである。
「虚空の如し」とは、この国に来生する者の数がいかに衆くても、なお無いにひとしいようだという意味である。
「広大にして辺際なし」とは、上の虚空の如しという意味を全とうするものである。つまり、どうして虚空のようかといえば、広大で際限がないからである。
量功徳の成就とは、十方衆生の中の往生する者━すでに往生したもの、今往生するもの、これから往生すべきもの━は量りなく、はてしなくあっても、つづまるところ常に虚空のように広大で際限なく、終に満ちてしまうときがないということである。
だから「究竟して虚空の如く、広大にして辺際なし」というのである。
問う。維摩居士などは、小さな部屋に、高さ八万四千由旬の師子座を三万二千つつみ入れて、なお余りがあるという。どうして国の界のはかりないところにかぎって広大と称するのか。
答う。ここにいう広大は、かならずしも五十畝を畦といい、三十畝を畹というような場所の広さを喩にしているのではない。ただ空のようだというのである。そのうえにどうして部屋の広さなどのたとえにかかずらう必要があろうか。
また維摩の部屋がつつみいれるのは、狭いところにあって広いのである。厳密に結果の優劣を論ずれば、どうして広いところにあって広いというのに及ぼうか。
『解読浄土論註』52頁
3 大慈悲(性功徳)
正道の大慈悲は、出世の善根より生ず。
この二句は、荘厳性功徳成就と名づける。〔真p.314〕
仏はもと(因位の菩薩のとき)、どうしてこの(浄土の性(大慈悲)の)荘厳を起したもうたかといえば、ある国土を見られるに、愛欲によっての故に欲界があり、禅定を修して高上しようとして欲界に厭うことによって色界・無色界がある。この三界はすべて煩悩にとらわれており、邪な道によって生じたものである。人々は大きな迷いの夢の中にぐっすり寝こんでいて、覚めることがあろうなどとはまったく知らないのである。
だから仏は大悲の心を興したもうて、私が仏と成るには、この上ない正見の道をもって、清浄な国土を起し、人々をこの三界から出させようと願われたのである。
「性」とは「本」という意味である。つまり、この浄土は法性にしたがい、法の根本(不生の理)にそむかないものであるということである。このことは、『華厳経』の宝王如来性起品に説かれている如来の性起の意義と同じである。
「性」は「積習成性」、(行を)積み習って性を成ずるのである。これは法蔵菩薩を指している。法蔵菩薩は、諸々の波羅蜜を集め、それを積み習い練って、この浄土を成じたもうたのである。
また、「性」とは「聖種性」のことである。はじめ法蔵菩薩は、世自在王仏のみもとにあって、無生法忍をさとられたが、この時の位を聖種性と名づける。法蔵菩薩は、この性の位のうちにあって、四十八願を発し、この土を修起せられた。即ちこれを安楽浄土というのである。この浄土は、彼の聖種性における発願によって得られた結果の中に、その原因を説くから、「性」と名づけるのである。
また、「性」とは「必然」の意味であり、不改の意味である。たとえば、海の性は一味であって、いろいろな流れが入ってくれば、必ず一味となり(必然)、海の味はそれらによって改わることがない(不改)。また人の身の性は不浄であるから、
いろいろの素晴らしい色や香り、美味ものでも、身体に入ればすべて不浄となるようなものである。安楽浄土は諸々の往生する者に、不浄の身もなく、不浄の心もない。つまるところすべて清浄で平等な無為法身を得るのである。それは安楽国土の性がまっとうされているからである。
「正道の大慈悲、出世の善根より生ず」とは平等の大道である。もとより平等の道であるからこういうのである。正道と名づけられるわけは、平等とは諸法の根本の相であって、諸法が平等であるから、法蔵菩薩の発せられた願心は平等である。発せられた願心が平等であるから、修行の道は平等である。道が平等であるから大慈悲である。大慈悲こそは仏道の正因である。(だから平等の道を正道というのである。)
さらに「正道の大慈悲」というのは、慈悲にはそれを起すのに三種の縁がある。
一には、衆生を縁として起す慈悲。これは小悲である。
二には、法を縁として起す慈悲。これは中悲である。
三には、縁なくして起す慈悲、これが大悲である。
大悲は即ち出世の善である。安楽浄土は、この大悲より生ずる。だからこの大悲をもって浄土の根本とするのである。
だから、「出世の善根より生ずる」というのである。〔真p.314-315〕
『解読浄土論註』56頁
4 形相(形相功徳)
浄光明満足すること、鏡と日月輪とのごとし。
この二句は荘厳形相功徳成就と名づける。
仏がもと、この荘厳形相功徳を起したもうた所以は、日が四域に行きわたるのを見るに、一方に光がそそぐときは、他の三方に光がとどかない。また宅内にあって庭で大きな火をたいて明りをとっても十仭にも満たない。
このようなわけだから、清浄な光明を満足しょうとの願いを起したもうたのである。日や月の光が、それ自体において満足しているように、彼の安楽浄土は、広大で辺がないとはいえ、清浄の光明が充満して、いたらぬところとてない。
だから「浄光明満足すること、鏡と日月輪とのごとし」というのである。
『解読浄土論註』59頁
5 種々事物(種々事功徳)
もろもろの珍宝の性を備えて、妙荘厳を具足せり。
この二句は荘厳種々事功徳成就と名づける。
仏はもと、どうしてこの荘厳を起したもうたかといえば、ある国土を見られるに、泥や土で宮殿を飾り、
木や石で華麗な楼閣をつくっている。或いは金を彫り、玉をちりばめてあるが、思うように願いを満たすことができない。或いは造営のため、あらゆるものを完備しようとすれば、さまざまの辛苦を受けるのである。
このようなわけだから、大悲の心を興したもうて、私が仏と成るには、必ず珍らしい宝物が充分にそなわり、荘厳華麗、しかも自然であって、宝の充分すぎるという満足の心も忘れて、それがおのずから仏道を成就する満足とならしめたい、と願われたのである。
この荘厳のさまは、たとい毗首羯磨が細工に妙絶であると言っても、彼がどれほど思案を積み、想いをつくしても、どうしてよく、それを、うつしとることができようか。
「性」とはさきにのべたように根本という意味である。根本たる願心がすでに清浄である以上、それから生まれた荘厳が、どうして清浄でないことがあろうか。だから『経』(維摩経卷上)に言っている。「その心が浄らかであれば、仏土は浄らかである、」と。
だから「もろもろの珍宝の性を備えて、妙荘厳を具足せり」というのである。
『解読浄土論註』62頁
6 妙なる色(妙色功徳)
無垢の光炎熾にして、明浄にして世間を曜かす。
この二句は、荘厳妙色功徳成就と名づける。
仏はもと、どうしてこの荘厳を起したもうたかといえば、ある国土を見られるに、優れたところとか劣ったところとかがあって同じでない。同じでないから尊いとか賤しいとかという形ができる。尊い賤しいという形ができれば、是非を争うことになる。是非の争いが起きれば、いつまでも三界にしずむことになる。
だから大悲の心を興して、平等であらしめたいという願いを起されたのである。願わくば、私の起す国土は光明が炎のように盛んであり、すべての中の第一であり、比べるものもなく、人天の所有する金色は、それよりもすぐれたものにあえば、光を奪われてしまうが、そのような光ではないように、と
相い奪うとは、どういうことかといえば、よくうつる鏡も金のそばにおけば光を現じない。今の時代の金を仏在世の時の金と比べれば、今の時代の金は光を現じない。仏在世の時の金も閻浮那の金と比べれば光を現じない。その閻浮那の金も大海の中の転輪王の道中の金沙と比べれば光を現じない。その転輪王の道中の金沙も金山と比べれば光を現じない。その金山も須弥山の金と比べれば光を現じない。その須弥山の金も三十三天の瓔珞の金と比べれば光を現じない。その三十三天の瓔珞の金も炎摩天の金と比べれば光を現じない。その炎摩天の金も兜率陀天の金と比べれば光を現じない。その兜率陀天の金も化自在天の金と比べれば光を現じない。その化自在天の金も他化自在天の金と比べれば光を現じない。
その他化自在天の金も安楽国の中の光明と比べれば光を現じなくなるのである。
どうしてかといえば、彼の安楽国土の金光は、垢れた業より生ずることが全くたえはてているから、清浄なる輝きが成就しないところがないのである。もともと安楽浄土は、無生忍をさとられた法蔵菩薩の清浄な業によって起されたものであって、阿弥陀如来法王が統ておられるところである。このように阿弥陀如来を増上縁とするので、「無垢の光炎熾にして、明浄にして世間を曜かす」といわれるのである。
「世間を曜かす」とは、器世間(環境)・衆生世間(人の生きるところ)の二種世間を曜かすのである。
妙色功徳
先の形相功徳では、浄土の体そのものが光明を満足していることを明かしているが、この妙色功徳では浄土の色相が光明であることを明かす。この場合の色とは、われわれの観念では物質という概念に近いが、浄土の色はそのような観念を超え、無比であるから妙色功徳といわれる。
『解読浄土論註』67頁
7 柔軟さ(触功徳)
宝性功德の草、柔軟にして左右に旋れり、触るるもの勝楽を生ずること、迦旃隣陀に過ぎたり。
この四句は荘厳触功徳と名づける。
仏はもと、なぜこの荘厳を起したもうたかといえば、ある国土を見られるに、金や玉を宝として重んじているが、それを衣服とすることはできない。よくうつる鏡を珍らしがって翫んでいるが、それを敷具にあてがうことはできない。つまりこれらによって目を悦ばせることはできても、身を便利にすることはできないのである。このようであっては、身と眼の二つのはたらきは、どうして矛盾しないことがあろうか。
だから願うて言われるには、我が国土の人天の六根は水と乳のように和合し楚と越のようなわずらわしさをすっかりなくしよう、と。だから七宝は柔軟であって、目を悦ばせ身を便利にするのである。
「迦旃隣陀」とは、インドの柔軟な草の名である。これに触れる者は楽しみを生ずることができる。だから喩としたのである。
註者(曇鸞)がいう、この世の土・石・草・木は、それぞれ定まった体がある。訳者は何の理由で浄土の宝を草にたとえたのか、おそらく、草が風をうけるさまが、ひるがえり、めぐっているものだから、草を宝にあてはめただけのことであろう。私がもし翻訳に参加していたなら別の方途があったであろう。
「勝楽を生ずる」とは、迦旃隣陀に触れば、煩悩の執着をます喜楽を生ずる。彼の浄土の柔軟な宝に触れば、法を喜ぶ楽を生ずる。二つの事はとおく、へだたっている。勝れていなくてどうしようか。
だから「宝性功德の草、柔軟にして左右に旋れり、触るるもの勝楽を生ずること、迦旃隣陀に過ぎたり」と言うのである。
『解読浄土論註』72頁
8 水・地・虚空(三種功徳)
8-①水(水功徳)
宝華千万種にして、池・流・泉に弥覆せり。
微風、華葉を動かすに、交錯して光乱転す。
この四句は荘厳水功徳成就と名づける。
仏はもと、どうしてこの願いをおこされたかといえば、ある国土を見られるに、川や海の水が大波をたて、にごり泡だって人々を驚かせたり、流水が迫り来って人々をとじこめおびやかしたりする。このような事態に向うと、安らかな悦びの心もなくなり、あとからふりかえってみると、恐怖の思いをいだくのである。
菩薩はこれを見られて大悲の心を興され、私が仏と成るにはあらゆる水の流れや池や沼は宮殿にふさわしくととのい、[このことは経(大経)の中に出ている]種々の宝花がしきつめられて水面を飾り、そよ風がその上をやわらかく吹き、光がきらきら輝きあうこと秩序正しく、見るものの心をはればれとさせ、身体をよろこばせて、何一つ意にそわないことの無いようにしよう、と願われたのである。
だから「宝華千万種にして、池・流・泉に弥覆せり。微風、華葉を動かすに、交錯して光乱転す」と言われるのである。
『解読浄土論註』74頁
8-②地(地功徳)
宮殿・もろもろの楼閣にして、十方を観ること無碍なり。
雑樹に異の光色あり、宝蘭遍く囲繞せり。
この四句は荘厳地功徳成就と名づける。
仏はもと、どうしてこの荘厳を起したもうたかというと、ある国土を見られるに、けわしくそびえたつ山々があり、その嶺には枯木が横たわり、形のととのわない山々が底無しの谷をいだいて連なり、雑草が谷一杯におい繁っている。はてしない大海原は見わたす限りつづき、雑草がむなしく風になびく広い沢は、誰一人足をふみいれたことがない。
菩薩はこれを見られて大悲の願いをおこされ、我が国土は土地が平らなこと掌のように、宮殿の楼閣にあってみれば鏡のように十方がおさまって、まさに属くところなく、また属かないというのでもなく、宝の樹々とそれらをとりまく宝の蘭とは、互いにてらしあうように、と願われたのである。
だから「宮殿・もろもろの楼閣にして、十方を観ること無碍なり。雑樹に異の光色あり、宝蘭遍く囲繞せり」と言われるのである。
『解読浄土論註』77頁
8-③虚空(虚空功徳)
無量の宝交絡して、羅網虚空に遍ぜん。
種種の鈴、響を発して、妙法の音を宣べ吐かん。
この四句は荘厳虚空功徳成就と名づける。
仏はもと、どうしてこの荘厳を起されたかというと、ある国土を見られるに、煤煙やちりが大空をおおいかくし、雷が稲光とともに大雨をふらせ、不吉な天火や虹がことごとに空からやってきて心配がかさなり、ために身の毛もよだつ思いがするのである。
菩薩はこれを見られて大悲の心を興され、我が国土には宝でおりなした羅網が大空一杯にひろがり、その羅網につけられた大きな鈴が五音の旋律をかなでて、仏道の法音を説き、これを見てあきることなく、仏道のことを懐い、その徳が身にそなわるように、と願われたのである。
だから「無量の宝交絡して、羅網虚空に遍ぜん。種種の鈴、響を発して、妙法の音を宣べ吐かん」と言われるのである。
『解読浄土論註』80頁
9 花衣を雨らす(雨功徳)
花衣の荘厳を雨り、無量の香普く薫ぜん。
この二句は荘厳雨功徳成就と名づける。
仏はもと、どうしてこの荘厳を起されたかというと、ある国土を見られるに、衣服を地にしいて尊敬する人をまねこうとしたり、香り高い花や名宝によって恭いの心を表そうとしたりするが、善業がとぼしく果報がまずしいので、このことを成しとげることができない。
だから大悲の願いを興され、我が国土には、つねにこれらの物(衣服や花や名宝)が雨ふって、人々の意を満足させよう、と願われたのである。
なぜ雨ということばで表現するかといえば、恐らく文にとらわれる者は云うであろう。もしつねに花や衣がふってくるなら、大空はそれらのもので満ちふさがれてしまうはずなのに、どうしてさしつかえがないのか、と。だからこそ雨ということばによってたとえるのである。雨は時に適いさえすれば大水の心配はない。安楽国土の果報に、どうしてそのように心をわずらわすものがあろうか。
『経』(大経と小経)にいわれている。「日夜六たび宝衣が雨ふり、宝花が雨ふる。その宝の質は柔軟で、その上を踏めば四寸ばかりさがり、足をあげるにしたがってまたもとにもどる。用がすめば、あたかも水が穴の中に流れ入るように、地中に入っていく。」と
だから「花衣の荘厳を雨り、無量の香普く薫ぜん」と言われるのである。
『解読浄土論註』82頁
10 光明(光明功徳)
仏恵明浄なること日のごとくにて、世の痴闇冥を除く。
この二句は荘厳光明功徳成就となづける。
仏はもと、どうしてこの荘厳を起されたかというと、ある国土を見られるに、人々の項背には円光があるのだが、無知の愚かさのために闇まされている。
だから願って、我が国土のあらゆる光明は、よく愚痴の闇を除いて、仏の智慧に入らしめ、無利益におわることのないように、と言われたのである。
また安楽国土の光明は如来の智慧より生ずるのだから、世間の闇冥を除くことができる、とも云われている。
『経』(維摩経)に言われている。「或は仏土があって光明によって衆生利益の事業をなす」と。即ちこれがそうである。
だから「仏恵明浄なること日のごとくにて、世の痴闇冥を除く」と言われるのである
『解読浄土論註』85頁
11 妙なる声(妙声功徳)
梵声の悟深遠にして、微妙なり、十方に聞こゆ。
この二句は荘厳妙声功徳成就となづける。
仏はもとどうしてこの願いをおこされたかというと、ある国土を見られるに、善い法があっても、その名高は遠くまでとどかない。名声があって遠くにとどいたとしてもまた微妙でない。名声があり、微妙でしかも遠くに及んだとしても、衆生を悟らせることができない。
だからこの荘厳をおこされたのである。
インドでは浄らかな行を「梵行」といい、妙なる辞を「梵言」という。かの国では梵天を貴び尊重するから、たびたび「梵」ということばを讃めことばとするのである。またインドの法は梵天と通じているからであるともいわれる。
声とは名ということである。名とは安楽浄土の名をいう。
『経』(大経)に言われている。「もし人が安楽浄土の名を聞いて往生したいと願いさえすれば、願いとおりになる」と。これは名が衆生をさとらせるということの証である。
『釈論』(智度論)に言われている。「このような浄土は三界につつみいれられるものではない。どうしてそう言えるかといえば、浄土は欲がないから欲界でない。地に居住するから色界でない。色があるから無色界でない。およそ浄土は菩薩独自の業によって建立されたものにほかならない。」と。
有を超えて、しかも有のままにあるのを「微」という。名がよく悟りを開かしめることを「妙」という。だから「梵声の悟深遠にして、微妙なり、十方に聞こゆ」と言われるのである。
『解読浄土論註』88頁
12 主なる力(主功徳)
正覚の阿弥陀法王、善く住持したまえり。
この二句は荘厳主功徳成就と名づける。
仏はもと、どうしてこの願いをおこされたかというと、ある国土を見られるに、鬼が君主となっている。だからその所領では互いに相手をとってくうありさまである。ところが転輪王の宝輪が宮殿にとどまれば、四域みな心配がなくなる。これをたとえて風になびくというのである。だから国はその主にもとづくのである。
だから願いをおこされ、我が国土にはとこしえに法王がましまして、法王の善根の力によっておさめたもたれるように、と願われたのである。
「住持」とは、たとえば(黄鵠という名の)鶴が(生命をすてて、恩人のすでに死した)子安のことを念じつづけていたら、千年の命をえてよみがえったといい、魚の母が子(卵)のことを念じつづければ、冬の水枯れの時期を経ても死なないというようなものである。安楽国は正覚によって善くその国をたもっている。どうして正覚をあらわさない事が存在しようか。
だから「正覚の阿弥陀法王、善く住持したまえり。」と言うのである。
『解読浄土論註』90頁
13 仏の仲間(眷属功徳)
如来浄華の衆は、正覚の花より化生す。
この二句は荘厳眷属功徳成就と名づける。
仏はもと、どうしてこの願いをおこされたかというと、ある国土を見られるに、血ぬれた胎内を身の器とし、糞や尿を生きる元とし、或いは三公九卿といった高い家柄でも、人をうらやみ、ねたむ生活をする子がでたり、下働きの女性から卓越した才をもった子が生まれたりする。これがために譏られて火を懐く思いをし、恥辱されて氷をいだく思いをするのである。
だから願って、我が国土ではすべてのひとびとが如来の浄らかな花の中より生まれ、眷属すべてが平等であって、差別するてずるのないようにしたい、と言われたのである。
だから「如来浄華の衆は、正覚の花より化生す。」といわれるのである。
『解読浄土論註』93頁
14 仏法の受用(受用功徳)
仏法の味を愛楽し、禅三昧を食とす。
この二句は荘厳受用功徳成就と名づける。
仏はもと、どうしてこの願いをおこされたかというと、ある国土を見られるに、鳥の巣を探して卵を破り食の膳としたり、砂袋を壁にかけ、それを指してうえを慰す方法としたりしている。ああ諸子よ、実に心痛むではないか。
だから大悲の願いをおこされ、我が国土は仏法を、三昧を食とし、永久に他の食物のわずらいを絶つように、と願われたのである。
「仏法の味を愛楽し」とは、たとえば日月灯明仏が『法華経』を説かれたとき六十小劫かかった。そのとき集った聴衆もまた一つの処に六十小劫坐ったままだったが、あたかも食事の時間のように思え、一人として身や心に倦怠を生ずることがなかった、というようなものである。
「禅定を以て食と為す」とは、諸々の大菩薩はつねに三昧にあって他の食が不要である、というのである。
「三昧」とは、かの浄土の諸々の人天が食事をしようとするときには、百味にのぼるおいしい料理がずらりと前にならぶが、眼でそれらの色を見、鼻で香をかいで、身にこころよいよろこびを受けて自然に満足する。それがおわれば消え去る。もしまた食事の必要があれば、再び現れる、ということである。この事は経(大経)にのべられている。
だから「仏法の味を愛楽し、禅三昧を食とす」と言われるのである。
『解読浄土論註』96頁
15 苦難を超える道(無諸難功徳)
永く身心の悩みを離れて、楽を受くること常に間なし。
この二句は荘厳無諸難功徳成就と名づける。
仏はもと、どうしてこの願いを起されたかというと、ある国土を見られるに、朝には天子の恩寵をこうむってよろこんだ者が、夕には重罪の刑におののき、或は幼いとき草の中へ捨てられていたものが、長じては一丈四方の料理を食卓に並べるという富者ぶりであったり、あしぶえを鳴らし勇んで門出したものが、各地をへめぐって、やむなく、もどってこなければならなかったりする。このように種々の、ちぐはぐなことがある。
だから願って、わが国土では安楽がいつまでも続いて全くとだえることがないように、と言われたのである。
「身の悩み」とは飢渇・寒さ熱さ・殺害にあうことなどである。
「心の悩み」とは是非のあらそい・得失・三毒(貪ぼり・いかり・無知)などである。
だから「永く身心の悩みを離れて、楽を受くること常に間なし」と言われるのである。
『解読浄土論註』99頁
16 平等の道(大義門功徳)
大乗善根の界、等しくして譏嫌の名なし、女人および根欠、二乗の種、生ぜず。
この四句は荘厳大義門功徳成就と名づける。
門とは大義の門に通ずるということである。大義とは大乗の所以のことである。たとえば人が城を造った場合、門が完成すれば中へ入ることができるように、もし人が安楽国に生まれることができれば、それが大乗の門を完成したことになるのである。
仏はもと、どうしてこの願いをおこされたかというと。
ある国土を見られるに、仏如来・賢者・聖者などの衆がおられても、国が濁っているから、一乗を三乗(声聞・縁覚・菩薩)として説かれている。また色目をつかうことによってとがめられるような事態がおこったり、指で語することによって、そしりをまねいたりしている。
だから願って、我が国土はことごとく大乗一味、平等一味であらしめたい、また芽を出す力のない種子(二乗)は一粒だにも生ぜしめず、女人とか残欠とかいう名字さえまったく絶やしてしまおう。と言われたのである。
だから「大乗善根の界、等しくして譏嫌の名なし、女人および根欠、二乗の種、生ぜず。」と言われるのである。
『解読浄土論註』103頁
問い。王舎城で説かれた『無量寿経』(大経)をひもとくに、法蔵菩薩の四十八願の中にいわれている。「たとい私が仏となっても、国の中の声聞にかぎりがあって、その数を知るようであれば、正覚ことをしまい」(第十四願、声聞無数の願)と。これは安楽国に声聞が存在する第一の証である。
また『十住毘婆沙論』の中で、龍樹菩薩は阿弥陀仏を讃える偈を造って云われている。「三界の牢獄を超え出て、目が蓮の花びらのような声聞の人々はかぎりなくおられる。だから、うやまって礼拝する」と。これは声聞が存在する第二の証である。
また『摩訶衍論』(智度論)にいわれている。「仏土は種々あって同じでない。ある仏土はもっぱら声聞僧だけがおり、ある仏土はもっぱら菩薩僧ばかりである。またある仏土は菩薩と声聞とがあつまって僧を形成している。たとえば阿弥陀仏の安楽国などがこれである。」と。これは声聞が存在する第三の証である。
いろいろな経典で安楽国について説かれている箇所には、多くの場合、声聞が存在すると言って、声聞が存在しないとは言っていない。声聞は即ち二乗の一つである。ところが『浄土論』では「二乗の名さえない」と言われている。これはどのように理解したらいいのか。
答え。理を推せば、安楽浄土には二乗が存在するはずがない。どうしてこう言うかといえば、大体病があればこそ薬があるというのが道理というものだからである。
『法華経』に言われている。「釈迦牟尼如来は五濁の世に出られたからこそ、一乗を三乗に分けて説かれたのである」(方便品)と。浄土はすでに五濁でないのだから、三乗がないことは明らかである。
さらに『法華経』に言われている。「声聞の人々はどういう点で解脱を得ているか。ただ虚妄を離脱した点で解脱というのである。この人は本当はまだすべてのものからの解脱を得ていない。この上ない道に達していないからである。」(譬喩品)と。当然この理をおせば、声聞のさとりたる阿羅漢は、まだすべてのものからの解脱を得ていないのだから、
必ず生れるということがあるはずである。しかしこの人は再び三界に生まれることはない。三界の外に浄土を除いて再び生まれる処はない。だからひとえに浄土に生れるしかないのである。
声聞と先ほどから言っているのは、他方の世界の声聞が浄土に来り生れるのを、もとの名によるから声聞とよんでいるのである。たとえば帝釈天は、むかし人間の世界に生れたとき、姓を憍尸迦といったが、後に天上の主となっても、仏は人々にその由来を知らせようと欲われ、帝釈天と語りあわれるときは、もとのまま憍尸迦とよばれたようなものである。いまもこの類である。
またこの『浄土論』には、ただ「二乗の種は生じない」とだけいわれている。つまり安楽国には二乗の種子は芽をださないというのである。どうして二乗が来り生れることまで、こばむことがあろうか。
たとえば橘の樹は江北には生じないが、(その江北の地たる)河南の洛陽のくだもの店には、橘があるというようなものである。また、鸚鵡は壟西より(東へは)渡らないが、趙や魏の国の鳥かごのとまり木には鸚鵡がいるという。この二つのもの(橘と鸚鵡)は、ただその種がむこうに渡らないというのである。声聞が存在するというのも、このようなものである。
このように理解すれば、経と論とは一致するのである。
『解読浄土論註』109頁
問い。名は事物をよぶものである。事物があれば、すなわち名がある。安楽国にはもはや二乗・女人・根欠などのものが存在しないのに、またどうしてことさらこの三つの名がないというのか。
答え。意志の弱い菩薩は、少しも勇猛でないから、これを譏って声聞とよぶようなものである。たとえば、こびへつらったり弱々しい男を譏ってよぶ名。また耳は聴えるが、義を聴いても理解しない者を譏ってよぶ名。また舌はものをいえるが、どもったりまだるこかったりする者を譏ってよぶ名である。このように器官がそろって満足していても、譏り嫌う名がある。
だから「譏嫌の名なし」という必要があることは明らかである。浄土にはこのように与奪の名はないのである。
問い。法蔵菩薩の本願(第十四願、声聞無数の願)、及び龍樹菩薩の(『十住毘婆沙論』の阿弥陀の本願を)讃えられたところをたずねると、皆かの安楽国に声聞の人々が多いことをもって奇特なこととしているようであるが、これはどのような義があるのか。
答え。声聞は実際に身を滅して涅槃に入ることを証としている。このことを考えると、声聞はそれ以上、仏道の根本たる求道の芽を生ずることはできないはずである。にもかかわらず仏は本願の不可思議な神力をもって声聞をつつみいれ、かの安楽国に生ぜしめ、そのうえにまた神力によってかならず無上の求道心を生ぜしめるのである。
たとえば鴆鳥が水の中に入ると、魚や、はまぐりなどがみんな死んでしまうが、犀のつのが、これに触れると死んだものがみな活きかえる、というようなものである。
このように生ずるはずがないのに生ずるから奇特なのである。
だから五つの不思議の中で、仏法は最も不可思議である。仏は声聞にふたたび無上の求道心を生ぜしめる。まことに不可思議のきわみである。〔真p.315〕
『解読浄土論註』112頁
17 願いを満たす(一切所求満足功徳)
衆生の願楽するところ、一切よく満足す。
この二句は荘厳一切所求満足功徳成就と名づける。
仏はもと、どうしてこの願いをおこされたかというと、ある国土を見られるに、名が知れわたり、位が重いので、どこかにかくれようにも、かくれるところがない。或いは平凡で出身がいやしいので、出世をねがってもその路がない。或いは命の長短は業の束縛によって制せられて意のままにならない。たとえば阿私陀仙人のような類である。このように業の風に吹かれてさまよい、ままにならないことがある。
だから願って、我が国土では各々が求めるままに心の願いを満足せしめよう、と言われたのである。
だから「衆生の願楽するところ、一切よく満足す。」と言われるのである。
結び
かるがゆえに我、願わくは、かの阿弥陀仏国に生まれん。
この二句は以上の十七種の国土を荘厳することの完成を観察するところを結び成立させるものである。「願わくは、かの阿弥陀仏国に生まれん。」と言われているからである。
器世間の清浄なることを観察することは以上で終わった。
②仏の荘厳
『解読浄土論註』116頁
つぎに衆生世間の荘厳が清浄にまっとうしたさまを観察する。この門のなかを二つにわける。
一には、阿弥陀如来の荘厳の功徳を観察する。
二には、かの国の諸々の菩薩の荘厳の功徳を観察する。
如来の荘厳の功徳を観察するところは八種をかぞえるが、その名は文に至って見ることにする。
問い。ある論師たちは、一般に衆生という名の意味を解釈するに、三界をめぐりめぐって衆多の生死をうけるから衆生と名づける、といっている。とすれば、いま仏と菩薩を衆生というのはどのようなわけであるか。
答え。『経』(涅槃経)に言う。「一つの法には無数の名があり、一つの名には無数の意味がある」と。衆多の生死をうけるから衆生と名づける、
というのは小乗の教えを伝える人たちが、三界の中の衆生という名の意味を解釈したもので、大乗の教えをうけ継いでいる人たちがいう衆生の意味ではない。大乗の人たちがいう衆生とは『不増不減経』に「衆生というのは、生ぜず滅せずという意味である」といわれているようなものである。
どうしてそう言えるかといえば、もし生ずるということがあれば、生じおわってまた生ずることになって、いつまでも無限にくりかえすという矛盾がおこるからであり、そうすれば生ぜずして生ずるという矛盾があるからである。だから生ということはないのである。もし生があれば滅がある。すでに生がない以上、どうして滅がありえようか。だから生ずることなく滅することなし、ということが衆生の根本義である。
たとえば『経』(維摩経)に、「五蘊(色・受・想・行・識)は空であって固定して存在するものはないと通達すれば、そのままが苦の衆生の根本義である」といわれているのはこの類である。
『解読浄土論註』120頁
1 蓮華の王の座(座功徳)
無量大宝王、微妙の浄花台にいます。
この二句は荘厳座功徳成就と名づける。
仏はもと、なぜこの座を荘厳されたかというと、ある菩薩を見られるのに、まよいの身を解脱する最後のとき、草を敷いて坐り、無上のさとりを成ぜられたが、人天はこれを見ることによって、仏をいよいよ尊くあおぐ信、いよいよ深くうやまう心、ますます法を愛楽する気持、さらに一そう修行にはげむ心を、かならずしもおこさなかった。
だから私が仏となるときには、無量の大宝王たる微妙の浄花の台をもって仏座としようと、とくに願われたのである。
「無量」という意義は、『観無量寿経』(第七華座観)に説かれている如くである。「七宝の地上に蓮花の大王ともいうべき大宝座がある。その蓮花の一一の花べんには百宝の色をあやなし、そのなかに八万四千の脈があって、あたかも自然の(妙をきわめた)絵とかわらない。一一の脈には八万四千の光があり、小さな花べんでもさしわたし二百五十由旬ある。このような花べんが八万四千まい、かさなっており、その一一の花べんの間に百億のもっともすぐれたマニ珠がちりばめられて、たがいに、きらめき、よそおいあっている。一一のマニ珠は千の光明を放ち、その光はおのずから七宝をかたちづくる、きぬがさとなって地上をあまねくおおっている。またその台は釈迦ビリョウガ宝でかざられ、この蓮花の台は八万の金剛石・ケンシュクガ宝・浄マニ宝珠・妙真珠の網などでかざられている。その台の上には、自然に四つの宝幢が立ち、一一の法幢はあたかも八万四千億の須弥山のように威容をきわめている。
幢の上に、はりまわされた宝の幔幕は夜摩天宮のように、五百億の微妙なる宝珠がちりばめられて、きらめきあっている。その一一の宝珠には八万四千の光があり、一一の光は八万四千種のくさぐさの金色をなし、その一一の金色の光が安楽国の宝土をあまねくおおって、いたるところに変化していろいろふしぎな相をあらわしている。あるいは金剛石の台となり、あるいは真珠の網となり、いろとりどりの花の雲となり、十方にわたって意のままに変現し、仏の教化、衆生の利益をめぐらしているのである」と。
このようなことがらは数量という考えを、こえたものである。
だから「無量大宝王、微妙の浄花台にいます。」とのたまわれたのである。
『解読浄土論註』127頁
2 身業の徳(身業功徳)
相好の光一尋なり、色像、群生に超えたまえり。
この二句は荘厳身業功徳成就と名づける。
仏はもと、なぜこのような身業を荘厳されたかというと、ある仏の身を見られるのに、一丈の光明をはなっているだけで、人身の光とあまりかけはなれていないのである。たとえば転輪王の相好のようなもので、かの提婆達多はそれにくらべてわずかに劣るだけで、一見したところは大体かわりがない。ただ一つの相好が少ないだけである。そのため阿闍世王はあやまって争乱の心を懐いたのである。サンジャヤらの外道が、かまきりのような小さなうでを釈尊にくわえたのもこのようなたぐいである。
だからこのような身業を荘厳せられたのである。
中国の古くからの教えによれば、六尺を一尋という。『観無量寿経p.105』(真身観)では「阿弥陀如来の身の高さは六十万億那由他恒河沙由旬である。仏の円光は百億の三千大千世界のようである」といわれている。翻訳者が一尋ということで仏の相好の光をあらわしているのはどうもしっくり合っているとはいえないようである。
数もかぞえられぬ里人たちは、縦横・長短をはっきりさせえず、みな一様に横に両手のひじをのばした長さを一尋といっている。翻訳者はこの(素朴な人々をすくう妙なるみ教えの)意味をもって阿弥陀如来がせい一ぱいに、のばされた両ひじの大きさとして、あらわしたものとおもわれる。だから一尋といえば(如来の両手をのばされた長さであり、それは大体身の高さと同じであるから)円光もまた直径六十万億那由他恒河沙由旬であるはずである。
だから「相好の光一尋なり、色像、群生に超えたまえり」とのたまわれたのである。
問い。『観無量寿経p.130』にいわれている。「諸仏如来は法界身である。(だから)すべての衆生の心の想いのなかに入る。だから汝らが心に仏を想うとき、この心がそのまま三十二相八十随形好である。
この心が仏となるのであり、この心がそのまま仏である。諸仏正遍知海は衆生の心想より生ずる」と。この意味はどのようなものであるか。
答え。身は集めて成立する意味に名づける。界は事物の別々の相に名づける。たとえば、眼界が眼根・その対境・空間・明るさ・意志という五つの因縁より生ずるようなものである。この場合、眼はただ眼自身の因縁を行ずるだけであって、他の因縁にはかかわらない。それがつまり事物が別であるという意味である。耳・鼻などの界もまたこのようなものである。
「諸仏如来は法界身である」(『観無量寿経』(第八像観))とは、法界は(さきにあげた眼界などのように)衆生の心の法そのものである。心は(因縁によって)世間・出世間のあらゆる法を生みだすから、心を法界と名づけるのである。(それゆえ)法界はまた諸々の如来の相好の身を生ずる。それは色界などが眼識を生ずるようなものである。だから仏の身を法界身というのである。この仏の身は(正道大慈悲出世の善根という浄因縁によって生ずるゆえに)他の(衆生の)業因縁によらず、一切の衆生の心想の中に入るというのである。
「心に仏を想うとき、この心がそのまま三十二相八十随形好である」とは、衆生が心に仏を想うとき、仏身の相好が衆生の心の中にあらわれるということである。たとえば、水が澄んでいればものの像がうつされる。水と像とは一つではないが、さりとて異なるものでもない。だから仏のすがた、かたちがそのまま衆生の心の想いである、というのである。
「この心が仏と作る」とは、衆生の仏を想う心が仏を作るということである。
「この心がそのまま仏である」とは、この衆生の作仏身のほかに仏はましまさないということである。
たとえば、火は木(をすりあわせること)から生じるから、火は木を離れてはいない。木を離れないから木を焼くことができ、それで木が火となるのであり、さらに木を焼いて火は火となるのである。〔信p.242〕
「諸仏正遍知海は心想より生ずる」。「正遍知」とは真であり正であって、(衆生の心想である)法界そのままに知るのである。法界は無相(と、さとるのが諸仏の智慧)であるから、「諸仏」はまた無知である。無知だから知らないことがない。無知であってしかも知であるのが正遍知である。だからこそ、その智慧が、深く、広く、はかりしることができないので「海」にたとえるのである。
『解読浄土論註』132頁
3 口業の徳(口業功徳)
如来の微妙の声、梵の響十方に聞こゆ。
この二句は荘厳口業功徳成就と名づける。
仏はもと、なぜこの荘厳をおこされたかというと、ある如来の名はかならずしも尊いおもいをあたえるとはかぎらないからである。たとえば外道が瞿曇(釈尊の生家の本姓)とその姓をよびすてにして仏を軽んじているようなものである。道を成じられてもその名はただ梵天にとどくばかりで(十方に聞こえないので)ある。
だから私が仏となるからには、その妙なる名声をはるか十方のはてまでおよばぬところのないようにゆきわたらせ、聞く者すべてをして無生法忍をさとらしめようと、とくに願っていわれたのである。
だから「如来の微妙の声、梵の響十方に聞こゆ。」とのたまわれたのである。
『解読浄土論註』135頁
4 心業の徳(心業功徳)
地・水・火・風・虚空に同じて、分別なからん。
この二句は、荘厳心業功徳成就と名づける。
仏はもと、なぜこの荘厳をおこされたかというと、ある如来を見られるのに、法を説く場合、これは黒(悪)これは白(善)これは黒でもなく白でもなく(無漏)、これは下法・中法・上法・上上法と説く。このような無量の差別の品類があって、法それ自体に分別があるかのようにうけとられる。
だから、私が仏となるからには、大地がものを荷負するのに、軽・重をわけることがないように。水がものをうるおし成長させるのに、悪草・薬草を区別することがないように。火がものを煮たきするのに、芳ばしい・臭いの別がないように。風がふきおこるのに、眠りをさまさせてやろうというような、はからいがないように。空間がものをうけいれるのに、まだあいている・もう一ぱいだという念のないように。このような無分別の心を内に得しめて、衆生を外なる万差のすがたに安んぜしめ、虚心に往って真実に満たされて帰ることここにきわまるように。と願っていわれたのである。
だから「地・水・火・風・虚空に同じて、分別なからん」とのたもうたのである。
『解読浄土論註』137頁
5 仲間たち(衆功徳)
天人不動の衆、清浄の智海より生ず。
この二句は荘厳衆功徳成就と名づける。
仏はもと、なぜこの荘厳をおこされたかというと、ある如来を見られるに、説法をされるところに、あつまったすべての大衆の根機、生まれつき習性、望みなどは種々不動であるため、(一味平等の)仏の智慧についてゆけず、(二乗に)退却したり(生死に)沈没したりするものがあるので、大乗が等しく清浄ではない。
だから、願わくは私が仏となるからには、あらゆる天人はみな如来の智慧清浄海より生まれるように、との願いをおこされたのである。
「海」とは、一切きわめつくされた仏の智慧が深広で涯がなく、二乗のあさい、よせあつめの善にもとづく縁覚・声聞などの残がいは全くとどめないということで、これを海にたとえたのである。
だから「天人不動の衆、清浄の智海より生ず」とのたもうたのである。
「不動」とは、彼の国の天人は大乗の根性を全うしていて、けっして動じないということである。〔行p.199〕
『解読浄土論註』139頁
6 須弥山王のごとし(上首功徳)
須弥山王のごとく、勝妙にして過ぎたる者なし。
この二句は荘厳上首功徳成就と名づける。
仏はもと、なぜこの願いをおこされたかというと、ある如来をみられるのに、教化せられる大衆のなかにことさらに強がる者がおる。たとえば提婆達多のたぐいなどである。あるいは国土と仏とが並んで国を統治していて、仏にゆずることをまったく知らないものがある。あるいは仏を請待しておきながら、ほかの用事にとりまぎれてすっかり忘れてしまったことなどがある。このように大衆の上首たる力が徹底していないようにみえることがある。
だから、願わくは「私が仏となるときは、すべての大衆は生まれたという自意識なく、したがってすべて私と等しからしめ、しかもただひとり法王として、さらにくらぶべき俗王のないようにしたい」と願っていわれたのである。
だから「須弥山王のごとく、勝妙にして過ぎたる者なし」とのたもうたのである。
『解読浄土論註』142頁
7 恭敬の道(主功徳)
天人丈夫の衆、恭敬して繞りて瞻仰したてまつる。
この二句は荘厳主功徳成就と名づける。
仏はもとなぜこの荘厳をおこされたかというと、ある仏如来を見られるに、所化の大衆があっても、そのひとびとのなかに仏を仏としてうやまわないものがいる。たとえばある比丘が釈迦牟尼仏に告げて、もし私のために十四の難問を解いてくれなければ、私はほかの道を学ぼうとおもう、といったようなものである。また居迦離が舎利弗をそしったのに対して、仏は三度いさめられたが三度とも拒否した、というようなものである。また外道の輩たちが、かりそめに仏の聴衆にまじって、つねに仏の短所がないかと、うかがっていたようなものである。また第六天の魔王がつねに仏のもとへやってきて、いろいろの妨害をくわだてたというようなことで、このような仏をうやまわないいろいろの相がある。
だから、私が仏となるからには、天人大衆は恭敬してものうきことのないように、と願っていわれたのである。
だから、ただ天人といっているのは浄土には女人や八部鬼神(というような人のそしりをうけるもの)がいないからである。
それで「天人丈夫の衆、恭敬して繞りて瞻仰したてまつる」とのたもうたのである。
『解読浄土論註』146頁
8 仏の住持の力(不虚作住持功徳)
仏の本願力を観ずるに、遇うて空しく過ぐる者なし、
能く速やかに功徳の大法界を満足せしむ。〔行p.167〕
この四句は荘厳不虚作住持功徳成就と名づける。
仏はもと、なぜこの荘厳をおこされたかというと、ある如来をみられるのに、ただ声聞ばかりをもって僧伽となして、真の仏道を求めるものがない。あるいは仏に値遇しながら、三悪道をまぬがれないものがある。善星・提婆達多・居迦離などがこれである。
また仏の名号を聞いてこの上ない求道心を発しながら、悪い因縁にあって声聞・独覚の二乗地にしりぞくものがある。このように空しく過ぎる者や退没する者などがある。
だから、私が仏となるときには、私に値遇するものはみな、無上の大宝をすみやかにとく満足するようにと願っていわれたのである。
だから「仏の本願力を観ずるに、遇うて空しく過ぐる者なし、能く速やかに功徳の大法界を満足せしむ」とのたもうたのである。
住持という意味はさきに(国土荘厳の主功徳成就の段で)のべたとおりである。
仏の荘厳たる八種の功徳を観察することは以上でおわった。
「観仏本願力 遇無空過者」というは、如来の本願力をみそなわすに、願力を信ずるひとはむなしく、ここにとどまらずとなり。
「能令速満足 功徳大宝海」というは、能はよしという、令はせしむという、速はすみやかにとしという、よく本願力を信楽する人は、すみやかにとく功徳の大宝海を信ずる人の、そのみに満足せしむるなり。如来の功徳のきわなくひろくおおきに、へだてなきことを大海のみずのへだてなくみちみてるがごとしと、たとえたてまつるなり。p.519 尊号真像銘文
③菩薩の荘厳
『解読浄土論註』151頁
つぎに、安楽国の諸々の大菩薩に四種の荘厳の功徳がまっとうしているさまを観察する。
問。如来の荘厳の功徳を観察したのに、このうえ何の不足があって、さらに菩薩の功徳を観ずる必要があるのか。
答。明君がましますときには必ず賢臣がある、というようなものである。堯や舜(という明君の政治)を無為と称するのも、このようなたぐいで(ことさら王が天下をおさめようとしないでも、民が安らかであったのは、賢臣あったからこそで)ある。もし、法王たる如来のみがましましても、法臣たる大菩薩がいなかったなら、仏道をたすけ、すすめてゆくのに十分ということが、どうしてできようか。また、たきぎを積みあげることが少ないときは、火もまた大きくならない、というようなものでもある。
『経』(浄土の三部経)に、阿弥陀仏の国には、数しれぬ大菩薩がたがおられ、観世音・大勢至といったようなかたは、みな一生他方世界にあり、次生には必ず仏の住処をおぎなうであろう、といわれているようなものである。
もし人が(それらの菩薩がたの)名を称え、憶念し、帰依し、観察すれば、『法華経普門品』に(観世音菩薩の徳について)説かれているように、いかなる願いであれ満たされないということはないのである。
ところで、菩薩が功徳を愛しもとめることは、あたかも海が川の流れをのんで、少しもあきる情のないようなものである。
たとえばこういうこともある。釈迦牟尼如来が、一人の失明の比丘の「誰か功徳を愛するものあらば、私のため針に糸をとおしてほしい」と、なげきうったえる声を聞かれて、ただちに如来は禅定より立ちあがられ、その比丘の所に至り、つぎのようにいわれた。「私は、さいわいなる功徳を愛するものである。あなたのため針に糸をとおしてやろう」と。
そのとき、失明の比丘は、暗に仏の語られる声を聞きわけ、驚きかつ喜んで、仏に申しあげた。「世尊よ、世尊にあってもその積まれた功徳は、まだ十分ではないのですか」と。仏はこたえられた。「私の功徳は円満していて、さらにもとめるべきものとてないが、ただ私のこの身は功徳によって生じたものであり、その功徳の恩をわきまえているが故に、いよいよ愛するというのである」と。
(以上であきらかなように)問いのとおり、仏の功徳を観察することで、十分願いは満たされているのであるが、さらに菩薩がたの功徳を観察するわけも、
ただただ上述のとおり、いろいろ意義があるからなのである。
『解読浄土論註』156頁
1 不動にして応化する徳(不動応化功徳)
安楽国は清浄にして、常に無垢の輪を転ず、化仏・菩薩の日、須弥の住持するがごとし。
仏はもと、どうしてこの荘厳をおこされたかというと、ある仏土を見られるに、小菩薩がましますばかりで、十方世界にわたって、ひろく仏の(衆生教化の)事業をなすことができない。あるいはまた、声聞や人天がいるばかりで、その利益するところはきわめて狭い。
だから、この願いをおこされたのである。願わくは、わが国土のなかには、はかりしれない数の大菩薩がいて、その場処を動かずに、あまねく十方世界に至って、いろいろその国土に応じてすがたをかえてあらわれ、真実(の力)のままに行じて、つねに仏の事業をなすように、と。
たとえば、日は天上にあって、しかもその影はあらゆる水面にあらわれる、というようなものであって、それは日そのものが水面に来ったのではないが、さりとて来ていないのでもない。
『大集経』にいわれている。「たとえば、人あって、池の堤をたくみにととのえ(水をため)、よいころをみはからって放水するときには、あれこれと思いをくわえなくても(自然と田地が)うるおされる、というようなもので、菩薩もまたこのように、まず一切の諸仏を供養し、一切の衆生を教化するためのもろもろの堤防をととのえれば、三昧に入るときいたって、身も心も動かさず、真実(の力)のままに行じ、つねに仏の事業をなすのである」と。
如実修行とは(真実の法の力のままに行ずることであるから)つねに修行しているけれども、しかも実際(作意的)に修行するところがない、ということである。
だから、「安楽国は清浄にして、常に無垢の輪を転ず、化仏・菩薩の日、須弥の住持するがごとし」とのたもうたのである。
小菩薩
三つの説がある。①下位(七地已下)の菩薩。②界内(三界内)の小行の菩薩。③小乗の菩薩。いまは②が適当かと思われる。
『解読浄土論註』160頁
2 同時に十方に至る徳(一念遍至功徳)
無垢荘厳の光、一念および一時に、普く諸仏の会を照らし、もろもろの群生を利益す。
仏はもと、どうしてこの荘厳をおこされたかというと、ある如来を見られるに、その眷属が、他方国土の数しれぬ仏たちを供養しようとおもい、数しれぬ衆生を教化しようとおもうときは、こちらを没してあちらにあらわれ、南を先にすれば北をあとにする、といったぐあいで、一念一時に光を放って、すべてを照らすことができない。これは、あまねく十方世界にゆきわたって、衆生を教化するのに、出と没、前と後といった相をとるからである。
だから願いをおこされたのである。願わくは、わが仏土の諸々の大菩薩は、一念のあいだに、あまねく十方世界に至って、いろいろの仏の事業をなすように、と。
だから「無垢荘厳の光、一念および一時に、普く諸仏の会を照らし、もろもろの群生を利益す」とのたもうたのである。
問。
上の意に、身を動かすことなく、しかもあまねく十方世界に至る、といっている。「動かずして至る」とは、とりもなおさず「一時に」という意味ではないか。(とすれば)この章とどのような差別があるのか。
答。上には、ただ「動かずして至る」といってあるだけだから、あるいは(その至り方に)前後があるかもしれない。ここには、前もなく後もないといっている。これが差別である。
また、この意は、上の「動かず」という意味をまっとうするのである。もし一時でなかったなら、往ったり来たりすることになる。往ったり来たりするのなら、不動というわけにはいかない。だから、上の章の「動かず」という意味をまっとうするために、「一時に」ということを、是非ともあきらかに観る必要があるのである。
『解読浄土論註』163頁
3 諸仏を供養する徳(無余供養功徳)
天の楽と花と衣と、妙香等を雨りて供養し、諸仏の功徳を讃ずるに、分別の心あることなし。
仏はもと、どうしてこの荘厳をおこされたかというと、ある仏土を見られるに、菩薩や人天の志ざすところが広くなく、あまねく十方のはてしない世界に至って、諸仏如来と大衆を供養することができない。また、自分の国土が穢れ濁っているので、(それを恥じて)あえて浄らかな郷におもむこうとしなかったり、住んでいるところが清浄なので、(それを誇って)穢れた国を軽蔑したりする。このようないろいろの局分があるので、諸仏如来の所をめぐりめぐって供養し、広大なる善根をおこすことができないのである。
だから願って、私が仏となるからには、わが国土のすべての菩薩・声聞・天人大衆は、あまねく十方の一切の諸仏の大会の処に至って、すぐれた音楽、妙なる花、みごとな衣、すばらしい香をあめふらし、巧妙な弁辞で諸仏の功徳を供養し、讃嘆しよう、といわれたのである。
穢土にまします如来の大慈悲の、つつしみぶかく忍耐づよいことを讃えこそすれ、その仏土のさまざまに穢れた相を見ることなく、浄土にまします如来の、はかりなき荘厳を讃えこそすれ、その仏土の清らかな相を見ることはないのである。
なぜかといえば、諸法は平等であるから、諸々の如来は平等である。だから、諸仏如来を等覚というのである。もし仏土について、優劣を差別するこころをおこせば、たとえ如来を供養したとしても、法にかなった供養ではない。
だから「天の楽と花と衣と、妙香等を雨りて供養し、諸仏の功徳を讃ずるに、分別の心あることなし」とのたもうたのである。
『解読浄土論註』166頁
4 「三宝なき世界」へはたらく徳(遍至三宝功徳)
何等の世界にか、仏法功徳の宝ましまさぬ。我願わくはみな往生して、仏法を示すこと仏のごとくせんと。
仏はもと、どうしてこの願いをおこされたかというと、ある意志の弱い菩薩を見られるのに、ただ仏がまします国土で修行することばかりを楽って、(無仏の国に仏道をおこそうとするような)堅い慈悲の心がない。
だから願いをおこされ、私が仏となるときは、わが国土の菩薩は皆、慈悲の心が勇猛でしっかりしており、自ら願って清浄の国土をすて、他方国土の仏法僧ましまさぬ処に至って、仏法僧の三宝を常にたもって失わしめずに荘厳し、それを人々に示すこと、あたかも仏がましますごとくにして、仏法の種をいたるところに(まいて)絶やさないようにしよう、と願われたのである。
だから「何等の世界にか、仏法功徳の宝ましまさぬ。我願わくはみな往生して、仏法を示すこと仏のごとくせんと」とのたもうたのである。
菩薩の四種の荘厳の功徳のまっとうしたことを観ずることは、以上でおわった。
十 回向
『解読浄土論註』170頁
つぎに、下の四句は回向門である。
我れ論を作り、偈を説きて、願わくは弥陀仏を見たてまつり、
普くもろもろの衆生と共に、安楽国に往生せん。
この四句は、論主自らの回向門である。
回向とは、自らがつんだ功徳をめぐらして、ひろく生きとし生けるものにめぐみ、ともに阿弥陀如来を見たてまつり、安楽国に生れよう、ということである。
無量寿修多羅の章句 我れ偈誦をもって総じて説きおわんぬ。
回向 『真宗新辞典』
めぐらしさしむけること。如来がその徳を衆生にめぐらし施して救いのはたらきをさしむけること。自力の心をひるがえして願力にむかわせること。
聖道門では、自分の修した善因を仏果菩提を得ることにさしむけ(菩提回向)、自己の善根功徳を他の衆生を利益するためにさしむけ(衆生回向)、善根の事を平等の理にさしむけて一一の善が真如法性の顕現であると観じて平等法身の理をさとること(実際回向)を意味し、これを三種回向という〔大乗義章〕。
親鸞はこれらの挟善趣求の自力回向に対して他力回向の説をたて、大経の本願成就文を「至心に回向したまへり」と訓読して如来の救済のはたらきの絶対性を強調し、曇鸞の浄土論註の説にもとづいて、衆生が浄土に往生してさとりをひらく往相も、滅度を証してから穢土に還って利他教化のはたらきをあらわす還相も、すべては弥陀の本願力のしからしむる所であり、仏から衆生にさしむけられたものであるとする。
浄土真宗に、往相回向と還相回向との二種回向があり、往相回向について真実の教行信証があるとし〔教巻〕、本願力の回向に二種の相があると説く〔浄土文類聚鈔〕、他力念仏の行は自力回向の行ではないから行者にとっては「不回向の行」〔行巻〕であり、浄土に生れたいとおもう欲生心も自力の回向心でないから「不回向」〔信巻〕であるとする。
念仏と諸善、本願と要門を対比して、回不回向対〔行巻〕、不回回向対〔愚禿鈔〕を立てる。「一念のほかにあまるところの念仏は十方の衆生に回向すべし」〔親鸞証人御消息集〕という回向は常行大悲の報恩行であり自力の回向ではない。
道綽は六種回向の説をたて①諸善を回向して往生し、自在に衆生を教化する、②因から果へ、③下から上へ、④遅から速へと、「世間に住せざる」現状から目標への志向、⑤衆生に廻施して善に向かわせる、⑥廻入して分別の心を去ること〔安楽集〕、
源信は五種回向をあげる。また、回向の意味に、回因向果、回思向道、廻入向他の三義があるという〔選択註解鈔〕。
なお、亡くなった人に対する追善(追薦)を回向ということがあるが、真宗の仏事は仏恩報謝のいとなみであり、追善回向ではない。勤式の終に唱える偈文を仏教一般にならって回向文といい、「願似此功徳…往生安楽国」〔観経四帖疏・玄義分〕、「世尊我一心…願生安楽国」〔浄土論〕、「我説彼尊功徳事…廻施衆生生彼国」〔十二礼〕を用いる。
十一 八番問答
1 普く諸の衆生と共に
問(一)。天親菩薩は回向門の章のなかで、「あまねく諸の衆生と共に、安楽国に往生せん」といわれているが、これはどのような衆生を「共に」と指しておられるのか。
答。王舎城で説かれた『無量寿経』(大経)をひもとくに、つぎのようにいわれている。「仏は阿難に告げたもうた。十方の恒河の砂の数ほどもある無数の諸仏如来は、みなともに無量寿仏の大いなる功徳の不可思議なることを称嘆されている。あらゆる衆生は、諸仏が称嘆したもう無量寿仏の名号を聞いて、信じよろこぶ心を、せめて一念でもおこすであろう。(無量寿仏は)まことの心をもって、(そのような信心をわれらに)めぐらしてくださっている。だから(そのような信心をおこし)彼の安楽国に生れたいと願いさえすれば、そのときそのまま往生することができ、ふたたび退転しない世界に住することができるのである。ただ五逆の罪をおかすものと、正しい法をそしる者は、このかぎりではない」と。
この文のこころを思いめぐらせば、すべての外凡夫の人が、みな往生できるのである。
また、『観無量寿経』に説かれているように、九種類の往生がある。「下の下の部類の衆生の往生とは、ある衆生は、不善の業たる五逆(①母を殺し②父を殺し③聖者を殺し④仏の身体を傷つけ血をいだし⑤教団を破り、分裂させること)・十悪(①生命をそこなう②盗む③よこしまな男女関係④うそをつく⑤二枚舌をつかう⑥悪いことば⑦かざりことば⑧むさぼり⑨いかり⑩おろかさ)の罪をつくり、
その他いろいろの善からぬことをなしている。このような愚かものは、まさにその悪業のために、悪道に墜ち、長いあいだくりかえしくりかえし苦しみを受けて止むことがないであろう。このような愚かものが、いまわのときに、このものをいろいろなぐさめ、このもののためにすぐれた法を説き、教えて仏を念じせしめる善き人に遇う。しかし、彼は苦しみにさいなまれていて、(心をしずめて)仏を念ずるいとまもない。そこで善き人はつげて「あなたは、もし心に仏を念ずることができないのならば、無量寿仏と口に称えよ」という。このように心をつくし、声を絶やすことなく、十念をそなえて南無阿弥陀仏と称えれば、仏の名を称えるが故に、その一念一念の中に、八十億劫ものあいだ彼を生死につないでいた罪がのぞかれ、命おわるや、金の蓮華が、あたかも日輪のようにかがやいて、その人のまえにあらわれ、またたく間に(この蓮華につつまれて)極楽世界に生れることができるであろう。蓮華の中で、十二大劫のときが満ちると、蓮華はまさしく開け(まさにこのとき、五逆の罪はつぐなわれる)、観世音菩薩と大勢至菩薩とが、大悲の音声をもって、そのもののために、広く諸法実相が罪をのぞき滅する法(即ち名号)を説くであろう。その人はこれを聞きおわって、歓喜し、即座に大菩提の心を発すであろう。これを下の部類のなお下のものの往生というのである」と。
この経をもって証とすれば、下の部類の凡夫が、正しい法をそしることがなければ、ただ仏を信ずることのみをよすがとして、みな往生することができる、ということはまことに明らかである。
諸法実相
諸法は、ありとあらゆる存在現象の差別の相。実相は、正覚よりみた諸法の体の平等の相。すなわち、存在の不変・常住の理、いわゆる真如の理。いまは、あらゆる功徳(法)をおさめた名号のことをいう。
2 往生
『解読浄土論註』176頁
問(二)。『無量寿経p.044』では、往生を願うものはみな往生できるが、ただ五逆のものと、正法をそしるものは、そのかぎりではない、といわれている。『観無量寿経p.120』では、五逆・十悪をおかし、いろいろの善からぬことをなしているものもまた往生することができるといっている。この二経(の差異)は、どのように理解すべきなのか。
答。一経に説かれてあるのは、二種の重罪をともにおかしているからである。つまり、一には五逆、二には正法をそしることである。この二種の罪のために往生できないのである。
一経には、ただ十悪や五逆などの罪をつくるとのみいって、正法をそしるとはいっていない。正法をそしることがないから、往生できるのである。
3 謗法の罪人は救われるのか
問(三)。たとい、ある人が五逆の罪をもっていても、正法をそしらなければ往生できる、と『経』に認めているのならば、ひるがえって、ある人が正法をそしるだけで、五逆などのいろいろな罪がなくて往生を願えば、往生できるというのだろうか。
答。ただ正法をそしるだけで、まったくほかの罪がないとしても、決して往生することはできないのである。
なぜかといえば、『経』(般若経)にいわれている。「五逆の罪人は、阿鼻大地獄に堕ちて、つぶさに一劫の重罪をうける。
正法をそしる人は、阿鼻大地獄に堕ちて、この(地獄での苦をうける)時劫がつきると、また転じて他方の阿鼻大地獄に至る。このように、つぎつぎと転じて、百千の阿鼻大地獄の中をへめぐるのである」と。
仏は、この地獄を出ることのできる時節を記されていない。正法をそしる罪が極めて重いからである。
また、正法とは即ち仏法のことである。この愚痴なるものは、すでに(その仏法を)そしっているのである。どうして仏の国土に生れたいと願う道理があろうか。たとえ、ただ彼の国土が、安楽なところだから生れたいと貪って、往生を願っても、それはあたかも、水によらない氷、煙のない火を求めるようなものである。どうして往生できる道理があろうか。
4 謗法の罪とは何か
『解読浄土論註』179頁
問(四)。どのような相が、正法をそしることであるのか。
答。たとえば、仏もなく仏の法もなく、菩薩もなく菩薩の法もない、という。このような見解で、自ら解釈したり、他の考えにしたがって、その心をうけて断定したりするのをすべて、正法をそしるというのである。
5 謗法の罪はなぜ重いか
問(五)。このような(正法をそしるところの)計というものは、ただ自己一人にかかわることであって、他の衆生に何の苦しみをあたえるものでもないのに、どうして(他の衆生に苦しみをもたらすところの)五逆の重罪よりもなお重いのか。
答。もし、諸仏や菩薩が、世間の善き道、出世間の善き道を説いて、衆生を教化することがなかったなら、どうして(人々が)仁義礼智信(の道)のあることをわきまえることができようか。このような世間すべての善き法は、みななくなり、出世間のすべての賢者・聖者もみな、ほろびてしまうであろう。あなたは、ただ五逆の罪の重いことだけを知っていて、五逆の罪が、正法のないことから生ずることを知らないのである。だから、正法をそしる人は、その罪が最も重いのである。
6 業道の超越
『解読浄土論註』184頁
問(六)。業道について説かれた『経』には、「業道は、秤のように、重いほうへひきつけられる」といってある。『観無量寿経』では「五逆・十悪をおかし、いろいろの善からぬことをなすものは、まさに悪道に堕ち、長いあいだをへめぐって、はかりしれぬ苦をうけるであろう。(しかし)いまわのときに、善き人の教えに遇い、南無阿弥陀仏と称える。このように心をつくし、声を絶やすことなく、十念を具足するならば、そのときそのまま安楽浄土に往生して、大乗の正定をえた聚に入ることができ、もう二度と退くことなく、三塗のもろもろの苦しみを、永にはなれるのである」といってある。(とすれば)業が重いほうへひきつけられるという意義は、道理としてどうなのか。
また、永遠のむかしより、人はすべていろいろな行為をしてきて、その煩悩にけがれた法は、三界につなぎとめられるものとなっている。(にもかかわらず)ただ十念、阿弥陀仏を念ずるだけで、たちまち三界を、でることができるというのなら、業によってつながれるという意義は、またどのように考えればよいのか。
答。あなたは、五逆・十悪といった(三界に)つなぎとめられる業などのほうを重とし、下の下の部類の人の十念のほうを軽として、だから罪のためにひかれてまず地獄に堕ち、三界につなぎとめられるはずだという。それではいま、道理をもって、(どちらの業が)軽いか重いかを比較することにしよう。
(業の軽重は)「心に在り」、「縁に在り」、「決定に在る」のであって、時節の長い短かい、多い少ないにあるのではない。
どのように「心に在る」のか。かの五逆・十悪などの罪をつくる人は、自ら虚妄顛倒のおもいにとらわれて罪をつくる。この十念は、善き人がいろいろ手だてをつくして慰め、実相の法(即ち名号)を説かれるのを聞くことによって生じる。一方は実、一方は虚である。どうして比較できようか。たとえば、千年このかたの闇室に、もし光が少しでもさしこめば、そのときたちまち明るくなる、というようなものである。闇が室に千年あったからといって、どうして(その闇が)室をはなれないということができようか。これを「心に在る」というのである。
どのように「縁に在る」のか。かの罪をつくる人は、自ら妄想の心にあり、煩悩虚妄のむくいをうけている衆生によって罪を生じるのである。この十念は、このうえなき信心をえ、阿弥陀如来のたくみな手だてである荘厳、真実の清浄さをそなえた、はかりしれぬ功徳の名号によって、(十念を)生じる。たとえば、ある人が毒矢をうけて、筋をきられ、骨を破られても、滅除(という名の)薬をぬった鼓の音を聞くと、たちまち矢がぬけ、毒ものぞかれる、といったようなものである。(『首楞厳経』にいわれている。「たとえば、滅除という薬があって、もし、たたかいのとき、これを鼓にぬり、そのたたく音を聞けば、矢はぬけ、毒ものぞかれる。大菩薩もまたこのように、首楞厳三昧に住していて、その三昧の名を聞けば、三毒の矢は自然とぬける」と。)どうしてかの矢が深くささり、毒がはげしくて、鼓の音を聞いても矢がぬけず、毒もさらないということがあろうか。これを「縁に在る」というのである。
どのように「決定に在る」のか。かの罪をつくる人は、後があると油断する心、雑念のまじわる心によって罪を生じる。この十念は、後をあてにしない(緊張した)心、雑念のまじわらない(ひたむきな)心によって生じるのである。これを「決定に在る」というのである。
この三義において比較すれば、十念のほうが(業が)重い。(だから)重いほうへひきつけられて、三界をでることができるのである。両経(業道について説かれた経と観経)の義はまったく一つである。
『業道経』
業道について説かれている経の意。業道という名の経があるのではない。それ故『安楽集』巻上では「大乗経に云く」として同じ文が引かれている。『惟日雑難経』に「秤の重き者に随うて、これを得るが如し」とあり、『道地経』に「譬えば、称の一上一下する如く、是の如く死を捨て生の種を受く」とある。称と秤は同じ意。
7 一念の自覚
『解読浄土論註』190頁
問(七)。どれほどの時間を一念というのか。
答。百一の生滅を一刹那といい、六十刹那を一念という。しかし、この『観経』の中に「念」というのは、このような時間についていうのではない。
ただ(ここに一念と)いわれているのは、阿弥陀仏の全体の相なり、一部の相なりを憶念して、そこに観じられてくるままにまかせて、心にほかの想いをいれず、十念が相続するのを、名づけて十念とするのである。また、ただ口に仏の名号を称えるのだけでも、このようにいえるのである。
8 み名を称す
問(八)。(十念する)心に、もし他のことを思いうかべれば、これをとりはらい、心をもとにかえして、仏を念ずる数の多い少ないを知るはずである。(しかし)ただ数の多い少ないを知るだけでも、雑念がまじわっていないとはいえない。
(かといって)もし心を集中させて、想いを仏にそそげば、こんどはどうやって念ずる数の多い少ないを心にきざむことができるのか。
答。『観経』にいうのは、十念とは往生の業がまっとうしたことを明かすのみで、必ずしも念ずる数の多い少ないを知る必要はない、ということである。たとえば、夏ぜみは、春や秋を知らない。といってこの虫自体が、いまは夏の季節だということを知るはずもない、というようなものである。それを知る者が、夏の季節であるというだけである。十念の業がまっとうしたというのも、これと同じで、(人間の)はかりしれぬ境地に到達したもののみが、十念というのである。
(われわれのほうは)ただひとえに念をつみつづけ、他のことをおもいうかべないなら、それで十分なのである。そのうえどうして、かりそめにも念ずる数を知る必要があろうか。もし、どうしても知る必要があるのならば、いろいろ手だてもあるが、それは必ず口授すべきものであって、筆でこれを書きしるすことはできないのである。
無量寿経優婆提舎願生偈註 巻上(おわり)
百一生滅名一刹那
一刹那は時間の最小単位。しかし、その中に百一の生滅があるとする説は、出拠不明。
尚、『安楽集』巻上には「経に説きて云うが如し、百一の生滅を一刹那と成す」とあり、ここからおせば、そのような説をなす『経』があったとも考えられるが、一方、道綽はこの『論註』の文を見て、このようにのべたとも考えられる。